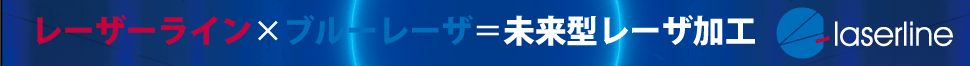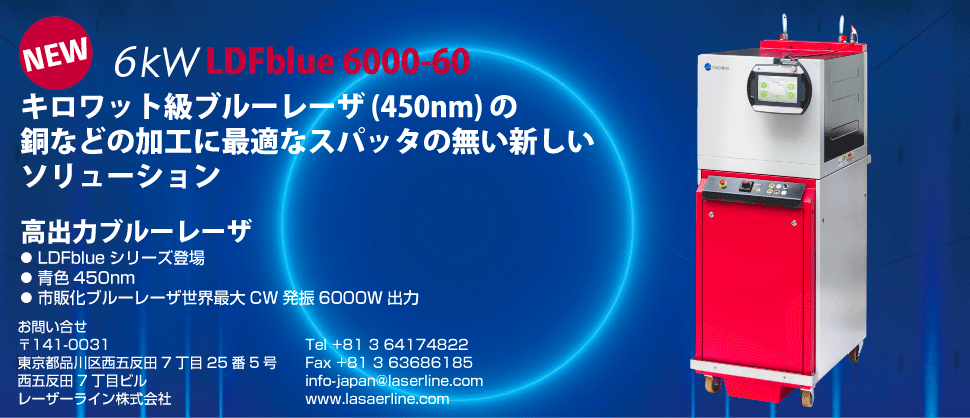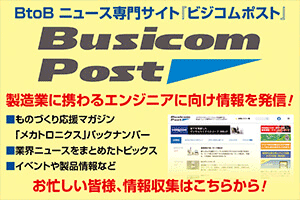Science/Research
April, 22, 2024, Wien--
ウィーン工科大学とMedUni Viennaの共同プロジェクトでは、脳線維の構造をモデル化し、磁気共鳴画像法(dMRI)の特殊なバリエーションを使用して画像化できる、世界初の3Dプリントされた「ブレインファントム」が開発 […]
April, 19, 2024, 東京--
東京工業大学 科学技術創成研究院の小田部荘達特任助教と理学院 物理学系の宗宮健太郎准教授らの研究チームは、量子光学の技術を応用して光バネを硬くすることに世界で初めて成功した。 光バネは、向かい合わせに配置した鏡の間の空間 […]
April, 19, 2024, Oak Ridge--
米国エネルギー省のオークリッジ国立研究所(ORNL)の科学者たちは、アディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンティング)で製造された大型金属部品に、材料の残留応力によって引き起こされる、コストがかかり、修復不能な損 […]
April, 18, 2024, 和光--
理化学研究所(理研)などの共同研究グループは、1次元と2次元という異なる次元性を持つナノ半導体の界面において室温で動作する量子光源が存在することを発見した。 この研究成果は、量子通信や量子計算などの量子技術への応用に貢献 […]
April, 18, 2024, Waterloo--
ウォータールー大学(University of Waterloo)の量子コンピューティング研究所(IQC)の研究者は、量子通信の分野を前進させるために、ノーベル賞を受賞した2つの研究コンセプトをまとめた。 科学者は、量子 […]
April, 18, 2024, Gainesville--
フロリダ大学のエンジニアは、蒸気誘起相分離3Dプリンティング(VIPS-3D)と呼ばれる3Dプリンティングの方法を開発し、単一材料および多材料のオブジェクトを作成した。 フロリダ大学(University of Flor […]
April, 17, 2024, Aachen--
光学産業は、プロセスチェーンの機械的プロセスにほぼ完全に依存している。しかし、この状況はすぐに変わる可能性がある。アーヘンのFraunhoferILTレーザ技術研究所は、非球面および自由曲面光学系の成形、研磨、最終形状の […]
月への次のステップ:LZHとTUベルリンがAstroboticと提携
April, 17, 2024, Hannover--
MOONRISEプロジェクトでは、研究者が月に3Dプリントを持ち込むことに取り組んでいる。Laser Zentrum Hannover e.V.(LZH)は、2026年後半に予定されている月への飛行について、Astrob […]
April, 16, 2024, Pasadena--
カリフォルニア工科大学(Caltech)の医用工学助教授Wei Gaoは、汗を使って生理学的状態を識別・測定するウェアラブルセンサの革新的な設計シリーズの最新作として、ストレス反応を特徴付ける9つの異なるマーカーを連続的 […]
ガン診断に未踏の波長を利用~安全性の高い短波赤外蛍光色素を開発
April, 16, 2024, 札幌--
北海道大学などの共同研究チームは、短波赤外蛍光イメージングの医療応用に向けた蛍光色素の開発に成功した。 研究成果は、短波赤外光を利用した非侵襲イメージング技術を医療応用するうえで非常に重要な基礎技術となる。 短波赤外蛍光 […]
April, 16, 2024, 札幌/岡山--
北海道大学電子科学研究所の渋川敦史准教授、三上秀治教授、岡山大学学術研究院医歯薬学域(薬)の須藤雄気教授、韓国科学技術院(KAIST)生物・脳工学科のMooseok Jang助教授らの研究グループは、超高速の光パターン照 […]
April, 15, 2024, Freiburg--
量子コンピュータを接続して性能を向上させたり、通信チャネルを盗聴防止で暗号化したり、原子時計を同期させたりして、衛星ナビゲーションや科学実験のための高精度な時間測定を実行するなど、量子インターネットは様々な重要技術分野で […]
April, 15, 2024, New York--
Weill Cornell MedicineとCornell Engineeringの研究者は、最先端の組織工学技術と3Dプリンタを使用して、見た目も感触も自然な成人の人間の耳のレプリカを組み立てた。 Acta Biom […]
原子層ナノ物質と微小光共振器による高効率波長変換に成功-ナノフォトニクス素子の高機能化へ期待-
April, 12, 2024, 東京--
理化学研究所(理研)光量子工学研究センター 量子オプトエレクトロニクス研究チームの加藤雄一郎 チームリーダー(理研 開拓研究本部 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 主任研究員)、藤井瞬 基礎科学特別研究員(研究当時、現 慶 […]
April, 12, 2024, Lausanne--
EPFLの研究者は、ニューラルネットワークを使用して、脳が体の動きと位置を「知る」ために使用する感覚である固有受容感覚を研究している。 脳は、体の様々な部分の位置や動きをどのように知っているか?この感覚は固有受容感覚と呼 […]
April, 11, 2024, Amsterdam--
AMOLFの研究者らは、ドイツ、スイス、オーストリアのパートナーと共同で、これまでにない方法で音波が流れる新しいタイプのメタマテリアルを実現した。 これは、機械振動を増幅する新しい形を提供し、センサ技術や情報処理デバイス […]
毎秒数兆フレーム処理により光学イメージングの限界を押し広げる
April, 11, 2024, Quebec--
INRS のJinyang Liang教授のチームは、新しい超高速カメラシステムでイメージング速度を向上させた。 より速いスピードを追求することは、アスリートだけのことではない。研究者もまた、発見によってそのような偉業を […]
April, 9, 2024, New York--
10年前に米国国立標準技術研究所(NIST)で開発された光リファレンスと光周波数コムを利用した光周波数分割(OFD)は、これまでで最も安定したマイクロ波信号を生成するために使用されている。このアプローチでは、通常、複数の […]
April, 9, 2024, 仙台--
東北大学 多元物質科学研究所の津留志音 大学院生(同 大学院工学研究科)、小澤祐市 准教授、上杉祐貴 助教、佐藤俊一 教授のグループは、ベクトルビームと呼ばれる特殊なレーザ光をガラスの裏面に集光する条件において、ガラス界 […]
April, 8, 2024, 東京--
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 量子複雑性解析理研白眉研究チームの桑原知剛 理研白眉チームリーダー(開拓研究本部 桑原量子複雑性解析理研白眉研究チーム 理研白眉研究チームリーダー)、ヴー・バンタン 特別 […]
April, 8, 2024, Vienna--
MedUni ViennaとTU Wienの共同プロジェクトでは、脳線維の構造をモデルにした世界初の3Dプリントされた「ブレインファントム」が開発され、磁気共鳴画像法(dMRI)の特殊なバリアントを使用して画像化できるよ […]
複数ドローン着陸技術「EAGLES Port」が強風下での精密着陸を実現
April, 8, 2024, 東京--
東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センターは、同センターが開発し特許取得済みの複数ドローン着陸技術「EAGLES Port」が、風の強い条件下でのドローンの着陸性能を大幅に向上させることを、風洞施設での実機実験によ […]
April, 5, 2024, Washington--
新しい臨床試験の結果は、手術中に前立腺ガンの断端を検出するための構造化照明顕微鏡(SIM)の可能性を示している。この機能により、外科医はすべてのガン組織を確実に除去することができ、ガンの再発を減らし、治療成功の可能性を高 […]
April, 5, 2024, Washington--
ワシントン大学の研究者は、スエプト照明光源をオープントップのライトシート顕微鏡に組み込み、より広い視野で光学セクショニングを改善した。この進歩により、この技術は非破壊3D病理学においてより実用的になる。 3D病理学は、組 […]
April, 4, 2024, 東京--
KDDIスマートドローン株式会社(KDDIスマートドローン)、株式会社KDDI総合研究所(KDDI総合研究所)、株式会社プロドローン(プロドローン)は、2024年3月5日、新たに共同開発した水空合体ドローン新型機で、未来 […]
前方励起ラマンユニットを用いた双方向励起ラマン増幅によるC+Lバンド800 Gbps伝送信号光の品質を向上
April, 4, 2024, 東京--
古河電気工業株式会社は、前方励起ラマンユニットを用いた光伝送システムにおけるC+Lバンド 800Gbpsの伝送信号光の品質を向上させた。 前方励起ラマンユニットの増幅帯域をCバンドのみからC+Lバンドに拡張し、C+Lバン […]
April, 4, 2024, 東京--
情報通信研究機構(NICT)フォトニックネットワーク研究室を中心とした国際共同研究グループは、光ファイバ伝送で世界最大の37.6THzの周波数帯域を活用し、378.9Tb/sの伝送実験に成功し、既存光ファイバの伝送容量の […]
April, 3, 2024, 東京--
量子科学技術研究開発機構(QST)量子技術基盤研究部門関西光量子科学研究所の森道昭上席研究員らの研究グループは、米国のカリフォルニア大学アーバイン校、カナダのウォータールー大学と共同で、細孔が多数開いたガラス板(マイクロ […]
April, 1, 2024, Lausanne--
EPFLの神経科学者は、心臓と肺を調節する脳の深部構造に単一のニューロンを見つけた。この成果は、脳と身体のシステムが、両方の重要なバイオリズムを自己制御する仕組みを明らかにした。 体はホメオスタシスと呼ばれるプロセスで自 […]
March, 29, 2024, Washington--
中国の研究者は、皮膚の血管の高解像度イメージングのための光音響イメージングウォッチを開発した。 ウェアラブルデバイスは、心拍数、血圧、酸素飽和度など、人の心臓がどれだけうまく機能しているかを示すことができる血行動態指標を […]











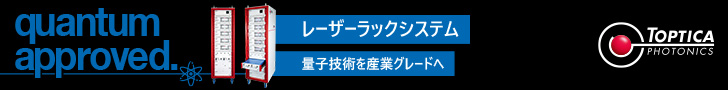
 レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。
レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。