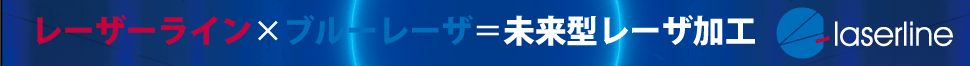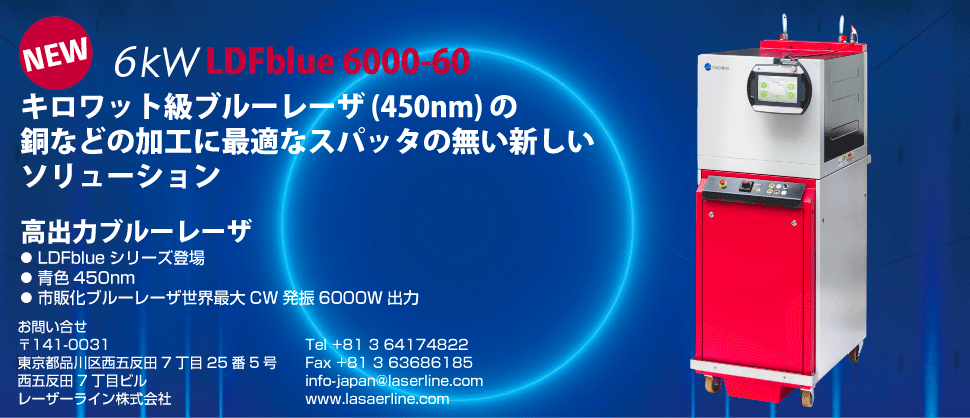国内リポート 詳細
ポストコロナ時代の新しい光科学
理化学研究所・光量子工学研究センターが第10回光量子工学研究シンポジウムを開催
January, 10, 2023, 東京-- 理化学研究所(理研、理事長:五神真氏)は、日本で唯一の自然科学総合研究所だ。物理学や工学、化学、数理・情報科学、計算科学、生物学、医科学など、幅広い分野において研究を推進してきた。1917年(大正6年)に財団法人として創設された同研究所は戦後、株式会社科学研究所、特殊法人時代を経て、2003年(平成15年)、文部科学省所轄の独立行政法人として再発足、2015年(平成27年)に現在の国立研究開発法人となった。研究成果を社会に普及させるために大学や企業との連携による共同研究、受託研究等を推進するとともに、知的財産等の産業界への技術移転にも積極的に取り組んでいる。
研究組織は、情報統合本部、科技ハブ産連本部、開拓研究本部、革新知能統合研究センター、生命医科学研究センター、生命機能科学研究センター、脳神経科学研究センター、環境資源科学研究センター、創発物性科学研究センター、量子コンピュータ研究センター、光量子工学研究センター、仁科加速器科学研究センター、計算科学研究センター、放射光科学研究センター、バイオリソース研究センターなどで構成されており、研究拠点は、宮城県仙台市(仙台地区)、茨城県つくば市(筑波地区)、埼玉県和光市(和光地区)、東京都中央区(東京地区)、神奈川県横浜市(横浜地区)、愛知県名古屋市(名古屋地区)、けいはんな学研都市(けいはんな地区)、大阪府吹田市(大阪地区)、兵庫県神戸市(神戸地区)、兵庫県佐用郡(播磨地区)などに設けられている。
同研究所は創設以来、科学者の好奇心と野心を原動力として、既存領域に囚われず未踏の知を求めるとともに、社会で人々の暮らしを豊かにするために役立てることを目指し活動を続けてきた。昨年には、そのあるべき姿は「科学者自身が究めたいと願う研究が、人類の未来のために必要となる学知の創造と重なり、科学と社会との相互の信頼が深まることで、互いに“つながっていく”場」だとして、新たな行動指針「RIKEN’s Vison on the 2030 Horizon」を公表している。
指針では、理研が世界に誇る最先端研究プラットフォーム群を、高度なデータの生成、最先端のAIや数理科学による新たな解析法の開拓、スーパーコンピュータと量子コンピュータを軸とした先端の計算科学において連環させ、既存の分野やパラダイムを越えて科学を繋ぎ、新たな知恵を創造する「Transformative Research Innovation Platform of RIKEN platforms(TRIP)」構想が打ち出され、五神理事長はこの指針に沿って今年実際の行動を起こしたいと述べている。
ポストコロナ時代における新しい光の利用・応用
昨年12月20日(火)と21日(水)の両日には、同研究所の光量子工学研究センター主催による理研シンポジウム「第10回光量子工学研究-ポストコロナ時代の新しい光科学」が、和光事業所の鈴木梅太郎記念ホールとオンラインで開催された。
開催にあたって、研究センター長の緑川克美氏は、「光量子工学研究センターでは、光の可能性を極限まで追求し、今まで見えなかったものを見ようとしている。例えば電子の動きを捉えるアト秒パルスレーザー、可視光でナノメートルの世界を見る超解像顕微鏡、メタマテリアルによる光の操作、超高精度な光格子時計による相対論的な測地学、人類に新たな目を提供するテラヘルツ光・・・。見ることができれば、それを理解し、制御することにも可能になる。光量子工学研究センターでは、最先端の光技術を研究の世界だけのものとせず、広く応用展開し社会的課題の解決に貢献することを目指している」とシンポジウムの挨拶文に記している。
今回のシンポジウムでは、ポストコロナ時代における新しい光の利用・応用を見据え、光の有するポテンシャルを極限まで追求すべく「ポストコロナ時代の新しい光科学」と題し、我が国の光科学を牽引する研究者による招待講演6件に加え、研究センターの若手ならびに異分野研究者による18件の最新研究成果報告、さらにはポスターセッションなども行われ、築くべき光科学の将来像が議論された。
本稿でそのすべてを紹介することはできないので、以下に招待講演のタイトルと講演者を記すとともに、次章においては未だ感染の収拾が見えない新型コロナウイルスを高感度で迅速に、かつ全自動で検出する、同研究所開拓研究本部の渡邉力也氏による「1分子定量法を基盤とした新型コロナウイルスの迅速診断技術」の概要を紹介したい。
【招待講演】
◆欲しい性能から材料をデザインする- MIntにおける逆問題解析の挑戦:出村雅彦氏(物質・材料研)
◆自動化トランススケールスコープが拓く新たな世界観:永井健治氏(阪大産業科学研究所、他)
◆光周波数コムによる光の自在制御・操作技術とその応用展開:美濃島薫氏(電通大情報理工学研究科)
◆1分子定量法を基盤とした新型コロナウイルスの迅速診断技術:渡邉力也氏(理研開拓研究本部)
◆極薄X線ライトシートを使った三次元イメージング(fs X線レーザーの構造光を用いた元素敏感な微細加工実験を含む):香村芳樹氏(理研放射光科学研究センター)
◆フォトニック結晶レーザー(PCSEL)の進展:野田進氏(京大工学研究科)
新型コロナウイルスを高感度・迅速に全自動で検出
新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、汎用的なウイルス感染診断法の確立が求められている。これまでの感染診断は、ウイルス由来の遺伝子をPCRなどで増幅・検出する方法や、タンパク質抗原を抗体反応によって検出する方法が主流だった。しかしながら、これらは感度や精度、計測時間のいずれかで技術的な欠点を持っており、大量の検体を高効率・高感度・高精度に解析して、感染診断につなげることは非常に難しいというのが実状であった。この課題を解決しようと、世界中でウイルス検出のための様々な分析技術が開発されてきた。しかし、その大半は既存技術を改良・改善したものに過ぎず、まったく新しい検出原理に基づいた分析技術の開発に大きな期待が集まっている。
渡邉氏の研究チームは、生物物理学の基礎研究で培ってきた「マイクロチップを用いた生体分子の1分子定量法」と「CRISPR-Casを用いた核酸検出技術」を融合させ、新型コロナウイルスなどのRNAウイルスを1分子単位で高感度かつ世界最速(9分以内)で全自動検出できる独自技術「SATORI法」を開発した。SATORI法は、PCR検査や抗原検査とは原理が異なる新しい検査方法。検体の前処理(精製・増幅)の必要がないので、1分子レベルでの迅速な検出が可能になった。
研究チームは、顕微鏡と連動・実装できる分注ロボットも開発して、サンプル調製から画像取得、陽性判定までの全自動化を実現、さらには新種のCas13(LtrCas13)を採用するとともに、ウイルスのRNA遺伝子を磁気ビーズに取り込み、これを微小試験管の裏面に設けた磁石で強制的に補足する方法を開発、この組み合わせによって、これまでの1400倍という高感度化を実現した。1塩基単位の変異解析から変異株を判定する新技術「1本鎖RNA精製法」の開発・実装にも成功し、臨床検体を用いた実証実験において、陽性判定および罹患している変異株判定の正解率98%という高い値も達成した。
低コスト化についても、マイクロチップの作製法をフォトリソグラフィから、CDの作製などに用いられている射出成型に変更することで、1検査あたり約2ドルという低価格を実現。さらにはテレセントリックレンズと1眼レフカメラを組み合わせて、大病院や大規模検査センターだけでなく市中のクリニックでも使える35×45×35cmという小型化と、すべて込みで約120万円という手頃な装置価格を実現した。
講演ではCRISPR-Cas12を用いたウイルスDNAの1分子定量法も紹介され、渡邉氏は講演の最後で、将来のパンデミックに備え、様々なウイルス検出に汎用的に使用できる感染症診断装置としての実用化を目指すと述べていた。
今回のシンポジウム参加者は、主催者発表によれば約200名、各方面から高い関心が寄せられた。我が国における新型コロナの感染状況を見てみると、ポストコロナ時代とは新型コロナウイルスがいなくなった時代ではなく、共存する時代と捉えた方が良いのかもしれない。弱毒化がより速く進み、人類にとって余り怖くないものになることを切に願う。
(川尻 多加志)






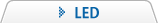





 レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。
レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。