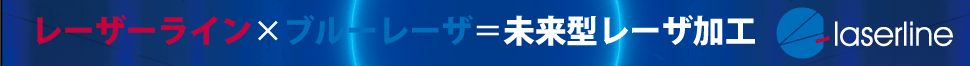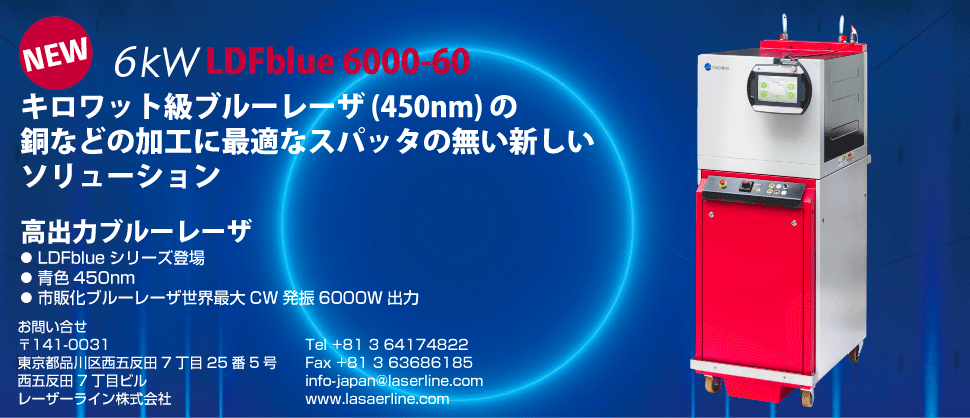国内リポート 詳細
新型コロナウイルス克服に挑戦する応用物理
応用物理学会、一般公開シンポジウムを開催
April, 1, 2021, 東京--3月16日(火)から19日(金)まで、オンラインで開かれた2021年第68回応用物理学会春季学術講演会の一般公開シンポジウム「新型コロナウイルス禍に学ぶ応用物理:未来社会に向けて」が3月17日(水)の午後から開催された(主催:応用物理学会(応物)、日本学術会議、未来社会と応用物理分科会)。
本シンポジウムは、同学会のウェブサイトに設けられた特別コラム「新型コロナウイルス禍に学ぶ応用物理」に掲載された35件のコラムから選出されたもので、今回は計9件の講演が行われた。
特別コラムは、新型コロナウイルス禍において応用物理の果たす役割の重要性を再確認するとともに、応用物理に関係する研究者や将来応用物理研究に携わる学生にとって新しい発見や気付きの一助になることを願って企画された。
会長の波多野睦子氏(東工大)は、同コラムの冒頭で「アイザック・ニュートンが英国ケンブリッジ大学トリニティカレッジの学生だった頃、ロンドンではペストが大流行し、大学は閉鎖されてしまったが、その間ニュートンは故郷のウールスソープで過ごし、万有引力の発見など、いくつもの大きな業績を上げた。この期間は「ニュートンの創造的休暇」と言われているが、新型コロナウイルス感染防止のため様々な自粛が求められる今、我々もこの時期を有効に過ごし、将来に繋げることが求められている」とし、さらに「新型コロナウイルスのサイズは100nm程度、このサイズは半導体デバイスや光の波長など、応用物理分野で良く取り扱うサイズであり、新型コロナウイルスの感染診断手法などに応用物理は多く用いられている。その性能・機能向上のために寄せられている応用物理への期待は大きい」と記している(筆者要約)。シンポジウムのプログラムを以下に示す。
◆はじめに:波多野睦子氏(東工大/応物会長)
◆呼吸器感染症を引き起こす新興ウイルスの検査診断:影山努氏(国立感染症研究所)
◆ウイルスの観察技術と治療法開発への応用:南保明日香氏(長崎大)
◆創薬を目指したSPring-8/SACLAの構造生物学研究:山本雅貴氏(理研)
◆PCR法による検査(原理):永井秀典氏(産総研)
◆AIによる医用画像診断支援:藤田広志氏(岐阜大)
◆COVID-19診断技術とバイオセンサー:民谷栄一氏(産総研/阪大)
◆ナノポアと機械学習を用いたウイルス検査:筒井真楠氏(阪大)
◆深紫外光の医療応用とウイルス不活化:青柳克信氏(立命館大)・黒瀬範子氏(精神・神経医療研究センター)
◆新しい生活様式を快適に過ごすためのモバイル技術:藤野弘行氏(NTTドコモ)
◆おわりに:伊藤公平氏(慶大)
今回のシンポジウムでは、検査・診断手法が数多く紹介されたが、本稿では人体に対する影響において、最近注目すべき知見が報告されている紫外光領域に関する青柳氏の講演「深紫外光の医療応用とウイルス不活化」を紹介する。
新型コロナウイルスの不活性化で注目される遠深紫外光
光の波長は短い方から紫外光、可視光、赤外光と大きく分けられるが、CIE(Commission Internationale de l’Eclairage:国際照明委員会)では、さらに315~400nmをUV-A、280~315nmをUV-B、100~280nmをUV-Cと分類している。
青柳氏は講演において、315~400nmを紫外光とし、それより短い深紫外光領域を、人体に対する影響の度合いから230~315nmの深紫外光と100~230nmの遠深紫外光に分類、それぞれの違いについて解説した。
紫外光は、日焼けや免疫機能の低下、皮膚のしみ、しわ、たるみの原因となり、深紫外光については、各種ウイルスを不活性化できるものの、皮膚がんや腫瘍、角膜炎、白内障の原因になるなど、大量に浴びると人体に何らかの害を及ぼす。それゆえ人のいない所にしか照射できない。これに対し、青柳氏は遠深紫外光が各種ウイルスを不活性化する一方で、人体に害が少ないという研究事例を紹介、人のいる所でも照射できる波長だと指摘した。
新型コロナウイルスは接触や飛沫、エアロゾルによって感染が広まっていく(WHOでは新型コロナウイルスの感染症の名称を「COVID-19」と命名しており、ICTV(International Committer on Taxonomy of Viruses:国際ウイルス分類委員会)では、ウイルスの名称を「SARS-CoV-2」と命名している)。感染の抑制には、マスクの着用や人と人との距離の確保、手洗いなどの消毒、換気などに加え、空気やエアロゾルに含まれるウイルスの不活性化も重要とされている。
新型コロナウイルスを不活性化するには、60~80℃の熱やアルコールによって可能だ。これらの方法は、ウイルスのRNAの外側にあるタンパク質でできたエンベロープやスパイクを破壊する。一方、深紫外光や遠深紫外光はRNAを直接攻撃する。人がウイルスに触れる前に、空気やエアロゾルに含まれるウイルスを効率よく不活性化できる。
深紫外光の光源としては、254nmの水銀ランプがよく知られている。しかし、深紫外光領域の波長は、前述のように人体への影響が大きいという欠点を持っている。さらに、ランプ中には水銀が含まれており、水俣条約による水銀フリーという潮流の中、高出力な水銀ランプは使用できないのが実情だ。
これに対し、遠深紫外光源は新型コロナウイルスを効率よく不活性化でき、人体への影響も少ないという特長を持っている。講演では、ネズミの皮膚に対しKrClエキシマランプの遠深紫外光(222nm)と水銀ランプの深紫外光(254nm)を照射して比較したところ、深紫外光では炎症を起こすが、遠深紫外光では炎症が起きなかったという実験結果が紹介された。
違いは、ウイルスや細菌、人体細胞の大きさによるという。ウイルスの大きさはおおよそ0.02~0.3μm、細菌は1~5μm、これに対し人体細胞は5~25μmと大きい。深紫外光や遠深紫外光をウイルスや細菌に照射すると、その小ささゆえ細胞核まで到達して損傷が起こる。人体細胞に対しては、深紫外光は吸収係数が小さいので細胞核まで到達してしまうが、遠深紫外光は吸収係数が大きく、かつ人体細胞は大きいので細胞質の所で止まって細胞核まで到達しないのだ。
光源については現状、KrClエキシマランプ(バンドパスフィルタ付き)が市販されており、よく使われている。一方、半導体デバイスとしてはAlGaN-LEDで222nm、AlN-LEDで210nm(LEDとしては最短波長)の発振などが報告されているが、出力の点で課題が残されている。
この他、講演では面発光タイプとして、BN電子線励起遠深紫外発光素子(225nm)や190、220、240nmの波長選択と大パネル化が可能なマイクロプラズマ励起深紫外発光素子(MgO-MIP:Micro Plasma Excited Deep Ultraviolet Light Emitting Device)などが紹介されたが、これら光源開発における応用物理研究への期待は大きい。
青柳氏が講演で示したように、遠深紫外光がスギ花粉アレルゲンを不活性化したり、紫外光によって網膜にEGR1遺伝子が活性化され眼軸長由来の近視が抑制されるなど、紫外光領域に関する研究では注目すべき成果が報告されている。その動向に注目して行きたい。
なお、冒頭で紹介した応物の特別コラム「新型コロナウイルス禍に学ぶ応用物理」に興味のある方は、下記URLをクリックしてご覧いただけたら幸いだ。
https://www.jsap.or.jp/columns-covid19
(川尻 多加志)






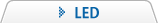





 レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。
レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。