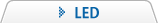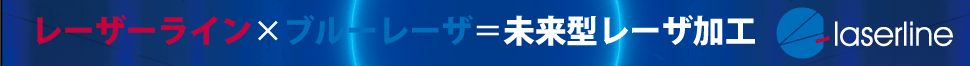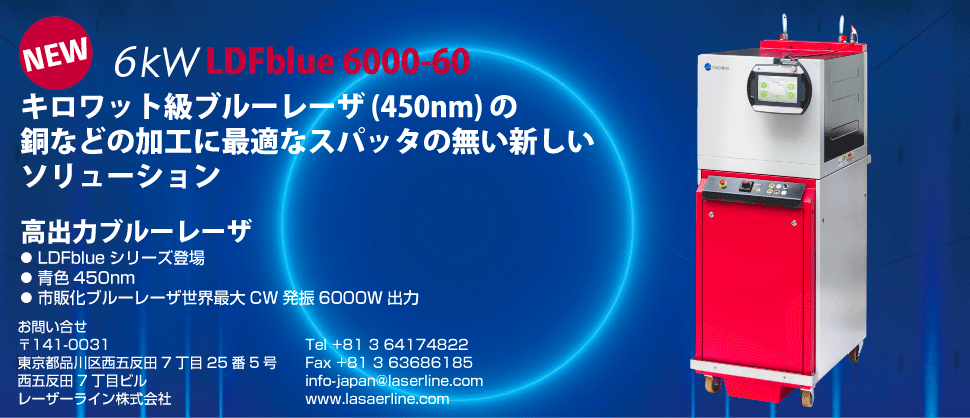国内リポート 詳細
AI時代のデータセンタを支える光技術
フォトニックデバイス・応用技術研究会が第34回のワークショップを開催

January, 13, 2026, 東京--
昨年の12月16日(火)、光産業技術振興協会フォトニックデバイス・応用技術研究会(代表幹事:上智大教授・下村和彦氏)が産業技術総合研究所臨海副都心センター別館(東京都江東区)で第34回のフォトニックデバイス・応用技術研究会 ワークショップを開催した。
今回のテーマは「AI時代のデータセンタを支える光デバイス・ネットワーク技術の最新動向」。以下に講演題目と演者を、次章では各講演の概要を紹介する。
◆開会の挨拶:研究会担当幹事
◆基調講演:AIによって変化する国内データセンター事情:三柳英樹氏(インプレス)
◆光スイッチによるデータセンタ/AIスーパーコンピュータネットワークの革新:佐藤健一氏(名古屋大名誉教授・産総研招聘研究員)
◆光電融合デバイスとその実装技術:佐藤昇男氏(NTT)
◆高密度シリコンフォトニクスCPOトランシーバとその集積化技術:加藤正樹氏(Marvell)
◆液浸冷却が可能なシリコンフォトニクス光トランシーバ:小林茂氏(アイオーコア)
◆AIデータセンタと標準化動向:磯野秀樹氏(IGSコンサルティング)
◆閉会の挨拶:下村和彦氏(研究会代表幹事)
AI時代のデータセンタと光技術
インプレスの三柳英樹氏は、国内データセンタ市場の現状とAI(特にGPU)普及がもたらすインフラ変化や課題、今後の展望を解説した。
国内データセンタ市場は、現在ハイパースケーラー(巨大IT企業)向けが主流になっており、ハイパースケール型のラック数は2023年末、リテール型のそれを上回った。その市場規模(ラック数ベース)は2031年には、2024年に比べて約1.7 倍に増えると予測されている。一方で資材の高騰や建設業における人材不足などが要因となり、一部プロジェクトで建設が遅れるという事態も発生している。
AIとGPUはインフラ構造にも変化をもたらす。AIの学習・推論用途ではGPUが必要不可欠だが、市場をほぼ独占しているのはNVIDIA製GPU。一方で、性能を向上させるため数多くのGPUを接続して一つの巨大なシステムとして扱う「クラスタ化」も進展しており、データセンタ側でも対応が迫られている。
国内データセンタはAIに対応するため、高熱を発生するGPUサーバ用に水冷化や、コストが安くて済むコンテナ型データセンタの建設によって乗り切ろうとの動きが目立っている。今後はAI専用に設計されたデータセンタから、より高密度・高消費電力なスパコン並みの設備を要する「AIファクトリー」への進化も予想されている。
GPUクラスタの大規模化に伴い、今後の最大の課題は消費電力となる。データセンタの立地も、安定した大量の電力を供給できる地域へとシフトする可能性が考えられる。総務省や経産省でも、電力と通信を連携させる「ワット・ビット連携」やデータセンタの地方分散を推進する。
三柳氏は、今後のデータセンタの進化は「AIの動向」が決定づけるとともに、特に電力使用量増加への対応が持続可能性の鍵を握ると述べる。さらに「ポスト生成AI」に向けた開発競争もあり、高性能GPUサーバの需要は引き続き続いていくだろうと指摘した。
名古屋大名誉教授の佐藤健一氏は、「光スイッチによるデータセンタ/AIスーパーコンピュータネットワークの革新」と題し講演を行った。
AIデータセンターネットワークはその規模を急速に拡大させている。近い将来には100万オーダのXPU(GPU/TPU/CPU等)を収容するギガワットクラスのデータセンタ構築も現実味を帯びてきた。この様な状況において、膨大な数のXPU同士を広帯域に結合するためのネットワークやインターコネクトの規模は、XPUの数に対して非線形に増える傾向にある。今後ネットワークの重要性はますます大きくなり、今やネットワークがデータセンタを定義するとまで言われている。
一方、半導体技術の進展は微細化の限界とともに飽和傾向が顕著になっている。XPUの性能の向上も2030年代の初めには大きな壁にぶつかるとの予測もある。この様な状況の中、光技術はその広帯域性やトランスペアレントなスイッチング(回線交換)特性、低消費電力性といった特長を活かして電子技術の一部を置換え、Front endネットワークやAIスケールアウトネットワークへの適用が始まった。
将来的に光スイッチ技術の適用領域はさらに拡大すると予想され、上記領域における適用範囲の拡大やメトロネットワーク(データセンタ間)と統合されたデータセンタ内の光ネットワーク、今後のCo-packaged Opticsの進展と相まってAIスケールアップネットワークへの適用も視野に入ってくる。
佐藤氏は、研究開発の進め方に関して留意すべき変化があると指摘する。GAFAMの株価時価総額は、日本最大の企業の実に56.5 倍(2025年11月現在)、NVIDIA、Broadcomを加えた場合には81.2倍にもなる。これらの企業は各々の領域でAI関連技術の開発を先導しており、要求条件を満たすための垂直統合による技術開発やMSAやオープンエコシステムズを中心とする開発をメインに据え、最新の技術進展の状況を学会で公表することは稀である。そこで佐藤氏は、研究者とそのコミュニティーは最先端技術の動向について、学会の枠を超えこれまで以上に広く探索することが重要だと指摘した。
NTTでは、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想のもと、光電融合デバイス(Photonics-Electronics Convergence Devices:PEC)の研究開発を進めている。佐藤昇男氏は、同社の光電融合デバイスとその実装技術について講演を行った。
講演では、IOWNおよびPECのロードマップが紹介され、2028年の製品化を目標にしたPEC-3世代に焦点を絞った解説が行われた。同社はPEC-3においてメンブレンInPデバイスの光IC技術の強みを生かし、電気IC・基板・光ファイバなどを実装したProof-of-Concept(PoC)として16チャネル光送信器と4チャネル光送受信器の二つのデバイス構造を設計・試作した。講演では、その構造を例にとりながら実装技術の観点から設計スキームとフローに基づいた解説が行われた。
佐藤氏は今回残された課題として、16チャネル光送信器においては信号の品質や熱設計、16チャンネルであるが故の負荷の大きさ、実験でサンプル数があまり採れなかった点などを挙げ、4チャネル光送受信器においてはデバイスの大きさ、実験でリフローまで示し切れなかった点、フルのLSI(CPU、GPU、FPGA等)と繋げていない点などを挙げていた。
「高密度シリコンフォトニクスCPOトランシーバとその集積化技術」を講演したのはMarvellの加藤正樹氏だ。
AIワークロードによるデータトラフィックの急増は、データセンタのインターコネクトに対し、これまでにない厳しい要求を突き付けている。一方で従来のプラガブル光トランシーバでは、次世代システムの帯域幅、消費電力、密度要件を満たすことは難しい。そこで、革新的なソリューションとして登場したのがCo-packaged Optics(CPO)だ。
CPOは、光エンジンをスイッチASICの非常に近くに配置する。これにより消費電力と信号損失を大幅に削減し、シグナルインテグリティを改善する。CPO実現の様々な技術の中でも、シリコンフォトニクス(SiPho)は拡張性、CMOS互換性、高い集積密度において際立った優位性を持っている。変調器、検出器、マルチプレクサといったフォトニックコンポーネントを単一チップ上に集積することができ、小型でコスト効率の高い光トランシーバを実現できる。さらに、高度なパッケージ技術と組み合わせることで、SiPhoベースのCPOアーキテクチャは、小型のフットプリント内で毎秒複数テラビットを超える高い総帯域幅を提供できる。
同社は、業界初となる高集積6.4Tbps 3Dシリコンフォトニクスエンジンを実現した。このエンジンには、次世代AIクラスタやクラウドデータセンタをマルチテラビット速度で接続するため32チャネルの200Gbps電気・光インターフェースが備えられている。導波路や変調器、受光器、変調器ドライバ、トランスインピーダンスアンプ(TIA)、マイクロコントローラの他、多数の受動部品など、数百ものコンポーネントを単一パッケージに集積することで、光インターコネクトの性能、帯域幅、エネルギー効率を劇的に向上させることができる。
具体的には100Gbps電気・光インターフェースを備えた同等のデバイスと比べ、2倍の帯域幅、2倍の入出力(I/O)帯域幅密度を実現、ビットあたり消費電力は30%削減した。これによってプラグインモジュールから将来のCPOに至るまで、様々な使用形態やフォームファクタに合わせ、最適化された広範な光インターコネクト製品を生み出す道を開くことができるという。
加藤氏は、高密度CPO向け3D SiPhoエンジン技術に加え、主要コンポーネントの特性とその集積化技術について解説した。
「液浸冷却が可能なシリコンフォトニクス光トランシーバ」について講演したのはアイオーコアの小林茂氏。データセンタでは消費電力量の増加が深刻化しており、2050年には世界全体で50万TWhを超えると予測されている。そのためプロセッサやネットワーク、冷却など、データセンタを構成する各要素において省電力化の取り組みが急務となっている。
プロセッサの冷却技術として注目されているのが、不活性液体中に基板ごと浸す液浸冷却で、その実用化も進んでいる。一方、データセンタ内での大容量・高速データ伝送には光ファイバを用いた光インターコネクションが有効とされ、Near Package Optics(NPO)やCPOなど、光トランシーバをプロセッサ近傍に高密度実装する技術の開発も活発化している。
プロセッサと同じ基板に搭載されるこれらの光製品は、液浸冷却においては不活性液に浸漬される。一方、現状の光結合にはレンズやプリズムなどの光学部品が用いられているが、これらは空気中での使用を前提としており、液浸環境下ではハーメチックシールなどの封止技術が必要になってしまう。さらに、光部品に関して構成材料やそれらを浸漬する冷媒の経時的変化など、明確な試験評価方法はまだ確立されていない。
同社では、シリコンフォトニクス技術を用いた量子ドットレーザと光ピンを集積した光トランシーバを開発した。105℃環境下で動作可能なチップを用いたもので、25Gb/sのエラーフリー動作を実現、CPU近傍に実装されるNPO用途にも適用できるという。また、冷却液の影響を受けない光路設計により、液浸冷却環境下においても 25.78125Gb/sのエラーフリー動作を達成した。
近年では、光部品の液浸冷却下での信頼性評価に関する業界標準化が進展、国際標準化への動きも加速している。小林氏は、技術開発成果とともに、データセンタ業界における液浸冷却技術の開発・普及・標準化を推進するOCP Immersion Sub-Projectや、液浸冷却環境においてオンボード光部品および光インターコネクトソリューションの性能を調査・評価するiNEMIでの標準化についても紹介した。
IGSコンサルティングの磯野秀樹氏は「AI データセンタと標準化動向」について講演した。
ICT市場で求められる情報量は、AI時代を迎え増加傾向が劇的に加速すると予測されている。AI向け光インタコネクションはデータセンタのBack end Fabric領域に導入され、 従来のデータセンタ領域の Front end Fabricと区別されている。Back end Fabricでは高速化(400G/lane)ととともに、小型化(高密度電気・光コネクタ)、低消費電力化、低遅延、低コストが要求される。対応するには従来とは異なる光インタコネクションの開発が必須だ。市場では新たなビジネス領域として期待が集まっており、学会・展示会等でも広く取り挙げられているのが現状だ。
Back end Fabricは、Rack内のAIサーバ間を接続するScale up領域と、Rack 間を接続するScale out領域に分類される。Scale upは伝送距離が10m前後以内で従来は電気で接続されていたが、光インタコネクションの導入も検討されている。Scale outは伝送距離が最大300m前後の光インタコネクションが検討されているが、AIデータセンタの規模により変わることが考えられるという。
光インタコネクションに関する標準化はここ数年、活発に審議されている。磯野氏はIEEE802.3やOIF を始め、多くのMSA(LPO-MSA、PCIe、UALinkなど)で進められている審議のトピックスを紹介した。IEEE802.3 では2025年7月に200G/laneのMMF方式がスタート、2026年3月には400G/laneの新規プロジェクトが開始される見通しだ。一方OIFではEEI(Energy Efficient Interface)プロジェクト傘下で、CPO/ELSFP、RTLR、COI、High Density Connector など多くのトピックスが取り扱われている。
近年ではAIデータセンタ・インタコネクションで、伝送速度400G/laneの重要性に関するコンセンサスが得られつつあるという。優先順位としてはScale up、Scale outの順だが、400G/laneではPCBの配線損失が大きくなるため、CPO構成とCPC(Co-Packaged Copper)を用いたFlyoverのプラガブル方式の二つが大きくクローズアップされている。
磯野氏は、課題の多くはまだ解決されていないため継続して市場で議論が続くと指摘、今後の動向を注視していく必要があると述べた。
第5回研究会の開催
第5回の研究会は2026年2月25日(水)、上智大学・四谷キャンパスで開催される予定だ。テーマは「(仮)フォトニックデバイスの最新世界動向と日本の立ち位置」。IOWNの最新トピックス、モビリティフォトニクスなどが取り上げられる。詳しくは研究会のURL(下記)をご参照願いたい。
https://www.oitda.or.jp/study/pd/
(川尻 多加志)