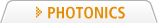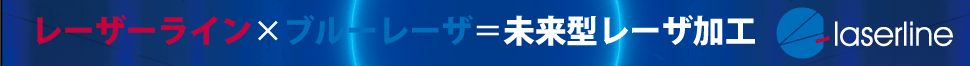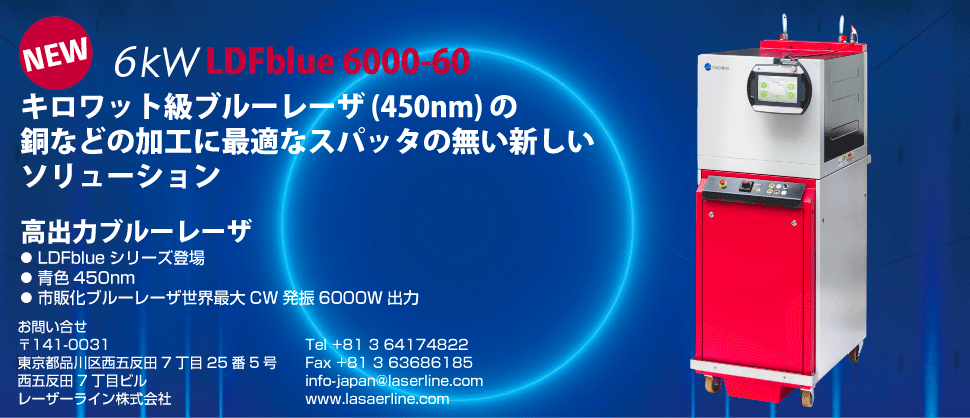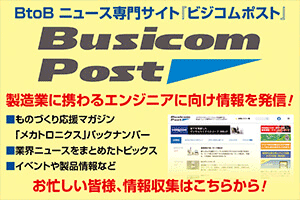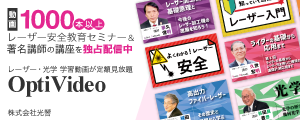国内リポート 詳細
ナショナルプロジェクト「次世代半導体微細加工プロセス技術」
マイクロ固体フォトニクス研究会/第5回レーザー学会「小型集積レーザー(Ⅱ)」専門委員会が開催される
August, 1, 2025, 東京--
マイクロ固体フォトニクス研究会/第5回レーザー学会「小型集積レーザー(Ⅱ)」専門委員会が7月2日(水)、自然科学研究機構・分子科学研究所(愛知県岡崎市)とオンラインのハイブリッド形式で開催された。主題は「先端レーザーと半導体プロセス」だ。
当日の講演題目と講師名を以下に記すとともに、次章以降では溝口計氏(九州大学)による講演「半導体製造用EUV光源開発とその応用の現状」の中で紹介されたナショナルプロジェクト「次世代半導体微細加工プロセス技術」の概要を紹介する。我が国半導体産業の復活をかけた注目のプロジェクトだ。
◆座長挨拶:平等拓範氏(理研/分子研)
◆講演「半導体素子製造におけるレーザープロセシングの現状と未来」:池上浩氏(高知工科大)
◆講演「半導体製造用EUV光源開発とその応用の現状」:溝口計氏(九大)
◆企業紹介「ハイティラ株式会社活動紹介」:平野嘉仁氏(ハイティラ)
◆講演「小型集積レーザーに関する特許説明」:平等拓範氏(理研/分子研)
◆社会連携研究部門平等研究室見学
K Program
世界の主要国は、国家や国民の安全保障上の様生な脅威等に対する有効な対策として、鍵となる技術の把握や情報収集・分析、技術流出問題への適切な対処、人工知能、量子技術といった先端技術の研究開発と活用を強力に推進している。
我が国の安全保障をめぐる環境が一層厳しさを増し、科学技術・イノベーションが国家間の覇権争いの中核となっている今、日本の技術的優位性を高め不可欠性の確保につなげていくには、研究基盤を強化することはもちろん、市場経済のメカニズムのみに委ねるのではなく、国が強力に重要技術の研究開発を進め育成していく必要がある。
日本政府はこれまで、重要技術育成を含めた経済安全保障に係る施策を総合的・包括的に進めるため、新たに経済安全保障担当大臣を置き、経済安全保障推進会議を開催するとともに、経済政策を一体的に講ずることで安全保障確保を推進する「経済安全保障推進法」を成立させてきた。
K Program(経済安全保障重要技術育成プログラム)は、我が国が中長期的に国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な先端的重要技術について、研究開発から実証・実用化までを迅速かつ機動的に推進するために創設されたものだ。
この中でも、我が国の経済安全保障を確保・強化する観点から、先端的な重要技術については国(内閣府、文部科学省、経済産業省)が「特定重要技術」として研究開発ビジョンを提示する。
研究開発ビジョンは「第1次」と「第2次」の2つに分類され、さらに重要技術の獲得を目指す比較的大規模な研究開発プロジェクトである「プロジェクト型」と、研究開発プロジェクトの高度化を図り得る、あるいは単独で重要技術となり得る要素技術等に関する研究開発の「個別研究型」に分かれている(個別研究型には、技術の特性等に応じて比較的中小規模のプロジェクト的な推進を図る研究開発も含まれ得る)。公募は受付け中のものを含め、今後も新たなテーマを設定して行われる計画だ。
次世代半導体微細加工プロセス技術
「次世代半導体微細加工プロセス技術」は、第2次研究開発ビジョンの中のプロジェクト型に属する。
半導体は、5G・ビッグデータ・AI・IoT・DX等のデジタル社会を支える重要基盤であり、「経済安全保障推進法」に基づく特定重要物資にも指定されている。
一方で、日本の半導体産業の地位は1990年代以降、徐々に低下していった。それ故、今こそ国内の半導体製造基盤を確保・強化していくことが戦略的に重要になっている。とりわけ、デジタル技術の利用が拡大する中、電子機器のさらなる高性能化に必要不可欠な半導体微細加工プロセス技術を強化していくことは喫緊の課題だ。
プロジェクトでは、現在半導体関連企業が共通して認識している技術課題の延長線上にはないような最先端のEUV露光技術を超える全く新しい技術や、半導体製造以外の用途の可能性を開拓することも視野に、革新的なレーザ技術・ミラー作成技術の開発およびその周辺技術の高度化を図り、よりエネルギー効率が高く省エネ・省スペースを実現する技術を獲得することを目指す。実用化に向けた要素技術の検討などの企業導入に向けた方策の検討も進める計画だ。予算総額は最大135億円程度とされ、以下に示す4つのテーマのもと開発を進める。
(1)EUV露光励起用レーザの開発:EUV光を発生させるレーザ(ドライブレーザ)の開発、特にレーザ発振器や前置増幅器、増幅器、エネルギー伝搬計測・制御技術などを開発する。
(2)EUV露光に用いるミラー開発:EUV用の大型ミラーの作製に必要な超微細研磨技術、膜技術、超精密ミラーの特性計測技術などを開発する。
(3)半導体チップを実装する工程での次世代微細加工プロセスの開発:様々な種類のチップに柔軟に対応可能となるよう、マルチスケールの微細加工に関するデータベースの整備、高速条件出しのためのAI技術開発等を行う。
(4)最先端露光技術のさらに先を見据えたBeyond EUVの実現も念頭に入れた革新的基盤技術の開発:EUV露光用の新規高性能光源の開発に向けた要素技術の開発(低消費電力で高出力を実現できる技術開発等)や、既存のEUV露光技術のさらにその先を指向した光源、光学系、材料系、計測技術等の要素技術開発(フィージビリティスタディ)を行う。
プログラム・ディレクター(PD)を務めるのは、東大名誉教授/特命教授の湯本潤司氏だ。これまで公募枠として採用されたテーマは3つ、この内の公募枠(3)は、さらに4つのテーマに分かれて研究開発が進められる。その概要は以下の通りだ。
【公募枠(1) 拠点研究開発】
研究開発課題名:次世代半導体微細加工の基盤技術研究開発
研究代表者/研究代表機関:緑川克美氏/理研
我が国においてEUV露光に関連する最先端の技術を有する機関と人材を結集し、次世代半導体技術のさらなる発展に不可欠とされる革新的基盤技術の研究開発を推進する。将来のEUV光源に必要な高出力で高効率な新しいレーザ光源と大口径で高精度なミラーの加工と成膜技術、さらに後工程に必要とされるレーザ微細加工において、これまでの技術を大きく凌駕し将来のキーテクノロジーとなり得る革新的技術の確立を目的とする。
【公募枠(2) EUV露光用次世代革新光源の開発】
研究開発課題名:革新的な次世代EUV露光用光源の実現を目指した自由電子レーザーの基盤技術開発
研究代表者/研究代表機関:本田洋介氏/高エネルギー研
加速器技術を利用して、現在の半導体関連企業が有する光源技術の延長線上にない新しい光源技術を開発し社会実装を目指す。超伝導加速空洞を用いたERL(エネルギー回収型線形加速器)にFEL(自由電子レーザ)発振技術を組み合わせることで、高効率で高出力のEUV光源(ERL型EUV-FEL)を開発する。
【公募枠(3) 光源、光学系、材料系、計測技術等の要素技術開発(フィージビリティスタディ)】
研究開発課題名:量子エリプソメータを用いたイオンスパッタ法によるBEUV反射多層膜鏡の開発
研究代表者/研究代表機関:江島丈雄氏/東北大
次世代半導体露光用の動作波長6.XnmのBEUV(Beyond Extreme Ultra-Violet)光学系には、反射多層膜を利用した反射光学系が使用される。研究開発では、イオンスパッタ法により膜品質の向上と、膜厚制御のための量子エリプソメータの導入でBEUV反射多層膜を開発するとともに、この反射多層膜を用いてBEUV結像光学系を開発し、BEUV像の取得を試みることでBEUV露光機の光学技術獲得を目指す。
研究開発課題名:連鎖反応不要な高感度・高解像度反応系設計による高性能極端紫外光レジストの開発
研究代表者/研究代表機関:古澤孝弘氏/阪大
金属・ハロゲン等の高吸収元素を活用し、かつ連鎖反応が不要なレジスト材料の開発を行う。放射線用レジストでは光子の選択的吸収を活用できず、反応系で光子のエネルギー利用の選択性を出す必要がある。そのため単に高吸収元素を添加するだけでは、高性能化は達成できない。放射線化学反応に基づき、レジスト反応系(プラットフォーム)を設計し、Beyond EUVにおいても適用可能な高感度・高解像度レジストを開発する。
研究開発課題名:波長170nm台コヒーレント光発生用非線形光学素子及びその応用の開発
研究代表者/研究代表機関:宮本晃男氏/オキサイド
次世代の半導体露光技術においては、露光マスクのパターンやウエーハ検査の高精度化が必須で、その実現には、検査用レーザ光源の波長を現在の最先端である200nm前後から170nm台へ大幅に短波長化することが必要。研究開発では、真空紫外光を発生可能な非線形光学結晶の材料選定から結晶育成、デバイス化、レーザ光源の試作まで一貫した技術開発を行い、波長170nm台レーザ光源の要素技術確立する。
研究開発課題名:波長3μm~4μm帯高出力中赤外レーザーによる高効率EUV光源基盤技術の実証
研究代表者/研究代表機関:安原亮氏/核融合研
EUV光発生に必要なレーザパワー密度1010W/cm2以上を可能とする3μmおよび4μmのEUV光発生用固体レーザの開発を行い、計算結果の妥当性の検証と、照射レーザ波長を最適化したEUV光変換効率の最大化を目指す。世界に先駆けたEUV光源用照射レーザの中赤外波長選択肢の多様化とEUV光発生効率のデザイン精度向上は、20年先を見据えた我が国の産業競争力強化のための重要な礎となる。
以上、ナショナルプロジェクト「次世代半導体微細加工プロセス技術」の研究開発の概要を紹介した。プロジェクトが、我が国の半導体産業復活に貢献することを大いに期待したい。
今後の予定
次回以降の研究会は、第6回が9月3日(水)、第7回が12月17日(水)、第8回が2026年の2月18日(水)、それぞれ分子研とオンラインのハイブリッド形式で開催される。国際会議は10月19日(日)から23日(木)の5日間、「Optica Laser Congress」がPrague Congress Center(Prague、Czech Republic)で開催される予定だ。詳しくは下記URLを参照。
イベント情報 | TILAコンソーシアム
(川尻 多加志)