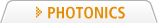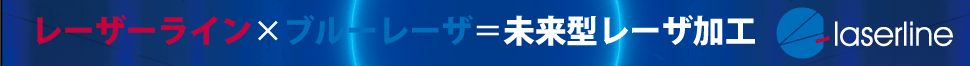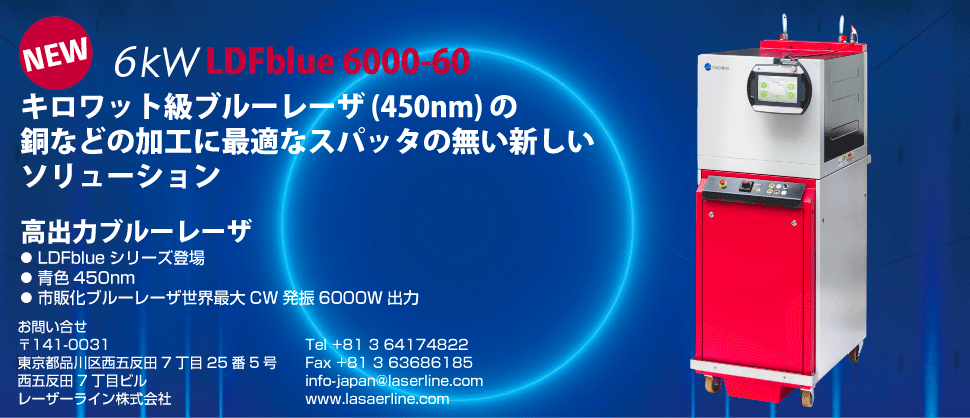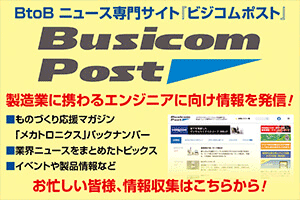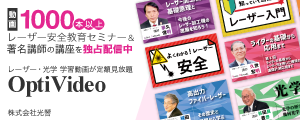国内リポート 詳細
AIと光技術の融合を探る
第175回記念微小光学研究会が開催される
June, 12, 2025, 東京--
急速に発展する人工知能(AI)において、微小光学を初めとする光技術はいかに貢献できるのか。AIの核心を学ぶとともに、光を用いた計算技術からAIを物理的に支えるデータセンターにおける光配線技術までを含めて議論する応用物理学会・微小光学研究会の第175回記念研究会「AIと光」が6月2日(月)、東京科学大・デジタル多目的ホール(東京都目黒区)とオンラインで開催され、合計158名(講師を含む)が参加をした。
当日のプログラム
メモリによる情報記憶が可能な電子技術に対し、それが困難な光技術は情報処理ではなく情報伝達に適していると言われてきた。しかしながら膨大な計算量が必要なAIにおいては、光技術の新たな役割が期待されている。
今回の研究会では、前半でそもそものAIの核心を俯瞰するとともに、光コンピューティングのシステム構成とそれを実現するための光回路についての発表が行われ、後半では光技術の分野融合について展望した後に、イメージングやセンシングへの展開、さらにAIを物理的に支えるデータセンターにおける光技術に関する発表が行われた(微小光学研究会機関誌「MICROOPTICS NEWS」Vol.43 No.2「はじめ」より抜粋)。
当日は実行委員長の横森清氏の「開会のあいさつ」でスタート、基調講演2本を含めた合計7本の最新の研究が発表され、最後は運営委員長・中島啓幾氏による「閉会のあいさつ」で研究会の幕を閉じた。
当日のプログラムを下記に記すとともに、次章以降では豊田工大の中野義昭氏が基調講演2で発表したCRESTの新たなプロジェクト「光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア」の概要を紹介する。
◆開会の挨拶:実行委員長・横森清氏
◆[基調講演1] AIの歴史、現在、未来 – 新しい文明社会:甘利俊一氏(帝京大)
◆光コンピューティングシステムアーキテクチャの展望:川上哲志氏(九大)
◆シリコンフォトニクスを用いた光行列計算アクセラレータ:北翔太氏(NTT)
◆[基調講演2] 光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア:中野義昭氏(豊田工大)
◆コンピュテーショナルイメージングと光コンピューティング:堀﨑遼一氏(東大)
◆光ニューロモルフィック計算とセンシング技術への展開:砂田哲氏(金沢大)
◆光エンジン向け高出力外部光源:藤原直樹氏(住友電工)
◆閉会の挨拶:運営委員長・中島啓幾氏
光融合技術
文部科学省は毎年、組織・分野の枠を超えた基礎研究を戦略的に推進するため、根本原理の追求と政策的な意思を結びつける戦略目標と研究開発目標を定めている。2024年度、同省は新たに6つの戦略目標と研究開発目標を掲げた。そのうちの1つが「社会課題解決に資する挑戦的な技術開拓:持続可能な社会を支える光と情報・材料等の融合技術フロンティア開拓」だ。これに呼応して科学技術振興機構(JST)はCRESTの新たな研究領域として「光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア(略称:光融合)」を立ち上げた。研究総括は豊田工大の中野義昭氏が努める。
戦略の目標は、持続可能な社会を支える将来のグリーン情報システムの基盤技術の確立へ向け、光科学と情報・材料等の異分野の科学との融合と、基礎研究から利用技術開拓までの階層間の融合を通して、革新的な技術創出と期待拡大の好循環の実現を目指すというものだ。具体的には、以下の達成を目指するとしている。
(1)光の真価を発揮する原理・要素技術の創出
将来のグリーン情報システムでの活用を見据えて、光の潜在能力を最大限引き出せる究極的な光電変換・制御等の要素技術を新たな理論・材料等を導入して創出する。また、光の基礎原理・新現象等を物性や量子性に踏み込んで追究する。
なお、その項目には、光デバイスのスケーラビリティ・制御性・効率等を極限まで高めるための原理・要素技術の創出が含まれる。
(2)光と異分野のハイブリッド技術の開発
光科学と情報等の異分野の科学との融合により、電子技術のみでは突破できなかった情報システムの性能や機能に係る、従来の限界を超える光×電子・量子等のハイブリッド技術を開発する。
その実現には、物性物理・材料科学等に基づく光デバイスに係る研究と情報科学に基づく数理モデル・アーキテクチャ・ソフトウェア等に係る研究の相補的な協調・融合が欠かせない。
このような異分野科学の融合により光と電子・量子等の、これまでは個別に扱われていた物理系を統一的に扱える設計理論・実装方法等を創出し、それらを適材適所で活用することで従来の限界を超えられる革新的な知識・技術の基盤体系を構築していく。
なお、その項目には、光と他の方式の計算資源の協調により従来計算機の効率・速度を圧倒する技術、光と電子の自在な相互変換により有線と無線の光通信をシームレスにつなぐ技術、これまで未利用の光の性質・波長帯等の活用を可能とする新たなデバイスとアルゴリズムが融合したセンシング等の技術開発が含まれる。
(3)持続可能な社会へ向けた光の革新的利用技術の開拓
将来のグリーン情報システムおいて重要となるコンピュータ・通信・IoT デバイス等の要素間の連携やサイバー空間と実世界の連携を強化するため、光の革新的な利用技術を開拓する。さらに、環境・食料・医療・製造等の様々な分野に関する社会課題を光を駆使した情報システムで解決するコンセプトを提示する。
なお、前者には、クラウド側とエッジ側のコンピューティングやセンシングおよびそれらをつなぐネットワークが融合した大きな情報システムにおいて、光を適材適所に活用して情報システム全体を効率化する技術の開拓が含まれる。後者には、本融合技術に基づく大小の情報システムと様々な社会課題に係る研究の融合による課題解決策の提示が含まれる。
2024年度の選定課題
2024年度には以下に記す5つの課題が選ばれ、活動がスタートした。それぞれの研究テーマと研究代表者名、研究概要を紹介する。
◆メタマテリアル技術を活用した医療用ARグラスの実現(研究代表者:東京科学大・雨宮智宏氏)
ウェイブガイド方式のARグラスで使用されている回折格子をメタマテリアル構造に置き換えることでFOV(Field Of View)を初めとした各種の性能を向上させ、医療用に特化したARグラスを開発する。分野の異なる4つのグループが互いに連携して素材開発から光学設計、製造技術の確立、アプリケーションソフトウェアを含めた実装、臨床現場での検証に至るまで、一気通貫の研究開発を展開する。
◆光インセンサーコンピューティングの革新的技術の創成(研究代表者:埼玉大・内田淳史氏)
光センサと光プロセッサを融合して抜本的な設計・開発を行う光インセンサーコンピューティングの革新的技術を創成する。光センサで取得した大容量データから、光の状態のまま高速に特徴抽出を行うための光リザーバ技術を開発する。さらには、光センサと光プロセッサを一体化して全体機能を最大化するための高速・低遅延システムを設計・開発、高速・高度視覚センシング技術を実現する。
◆多種演算子を活用する光ストリーミングプロセッサ(研究代表者:産総研・Cong Guanwei氏)
脳に啓発された多次元の高度な演算子(微分、積分、写像式演算、低精度推論)を光集積回路で実現して、光ニューラルネットワークに融合する光SPUを提案する。この光SPUは光伝搬だけで瞬時にAI処理が完了しエネルギー効率に優れた光ストリーミング演算が可能であり、チップレットとしてネットワーク化することで大規模AIモデル構築への汎用性と拡張性が両立できる新たなアナログプロセッサを提供する。
◆「集積光コム×異種材料集積」による超多次元光テンソルコア(慶應大・田邉孝純氏)
AI演算で必要となる大規模な行列内積計算を、高速かつ省エネルギーで実行するための光テンソルコアを開発する。行列計算では、要素ごとに積算や和算の演算を行うため信号の干渉を防ぐことが不可欠だが、集積光コムと異種材料集積技術を用いて「波長×時間×空間」の多重化を実現して、より大規模な行列演算を可能にする基盤技術を研究開発する。
◆高速スピンデバイスに向けたテラヘルツ光電インターフェースの創出(京大・廣理英基氏)
次世代通信情報技術発展のためにテラヘルツ波とスピンの2つの情報を結ぶ新しい光電インターフェースの開発が求められている。研究では、世界最高強度のテラヘルツ光源を活用した磁気分光技術や独自に開発した金属メタマテリアル共振器構造を利用して、磁性体中のマグノンやスピン流を生成・制御する技術を創出する。実験・理論の研究者間の融合によってテラヘルツスピントロニクスの新たな基盤技術を確立する。
以上が2024年度・第1期の研究課題の概要だが、課題公募はすでに2025年度分も実施されており、今後選定作業に入る予定だ。なお、プロジェクトではそれ以降も課題公募を行っていくとしている。
研究会の今後の予定
9月3日(水)には第176回の微小光学研究会が工学院大の新宿キャンパス(東京都新宿区)で開催される。テーマは高密度実装・パッケージング(仮)だ。
10月12日(日)から15日(水)にかけては、第30回微小光学国際会議(MOC2025)が栃木県宇都宮市の宇都宮ライトキューブにて開催される。ポストデッドライン論文の締め切りは9月の上旬、早期割引参加登録の締め切りは9月11日(木)となっている。詳しくは下記URLを参照。
https://moc2025.com/
(川尻 多加志)