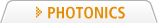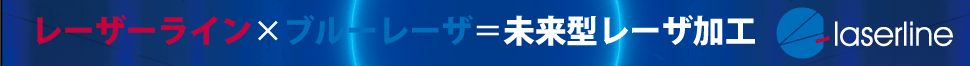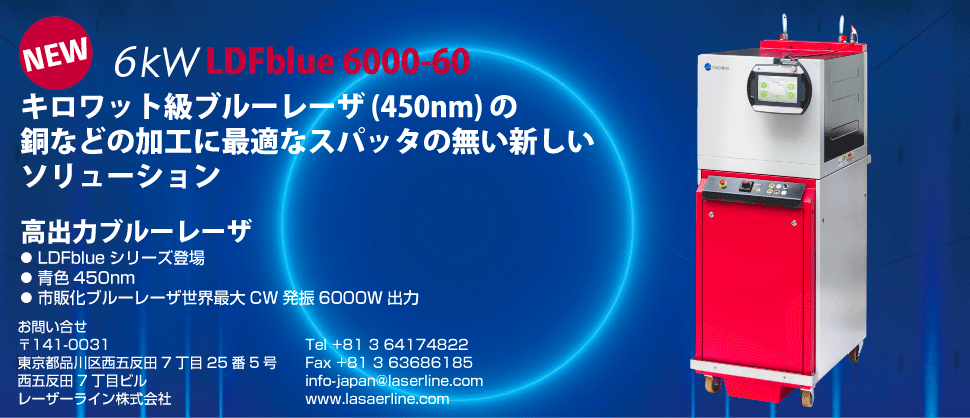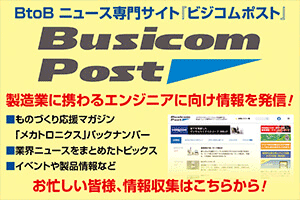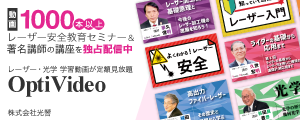国内リポート 詳細
HODIC、学生シンポジウム2025を開催
優秀発表賞は4本の研究発表に授与
April, 7, 2025, 東京--
ホログラフィは1948年、Gaborにより発明され、現在存在する唯一完全な3次元像表示方法だと言われている。その応用範囲は3次元表示の他にも計測や光学素子など、今日の光学の発展に伴い拡大し続けている。
そんな中、日本光学会のHODIC(ホログラフィック・ディスプレイ研究会、会長:徳島大学教授・山本健詞氏)が3月6日(木)に「学生シンポジウム2025」をオンライン開催した。
同研究会は、ホログラフィの応用範囲の中でも、特に人間を対象とした表示応用やその他の3次元表示法について最新情報を交換する場として設立された。近年の技術的進歩に伴って拡がる広範囲な分野をカバーするため、これまで研究会や講演会、学生シンポジウムの開催に加え、会誌「HODIC Circular」の発行や見学会・展示会などの開催など、ホログラフィおよび3次元画像の啓蒙活動を積極的に行ってきた。
研究会には、国内外のホログラフィ研究の専門家はもとより、ホログラムを実務に利用したりホログラム販売に携わっている人、さらにはホログラフィ・アーティストまで、幅広い分野の人々が参加しているという。
同研究会の学生シンポジウムは、未完成であったり研究中のものでも発表できるというユニークなもので、今回のスコープはホログラフィ(ホログラム作製技術、CGH、HOE、芸術等)、3D 映像(3Dディスプレイ、XR、3Dコンテンツ作成、評価等)、その他の関連技術(視覚特性、インタラクション、臨場感映像等)。発表は全部で18本、そのすべては紹介できないので、後になって発表された4本の優秀発表賞授与研究の概要を紹介する。
★様々な電子ホログラフィ表示装置に対応するための物体光変換手法の提案:梅内飛翔氏、柏木暁史氏、坂本雄児氏(北海道大学)
電子ホログラフィ表示装置には多くの種類があるが、それぞれの種類で物体光の計算手法が異なり、そのための専用プログラムを用いる必要がある。梅内氏等は、光波伝搬計算やレンズの位相変換計算で物体光を逆算的に変換して、様々な電子ホログラフィ表示装置に対応する計算手法を提案。光学実験によって、その有効性を確認した。
提案した手法は、光学系の特徴的なパラメータと得たい物体光を入力することで、それらを基に光学系に対応したホログラムを生成するというもの。梅内氏は今後の展望として、この手法を実際の視野・視域拡大のためのホログラフィ再生装置へ応用することやリアルタイム化などを挙げていた。
★計算量の次元を圧縮したホログラフィ専用計算機HORN-Xに関する研究:菅野朋輝氏、岡本規伴氏、聖德壯登氏、下馬場朋禄氏、伊藤智義氏(千葉大学)
菅野氏らの研究チームでは、CGH(計算機合成ホログラム)を高速計算するため、ハードウェアレベルでアルゴリズム設計を行うホログラフィ専用計算機「HORN(Holographic ReconstractioN)」の開発を行ってきた。これは、CPU や GPUに比べ専用設計によるパイプライン計算で計算時間を削減するというもの。研究チームでは、漸化式法のアルゴリズムを取り入れることで、CGH計算に必要な加減乗算を加算のみに置き換え、大幅なリソースを削減、回路の並列数を増加させてきた。
具体的には今回、CGH計算のX成分とY成分を分離して計算する手法である分離畳み込み計算を用いたハードウェア設計を行い、計算量の次元数を削減、HORNの10代目となる「HORN-X」を開発した。
本来の位相計算は、すべての画素で減算1回、乗算2回を計算しなければならないが、漸化式法では初めの画素以外を2回の加算だけで済ませることができ、大幅なリソース削減が実現できる。実験では、CPUとGPUの計算時間がそれぞれ2.26 秒、0.75秒であるのに対し、HORN-Xの見積もりでは0.035秒と、それぞれ65倍、21倍の高速化を達成した。
★全方向視差高解像度CGHにおける鏡面性表面へのバンプマッピング:岡田一隼氏、西寛仁氏、松島恭治氏(関西大学)
コンピュータホログラフィの技術発展は著しい。解像度が3000億ピクセルを超える大型の全方向視差高解像度計算機合成ホログラム(Full-parallax high definition computer-generated hologram : FPHD-CGH)も作製できるようになった。
岡田氏等は、ポリゴン法物体光波計算における鏡面性曲面のレンダリング法を応用し、FPHD-CGHで鏡面性表面へバンプマッピングする手法を提案。この手法を用いて計算したFPHD-CGHの光学再生像を示すとともに、CG画像との比較した実験結果を報告した。
具体的には、提案した手法を用いて計算した物体光波から約340億画素のFPHD-CGHを作製、光学再生を行うとともに、サイコロの3Dモデルと高さをマップして、さらに深さ4mmの賽の目をバンプマッピングした。光学再生像と比較用CG画像を比べたところ、モデルは鏡面性の立方体だが表面に窪みがあるかのような陰影が現れることを確認、視点を移動すると陰影も変化するバンプも確認できた。正面視点ではCG画像とも概ね一致したという。この結果を受け、岡田氏は提案した手法の有効性が確認できたと述べた。
★イメージセンサに対して6倍速撮影を可能にする空間多重インコヒーレントディジタルホログラフィ:植山恭帆氏、角江崇氏、下馬場朋禄氏、伊藤智義氏(千葉大学)
植山氏等の研究チームは、これまでにインコヒーレントホログラムの空間多重記録を活用して、イメージセンサの2倍速い動画撮影手法を提案してきた。さらなる高速化には、空間多重記録を行う際に限られた撮影面上に現れる干渉縞領域のシフトをより正確に制御する必要があるが、研究チームは今回、近軸光線追跡の原理を応用してシフト量を定式化、空間多重数を6倍とすることに成功した。
具体的には、複数の位相パターンをイメージセンサの撮影速度より高速に切り替え、1 枚の撮影画像内の複数箇所にホログラムを空間分割して記録する空間多重記録を実現。さらにRaspberry Pi 5(Raspberry Pi財団が開発・提供する手のひらサイズのワンボードマイコン)を使用して、イメージセンサの撮影周期と位相パターンの描画周期の同期制御を行い、この結果、動画撮影をした際に撮影される1コマに複数の干渉縞を空間多重記録することに成功した。
イメージセンサの撮影速度の場合、フレーム間の撮影対象の動きは0.55 mmだが、時間超解像撮影によってその間の動きを6倍の速度で精細撮影できることを実証した。
以上、今年のHODIC学生シンポジウムの優秀発表賞4本の概要を紹介した。同研究会では学生シンポジウムの他、年4回の研究会も開催している。5月下旬~6月中旬には2025年の第2回の研究会が開催される予定だ。詳しくは下記URLを参照されたい。
https://www.hodic-osj.org/
(川尻 多加志)