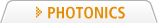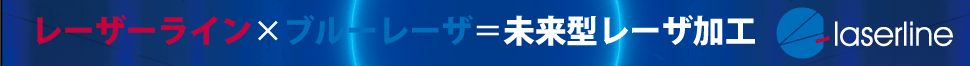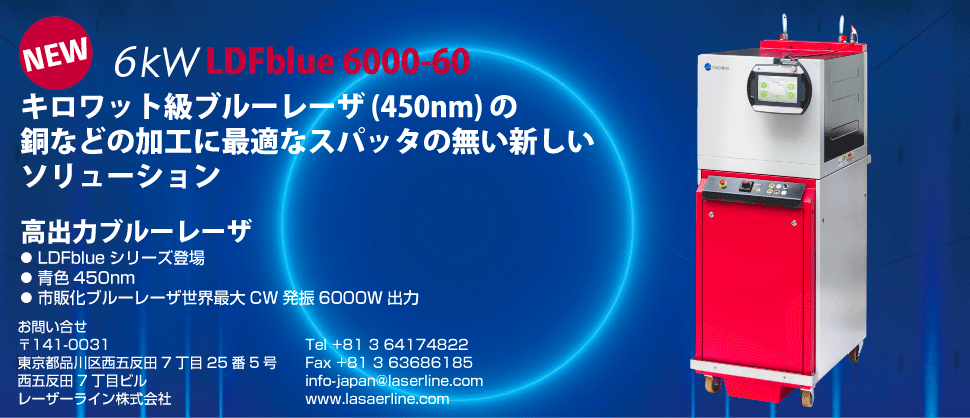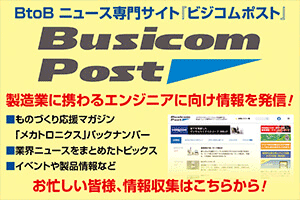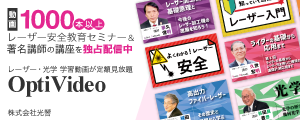国内リポート 詳細
量子情報通信技術の未来
IEICEがICT PIONEERS WEBINARシリーズ第60弾を開催
March, 13, 2025, 東京--
2月21日(金)、IEICE(電子情報通信学会)ICT PIONEERS WEBINARシリーズの第60弾「量子情報通信の現在と未来」がオンライン開催された。講師は慶応義塾大学の武岡正裕氏だ。
武岡氏は2001年、慶応義塾大学電気工学専攻博士課程終了後、情報通信研究機構(NICT)のポスドク、研究員、主任研究員を経て、総務省技術政策課研究推進室課長補佐を務めた。その後、Raytheon BBN Technologiesで客員科学者として研究に従事、2016年にはNICTに戻り量子ICT先端開発センター長を務め、現在は慶応義塾大学理工学部電気情報工学科教授に就任している。NICT未来ICT研究所統括、慶應義塾大学量子コンピューティングセンター研究員、ルイジアナ州立大学ハーン理論物理学研究所アソシエイトメンバー、デンマーク工科大学物理学科の客員教授も兼任している。
その研究は量子情報通信、量子暗号、光情報処理の研究から始まり、ICT研究開発政策の立案、量子情報理論の研究、量子暗号の実用化に向けた研究開発・標準化活動など多岐に渡る。
現在確立している情報通信技術は「古典物理学」に基づいた理論をベースに構築されている。これに対し、量子力学の世界では古典物理学では想像もできないような様々な事象や性質が生じる。この量子力学が持つ特有の性質を情報処理やネットワークに適用して、新しい付加価値を生み出そうという取り組みが活発化している。盗聴や改ざんが不可能な量子暗号通信や飛躍的な演算速度を有する量子コンピュータなどの研究だ。
量子情報技術の現状
量子情報技術は、問題を超高速で計算できる量子コンピュータ、これまでの測定感度限界を超える量子センシング、あらゆる計算機で解読不可能な量子暗号を含む量子情報通信の3つの柱からなるとされている。
量子情報の概念や基礎理論は1960年代から研究がスタートし、約半世紀の基礎研究期間を経て、近年の周辺技術の進展により、今では学術界・産業界が一体となった研究開発が急速に進展している。その一方で、歴史のある情報通信分野から比べれば、実用化の観点でも学問的にもまだ未成熟な青年期にあると言えよう。特に、上記に示した量子情報技術の3つの柱(計算・計測・通信)が将来的に融合されることは必然と考えられるものの、その進むべき道については様々な試行錯誤を続けている段階にある。
講演では、量子情報技術と量子情報通信の全般的な解説から始まり、量子暗号の仕組みや量子鍵配送(QKD)ネットワークの実用化・市場化に向けた取り組み、量子情報通信の未来の姿といわれる量子ネットワークに対する長期的な基礎科学技術力向上の取り組み、さらには量子情報理論(シャノン情報理論と量子力学の融合)に関する最新の情報が紹介された。
実証実験の進む量子情報通信
世界の量子コンピュータ研究者44名に実施した調査によると、現代暗号(RSA-2048)を24時間で解くことができる量子コンピュータ実現の可能性は、20~30年後には50%以上になるとされている。量子コンピュータは、いま対策を考えなければならない潜在的脅威なのだ。
現在はまだ解読できなくても、データを盗聴して保存さえしておけば、将来過去に遡ってすべてのデータが解読されてしまう恐れもある。国家レベルの大規模な機関は、すでにこのような攻撃を実行できる能力を有している。
量子暗号は、量子コンピュータを含むどんな計算機でも解読が不可能であることを証明できる現在唯一の暗号方式だ。あらゆる計算アルゴリズムを使っても解読が不可能な情報理論的安全性と、あらゆる盗聴攻撃を検知・排除できる(鍵共有)通信路への盗聴攻撃に対する安全性を有している。
1984年、BennettとBrassardが単一光子を使った量子暗号「BB84方式」を世界で初めて提案してから、量子暗号に関する研究は2000年頃まで物理学部門を中心とした基礎研究がメインだった。実用化の道を開いたのは、2002年に提案された、レーザ光源で単一光子並みの性能を実現する「デコイBB84方式」。この理論研究におけるブレークスルーによって光通信を活用した実装が可能になり、装置の開発やフィールド実験は急速に進展した。2020年には東芝が製品化も発表している。
量子鍵配送(QKD)ネットワークの実証実験は米国や欧州を初め中国、韓国など、世界各国で活発に進められている。講演では、我が国の取り組みとして「東京QKDネットワーク」が紹介された。
東京QKDネットワークは、東京都心と郊外の小金井市を繋ぐテストベッド光回線「JGN」を利用したもので、NEC、東芝、NTT、学習院大等の産学機関と一部の海外機関がそれぞれのQKD装置を導入してネットワークを構成した。2010年には世界初のQKDによる秘匿動画配信(TV会議)の実証に成功、この他にも様々な実証実験を世界に先駆けて成功させている。実証試験は現在も継続中であり、世界最長の運用実績を誇っている。
量子暗号に関する国際標準化も、国際電気通信連合・電気通信標準化部門や国際標準化機構・国際電気標準会議、欧州電気通信標準化機構などで行われており、我が国からは量子フォーラム・量子鍵配送技術推進委員会が各標準機構に参画、QKDネットワーク開発と実証の先行優位性を活用して、主導的に活動に寄与している。
講演では、QKDのアプリケーションとして「量子セキュアクラウド技術」も紹介された。QKDと現代セキュリティ技術を融合させたものだ。
データの寿命(秘匿期間)は、軍事(作戦計画や防衛装備品に関する技術情報)、行政(政策や外交情報)、インフラ(SCADA〈産業監視制御システム〉や新エネルギー開発情報)が概ね30年とされているが、医療に関しては100年以上の期間が求められている。医療データの中には電子カルテの他、非常に高い秘匿性が求められる遺伝子情報が存在しており、この情報からの差別や雇用の採否にも影響する可能性があるからだ。
そこで求められるのが、情報理論的に安全な超高秘匿ストレージネットワーク。量子暗号と現代セキュリティ技術(秘密分散)を融合させた超長期セキュア秘密分散保管技術だ。将来にわたって機密漏洩と不正改ざんを防ぐ安全なデータ保管を実現するもので、一部のサーバが棄損した場合でも必要時に原本データを復元でき、パスワード一つでも情報理論的に安全な本人認証が可能だ。
すでに様々な社会実証実験が我が国で実施されている。電子カルテ(高知医療センター)、ゲノムデータ(東北メディカルバンク)、レーザ加工拠点の重要回線(東大・京大・慶大)、生体認証の参照データ(スポーツ団体)、金融データ(野村HD)などの実証実験だ。
量子コンピュータのポテンシャルをフルに生かせる量子もつれを介して量子通信を伝送する量子ネットワークも、欧米でテストベッドが構築されており、我が国においても慶應義塾大学の矢上キャンパスと新川崎タウンキャンパス、かわさき新産業創造センターを量子ネットワークで結ぶ実証実験が行われている。
講演では、量子情報伝送・エンタングルメント配信・量子鍵配送の原理限界についても取り上げられた。武岡氏は、今以上効率的なpoint-to-point QKDプロトコルを考えようとしても無駄であり、限界を超えようとするならば必ず量子信号を中継する仕組みが必要だと指摘した。
(川尻 多加志)