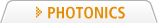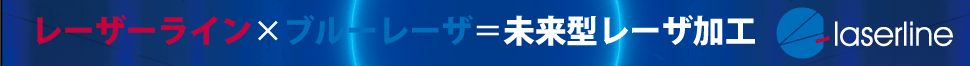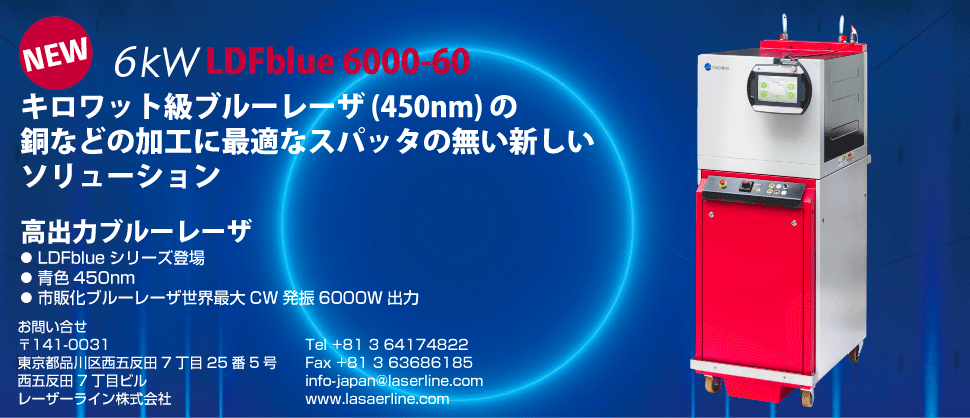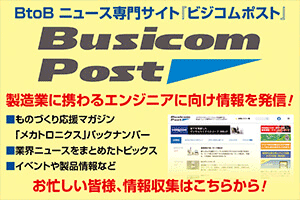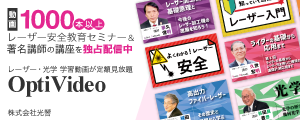国内リポート 詳細
ナノフォトニクス研究に新たな地平を拓くプラズモニクス
プラズモニクス研究会がシンポジウムを開催
June, 17, 2024, 東京--
6月7日(金)と8日(土)の両日、プラズモニクス研究会が、第20回のプラズモニクスシンポジウムを東京農工大の小金井キャンパス(東京都小金井市)とオンラインのハイブリッド形式で開催した。
「表面プラズモンは、金や銀などの貴金属表面に局在する電子密度波であり、電磁波と相互作用を起こし共鳴状態を形成する。この共鳴が起きている表面近傍の領域では、数桁倍に及ぶ電場増強が見られ各種の光学効果に顕著な高揚が観察される。 表面プラズモンは古くから物理学における重要な研究分野であったが、近年になりその応用研究も盛んに行われるようになってきた。特に、最近では光学分野におけるナノテクノロジーの強力なツールとして、3次元的な微少領域に局在させた表面プラズモンの利用が提案され、多様な研究が展開されるようになってきた。この中には、バイオセンシング、太陽電池、超高密度記録などをはじめとする研究も含まれている。このように局在化した表面プラズモンが展開する研究分野は、我が国の科学技術政策の重点推進分野であるライフサイエンス、ナノテクノロジー・材料分野と密接なかかわりをもつ。プラズモニクス研究会は、このような背景を踏まえ異なる専門の研究者の情報交換、研究交流のために設けられた。」(同研究会ホームページより)
今回のシンポジウムでは、招待講演(2本)と特別講演(1本)を含め計15本の講演が行われ、この他にも12件のポスターセッションや企業展示が行われた。ここでその全ては紹介できないので、以下に招待講演と特別講演のタイトルと講演者を記すとともに、次章以降で2件の招待講演の概要と、特別講演の最後で語られた「まとめ」を紹介する。
◆招待講演:表面格子共鳴による蛍光制御(京大・村井俊介氏)
◆招待講演:光共鳴ナノ構造を用いた超高感度分光センシング・イメージング(徳島大・矢野隆章氏)
◆特別講演:ナノ空間トポロジカル光場制御(北大・笹木敬司氏)
表面格子共鳴による蛍光制御
金属や誘電体ナノ粒子を光の波長ほどの間隔で並べるアレイ構造では、個々の粒子で共鳴が発生し、それに並行して周期に応じた光の回折現象が起こる。この両者が同時に起こる時、表面格子共鳴(Surface Lattice Resonance:SLR)という強い共鳴が発生する。
SLRは回折現象に由来するものだ。そのため、励起条件が強い角度および波長依存性を持ち、それゆえ特定方向から入射する特定の波長の光を面内に閉じ込めることができる。逆に、アレイに蛍光体膜を塗布してアレイ面内で蛍光を発生させれば、特定の波長の蛍光を特定方向へ放つことができる。
京大の村井俊介氏の研究グループでは、この性質を活かした照明・光源への応用研究を行っている。2018 年には金属アルミニウムのナノアンテナと蛍光体を用いて、蛍光強度の増大と指向性の付与に成功した。しかしながら、アルミニウムが光を吸収してしまうために使用中に蛍光体の温度が上昇、結果として効率が落ちてしまうという問題が起こった。これは、高輝度照明への応用において無視できないものであった。
そこで、研究グループではアルミニウムに替えて、光吸収の少ない二酸化チタンからなるナノアンテナを作製、効率を落とすことなく顕著な指向性蛍光を得ることに成功した。これを利用すれば、より明るく省エネ化を実現する照明が可能になる。マイクロLEDや手のひらサイズのプロジェクタ、ドローン用の軽量光源やマシンビジョンなどへの応用が期待できるという。
講演では、ナノアンテナをフレキシブルな樹脂に埋込んで、貼って剥がして何度でも使用できる「ナノアンテナシール」についても紹介された。シールは提供可能とのことだ。
光共鳴ナノ構造を用いた超高感度分光センシング・イメージング
徳島大の矢野隆章氏の研究グループでは、プラズモニック構造やメタマテリアルなどの光共鳴ナノ構造を用いて、高感度・高分解能で試料分子を分光センシング・イメージングする手法の研究・開発を行っている。
最近の成果としては、ラマン散乱分光や赤外吸収分光、蛍光分光など、各種の分光計測の高感度化・高分解能化によって、ペプチド・タンパク質の単一分子検出や新型コロナウイルスを迅速に検出する方法を実現してきた。講演では、種々の光共鳴ナノ構造を用いた高感度・超解像分光を用いた分子センシング・イメージング応用の一端が紹介された。
プラズモン強結合を利用したデジタル分光センシングの研究においては、金属ナノ粒子が金属ナノホール内に挿入されると金属ナノ粒子の散乱色が赤色から緑色に変化することを発見、この変化を利用したデジタル比色免疫センサを開発した。Au基板上にガラス層をつけることによって、アナログ式プラズモニックセンサと比べて検出感度が2桁以上も向上し、アルツハイマー病のバイオマーカの高感度検出を実現した。
高屈折率誘電体ナノ構造を用いた高感度分光センシング・イメージングの研究では、高屈折率誘電体ナノ構造のミー共鳴モードに由来する電場増強効果に着目、種々の誘電体ナノ構造を設計・作製することによって、可視から赤外域までミー共鳴波長を自在に制御して、蛍光、ラマン散乱、赤外吸収などの高感度分子分光センシング・イメージング応用を実現した。
研究グループでは、この他にもグラフェンや二硫化モリブデンを用いたプラズモン共鳴波長制御や表面増強分光センシング応用の研究も行っている。
なお、2025年5月には関連の国際会議、SPP11(The 11th International Conference on Surface Plasmon Photonics)が、東京都千代田区の日本教育会館・一ツ橋ホールで開催される予定だ。
ナノ空間トポロジカル光場制御
北大の笹木敬司氏の研究グループでは、スピン・軌道角運動量を持つ光「螺旋光」とナノ物質の相互作用を増強して制御・操作することを目的に、局在プラズモンにより回折限界を超えて光をナノサイズまで絞り込み、局在光場の振幅・位相・偏光の分布をナノスケールで自在に成形する光ナノシェーピング技術の開発研究を行っている。
笹木氏はナノ空間トポロジカル光場制御の研究について、金属ナノギャップ内の光場はN個の点電荷の位相制御で様々な形状を作り出すことができると述べ、さらにナノギャップ周囲近傍の光場は角運動量変換と干渉によって特異なトポロジカル特性を有すると指摘。ナノ局在光渦場の光トルクによりナノ物質の回転操作や分子集合構造の自在な制御ができ、磁気スキルミオン構造の生成・制御に向けたナノ局在光スキルミオン場の形成が可能であると述べていた。
(川尻 多加志)