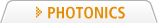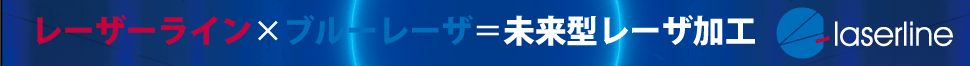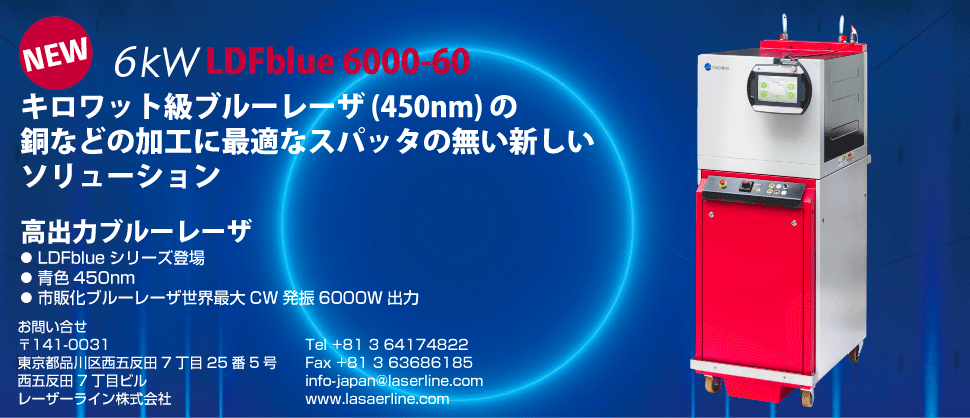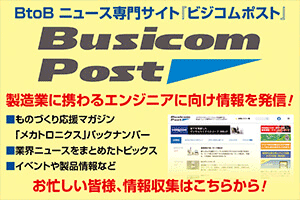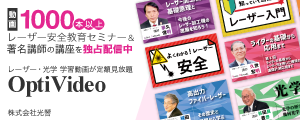国内リポート 詳細
長距離大容量光通信と超広帯域光伝送技術の最新動向
光ネットワーク産業・技術研究会、2024年度の第1回公開討論会を開催
May, 24, 2024, 東京--
光産業技術振興協会の光ネットワーク産業・技術研究会(代表幹事:慶應義塾大学教授・津田裕之氏)が5月13日(月)、2024年度の第1回公開討論会をAP東新宿(東京都新宿区)とオンラインのハイブリッド形式で開催した。
討論会のテーマは光伝送/ネットワーク関連技術の最新動向で、長距離大容量光通信や超広帯域光伝送技術の研究開発に加え、生成AIで注目を集めるLLM(大規模言語モデル)やGPU(画像処理ユニット)とネットワーク、ならびに光ファイバDAS(分布型音響センシング)による地盤モニタリング技術の研究開発など、計4本の講演が行われた。
本稿ではスペースの関係もあり、長距離大容量光通信と超広帯域光伝送技術に関する討論会前半2本の講演を中心に、その概要を紹介する。なお、当日のプログラムは以下に記す通りだ。
プログラム
◆長距離大容量通信用光ファイバの研究開発動向:川口雄揮氏(住友電気工業・光通信研究所光伝送媒体研究部主席)
◆超広帯域伝送技術の最新動向:相馬大樹氏(KDDI総合研究所・光トランスポートネットワークグループエキスパート)
◆LLMとGPUとネットワーク:川上雄也氏(ソフトバンク・共通プラットフォーム開発本部シニアネットワークアーキテクト)
◆光ファイバDASと微動探査による地盤モニタリング手法の開発:藤原広行氏(防災科学技術研究所・ マルチハザードリスク評価研究部門部門長)
長距離大容量光通信と超広帯域光伝送技術
年率で30%の成長を続ける通信容量は、今後もさらなる拡大が求められている。数千kmから1万kmに及ぶ海底長距離光通信において、これまでその拡大に貢献してきたのが空間分割多重(SDM:Space-Division Multiplexing)方式だ。具体的な手法としては、ケーブルに収容する光ファイバの数を増やす多心化が用いられてきた。しかしながら、海底ケーブルにおいてはケーブルの太さに制約がある。そのため、光ファイバを用いた従来の多心化は限界に達しつつあると言われている。
住友電気工業の川口氏は「長距離大容量通信用光ファイバの研究開発動向」の講演の中で、SDM光ファイバや極低損失ファイバの研究開発に関する最新動向を紹介した。
長距離大容量通信に適したSDM光ファイバでは、ケーブル内の光ファイバ数を増やすため、従来の250μm外径から200μmに細径化した光ファイバの他、マルチコアファイバ(MCF)やマルチモード光ファイバ(MMF)/数モード光ファイバ(FMF)の研究開発が進められている。
MCFには非結合型とランダム結合型の2種類があり、同社では世界初の非結合2コアファイバの量産化に成功している。講演では、ケーブルあたり1Pb/sを超える伝送容量実現は可能だという認識が示され、さらにその先の、いわゆるBeyond-1Pb/sケーブルを目指す4コア、およびそれ以上のコアを有する各種MCFについても、研究開発の最新動向が紹介された。
長距離光通信システムにおいて、もう一つ重要な特性とされるのが光ファイバの伝送損失だ。デジタルコヒーレント方式が導入されて以降、光ファイバには極低損失特性が要求され、その研究開発は加速したが、川口氏の研究チームでは、屈折率分布を適切に設計するとともに粘性を調整するためコアにフッ素を入れ仮想温度を低減させることで、シリカコアファイバとして最も低損失な0.1397dB/kmという値を実現した。講演では、さらなる低損失化に向けたQSMF(Quasi Single-Mode Fiber)や高温高圧の印加、Hollow Core Fiber(HCF:0.08±0.03dB/kmを達成して、計算予測ではさらなる低損失も期待できるという)についても紹介された。
川口氏は、SDMファイバでは200μmファイバは250μmファイバと比較して特性の悪化もなく、実用 上問題ない環境特性、機械特性を有すると指摘。MCFにおいては、2コアファイバが海底ケーブルに導入されており、さらなる大容量化に向けた4コアファイバは、ファイバだけではなく周辺技術の開発も必要だと述べた。一方、極低損失光ファイバにおいては、上記のようにシリカコアファイバの低損失化やHCFの極低損失化などが実現されており、今後もさらなる低損失化が期待されると述べた。
KDDI総合研究所の相馬氏は「超広帯域伝送技術の最新動向」の中で、既存のC+Lバンド伝送システムからO、E、S、Uバンドなどの新たなバンドに信号帯域を拡張するマルチバンド伝送に関する研究開発について紹介した。
マルチバンド伝送は、光ファイバ中の伝送損失や光増幅器および光送受信器の高性能化などに関する課題は残っているものの、現状で広く敷設されている標準のシングルモードファイバ(SMF:single-mode fiber)が利用できるという特長を有している。
近年では、既存のC+Lバンドを波長軸や空間軸に拡張したマルチバンド伝送やSDM大容量波長多重伝送実験も数多く行われている。標準SMFを用いたS+C+LバンドやC+L+Uバンドを用いた3バンドWDM伝送実験、E+S+C+Lバンドを用いた4バンドWDM伝送実験、O+S+C+L+Uバンドを用いた5バンドWDM伝送実験、37THzを超える総信号帯域を持つO+E+S+C+L+Uバンドを用いた6バンドWDM 伝送実験などが代表的なもので、SDM技術としては従来のケーブル構造や送受信器が適用できる標準外径の非結合型MCFを用いてC+LバンドやS+C+Lバンドに渡った4コアファイバWDM伝送実験などが報告されている。
相馬氏の研究グループは、より商用環境に近い敷設光ファイバケーブルを用いたマルチバンド伝送実験とSDM伝送実験を実施。敷設SMFを用いてO+S+C+L+Uバンドに渡ったマルチバンド伝送実験を行い、762波長チャンネルで伝送距離45km、25THzを超える帯域と119.3Tbit/sの伝送容量を実現した。さらに、敷設非結合型4コアファイバを用いて、C+LバンドのマルチバンドSDM伝送の実験を行い、伝送距離2,160kmと121.9Tbit/sの伝送容量も達成している。
二つの研究成果は、従来のC+Lバンド伝送システムに比べ、SMFを用いたマルチバンド伝送技術で約2.7倍、4コアファイバを用いたSDM伝送技術では約4倍の総信号帯域の拡張が可能であることを証明したものだ。
次回の予定
後半2本の講演にも触れておこう。LLMにおけるキーデバイスであるGUPはインターコネクトを含め、有望技術を開発した新興企業を買収するなどして、もともと圧倒的な地位を築いていたNVIDIAの独壇場という印象だ。
光ファイバDASに関しては、新たに埋設する光ファイバや既存の光ファイバを利用し、同時測定する微動計データとの対応関係を把握することで、従来の250mメッシュの地盤モデルを、10m以下の間隔で地盤の揺れを計測・データ処理できる技術を開発するもので、今後の進展に期待が集まっている。
なお、次回の公開討論会は7月26日(金)、「200Gbaudが視野に入った光変調デバイスの動向」をテーマに、東工大・大岡山キャンパスの蔵前会館で開催される予定だ。詳しくは下記URLを参照されたい。
https://www.oitda.or.jp/study/
(川尻 多加志)