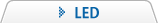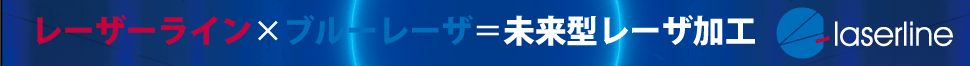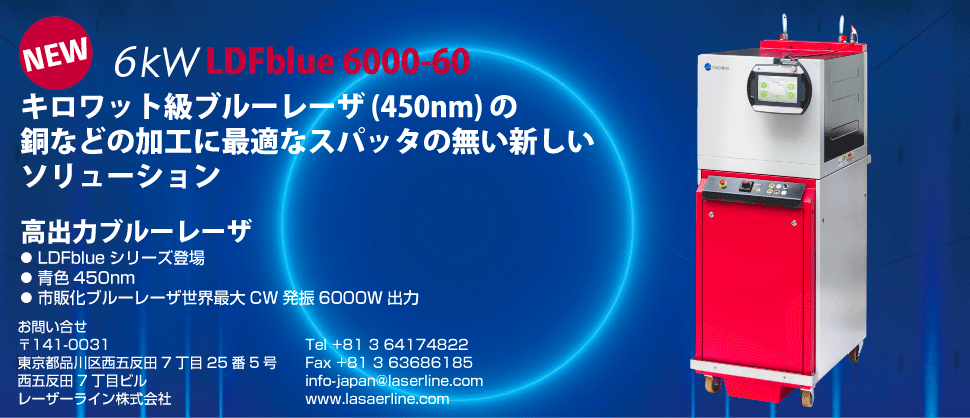国内リポート 詳細
日本の半導体デバイスはなぜ凋落したのか
マイクロ固体フォトニクス研究会が半導体産業と経済安全保障をテーマに研究会を開催
April, 7, 2022, 東京--かつては圧倒的な競争力と市場占有率を誇った日本の半導体デバイスは、何故ここまで凋落してしまったのか。経済安全保障の観点からも、ようやく半導体産業復活の機運が高まる中、3月16日(水)に開かれた第4回マイクロ固体フォトニクス研究会では、「半導体産業と小型集積レーザーの接点」というテーマのもと、多方面から関心が集まる半導体と経済安全保障にまつわるトピックスが取り上げられた(研究会は、第4回レーザー学会「小型集積レーザー」専門委員会と第4回科学技術交流財団「ジャイアント・マイクロフォトニクス」研究会との合同開催)。
小型集積レーザ
物質や材料の光に対する性質をマイクロメーターオーダーで制御して光学特性を強調したり、新たな機能を発現させることを可能にしたのがマイクロ固体フォトニクスだ。マイクロ共振器によって固体レーザの小型化を実現したマイクロチップレーザは、機能集積した極めて小さな体積から高輝度で制御された光波を創り出すとともに、これまでの高出力レーザの大幅な小型化を実現、場所が限定されない利用を可能にすると期待を集めている。
一方、これらをビルディングブロックとして組み上げれば、これまで不可能だった極限的な高出力レーザや波長・位相を自由自在に制御できるレーザの実現も可能になる。レーザ加工の特長である高輝度性を利用した非熱加工や衝撃波を用いた加工には、尖頭値が非常に高いジャイアントパルスが必要で、その発生には共振器品質因子Q(quality factor)を短時間に切り替えて、レーザ媒質中に蓄積された反転分布エネルギーを瞬時に取り出すQスイッチ法が用いられる。
Qスイッチ法は、蛍光寿命が長い希土類固体レーザに適しており、端面励起で共振器長を短くすることが容易だ。パルス幅は共振器長に比例するので、出力するパルス幅を短くでき、その結果、出力ジャイアントパルスの尖頭値を高くできる。このQスイッチとセラミックレーザを用いてジャイアントパルスを発生させるのが、小型集積レーザ(Tiny Integrated Laser:TILA)だ。
平等拓範氏(理研/分子研)は、新しい高出力レーザの形状として、繰り返し透明高熱伝導率材料でレーザ媒質を挟み込んだ分布面冷却(Distributed Face Cooling:DFC)構造を提案した。これは、複数枚のサファイア板とNd:YAGを交互に直接接合するもので、これによって高出力レーザや高輝度レーザの最先端技術である面冷却マルチディスクレーザを小型集積レーザにできる。ジャイアントパルスマイクロチップレーザの性能を飛躍的に高め、新たな科学技術、産業分野の開拓に貢献すると注目を集めている。
小型集積レーザは、レーザ加工やエンジン点火、自由電子レーザや放射光源、粒子加速器の小型化など、多方面での応用が期待されている。その研究開発は、理研のレーザー駆動電子加速技術開発グループで進められている他、分子研の社会連携研究部門でも実施されている。分子研内には同レーザの社会実装を目指す「TILAコンソーシアム」も設立されている。会員は、社会連携研究部門との共同研究や分子研が所有する知的財産実施に係わる優遇措置に加え、同部門が収集したデータの提供や技術相談も受けることができる。
プログラム
今回の研究会では、日本の半導体露光装置や半導体デバイス産業が衰退して行った原因やその過程に加え、我が国が打ち出している経済安全保障に関するトピックスが紹介され、会員による研究開発事例も報告された。当日プログラムは以下に示す通りだが、本稿では半導体露光装置における日本メーカーとASLMを比較したギガフォトン・榎波龍雄氏の講演を中心にレポートをお届けする。
◆座長挨拶:平等拓範氏(理研/分子研)
◆アーキテクチャ進化における製品開発マネージメント:榎波龍雄氏(ギガフォトン)
◆日本の半導体産業インフラストラクチャーと経済安全保障:山下政治氏(マイクロセミコンダクターリサーチ)
◆経済安全保障とセラミックス:矢野友三郎氏(日本ファインセラミックス協会)
◆会員活動紹介 マイクロチップパルスレーザのご紹介:永田毅氏(パナソニックプロダクションエンジニアリング)
日欧半導体露光装置メーカーの相違点
製品アーキテクチャには、インテグラルアーキテクチャとモジュラーアーキテクチャの2種類がある。前者は、機能要素と製品の構造の対応が1対1ではなく、それぞれの要素間のインターフェイスが相互干渉的になっている。製品としては自動車などがこれに相当し、日本企業が得意とする。一方の後者は、機能要素が製品の構造と1対1で対応し、かつそれぞれの要素間のインターフェイスが切り離されている。パソコンなどがこれに当てはまり、欧米企業が得意とする。
ニコンやキヤノンなどの日本勢とASLMの半導体露光装置における市場占有率を見てみると、日本メーカーは1990年代後半、圧倒的な地位を確保していたが、その後ASLMが急進して2020年には約80%の市場を掌握、日本メーカーは両社を合わせても20%程度と、圧倒されている。
半導体露光装置は究極の擦り合わせ型製品で、日本企業が得意とするはずであった。しかし、露光機はその後アーキテクチュラル・イノベーション(デュアルステージ技術と液浸技術)という大変革期を迎えた。ASMLは、このアーキテクチャのスムーズな変更に成功したが、日本メーカーは同じアーキテクチャを目指したものの、思い通りには行かなかった。
双方の顧客を見ると、ニコンはIntelや東芝、日本電気などで、ASMLはSamsungやTSMC、Hynixなどであった。言い換えると、ニコンは最も優秀な半導体メーカーすべてを押さえていたので、ASMLは二番手メーカーと手を結ぶしかなかったというのが実状だった。
顧客の違いは設計方針の違いにも表れた。ニコンの場合は、複雑なデザインが求められるIntelのマイクロプロセッサがターゲット。そこでは優れたチューニング能力や個別要求に合わせた多様なパフォーマンスが求められた。ニコンは、その個別ニーズに見事に対応した。一方のASMLの場合は、必要に応じた複雑性と処理能力があれば良い(それほど解像度が要求されない)SamsungやTSMCのDRAMやASICといった汎用製品がターゲットで、そこでは使いやすさや統一されたパフォーマンスが求められた。
構成要素(コンポーネント)における自社製と外注の違いも大きかった。ニコンは投影レンズ系や照明系、制御ステージ、ボディ、アライメント系など、光源以外は内製化にこだわった。これに対しASLMは、ソフトウエア以外はZeissやPhilipsなどに(1コンポーネント1社に限定して)外注した。
製品アーキテクチャにおいては、コンポーネント知識よりアーキテクト知識が重要だ。ニコンは能力の高い(調整能力を持ったIntelという)ユーザーを顧客に持つがゆえ、その知識が蓄積されないという状況に陥ってしまった。
アライアンスパートナーの有無にも大きな違いが生じた。論文執筆者を調べると、ニコンは自社単独が多いのに対し、ASLMは共著や外部の執筆者が多い。そこから導かれるのは、ニコンには密接なアライアンスパートナーがおらず、ASLMにはいたという事実だ。
さらに、1987年からの約10年間、日本には半導体コンソーシアムが存在しなかった。その間、欧米では日本を模倣してimecに代表されるようなコンソーシアムが長期に渡り、継続的に運営されていた。
ASLMの成功要因を組織体制と運営から整理すると、その基本コンセプトはimec内のテーマ別組織と連携・決定するとともに、プロダクトマネージャー、システムエンジニア(SE)、マーケティングマネージャーの3人が組織を統括、リーダーシップはプロダクトマネージャーとSEが取り、中でもSEはスケジュール、コストを含む全て(コンセプト、システム設計、詳細設計)を統括する役割を担った。サプライヤーに対しては、仕様設計と性能評価について詳細なドキュメントを提出させ更新して行くマネージメントを実施、研究開発ではお互いに情報を開示、収益性については共同責任を取るという形が作られた。リードタイム管理についても、2次サプライヤーレベルまで掘り下げた細かい管理を行った。
では、モジュラーアーキテクチャを採用している企業は、将来に亘っても安泰なのだろうか。そこには落とし穴もあるという。例えば、新しいイノベーションをベースにした製品が求められる時には、モジュラーキテクチャからインテグラルキテクチャに戻るのは非常に難しいとされる。なぜなら、モジュラーアーキテクチャではモジュールの内部の話しかしないグループが乱立しており、新たな製品に最適だと思って各グループが夫々のモジュラーを設計しても、組み合わせてみたらまったく動かないという場合が多々あるというのだ。そこではインテグラルアーキテクチャにおいて大切とされる、モジュラー間で「会話」ができるシステムエンジニアグループが重要になってくる。
研究会では、経済安全保障という観点からも日本の目指すべき方向が提案された。半導体は戦略物資で、先端兵器の製造にも不可欠なパーツなので、軍事的な安全保障にも欠かせない。確かに日本は半導体集積デバイスや超微細な露光装置では諸外国に追い抜かれた。だが、C-MOSイメージセンサを始めとしたディスクリート半導体や周辺部品、半導体用シリコンウェハ、フォトレジスト、フォトマスクなどの部材、炭化フッ素ガスを始めとした高純度薬品やガス、CVDなどの製造装置等々、日本の半導体産業インフラストラクチャー企業は強い競争力を保持している。この状況を踏まえ、講演では中国に対抗するために日本の強みと米国の強みを活かした日米半導体同盟の締結が提唱された。
日本経済の世界評価は、G7の中で最階位を低迷している。にもかかわらず、経済大国・技術大国という幻想を抱き続ける日本。今こそ、中国に劣っているという(見たくない)現実を真剣に危惧する必要があるという。経済安全保障の基本は経済であり、それこそが交渉の源泉。問題の一端には、総理大臣の頻繁な交代や、官僚が部署を担当する期間の短さもあるようだ。技術優位性の保持は企業だけが頑張っても難しく、国の戦略的支援が継続的に必要だ。講演では、セラミックは日本にとっての最後の砦の一つだとして、先端材料として多種多様な部品や製品に幅広く応用される横断的なコア技術であるがゆえ、その技術向上と保持(技術漏洩防止)のため、諸外国と伍するかたちで研究開発を継続的に推進する制度の整備と、欧米、中国、韓国に対する技術動向調査の継続的実施が必要との提言も示された。
次回の研究会
研究会は今後6月、9月、12月と来年2月に開催される予定だ。次回第5回研究会は6月30日(木)、分子研とオンラインのハイブリッド形式で開催される。詳しくは、下記のTILAコンソーシアム内イベント情報に掲載される予定なので、下記URLを参照していただきたい。
https://tila.ims.ac.jp/
(川尻 多加志)