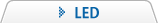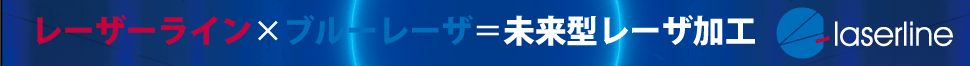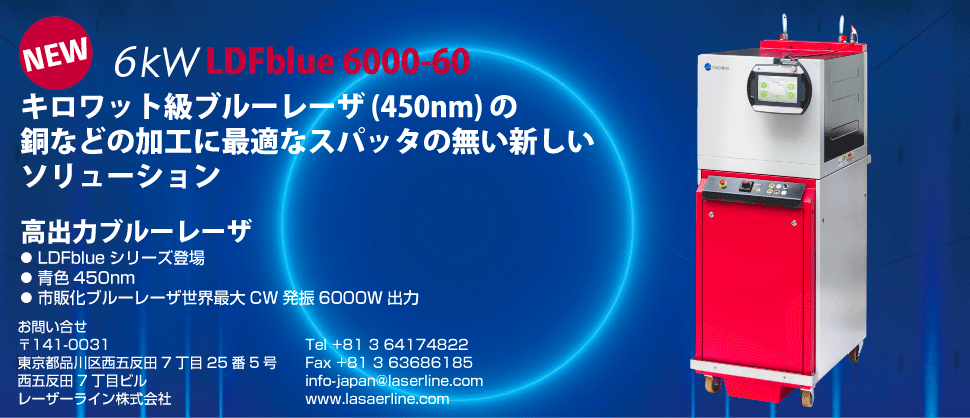国内リポート 詳細
国際光デーで見えた我が国が誇る光科学技術
日本学術会議 総合工学委員会ICO 分科会、「国際光デーシンポジウム2019」を開催

July, 1, 2019, 東京--6月28日(金)、東京都港区の日本学術会議講堂において「国際光デーシンポジウム2019」が開催された(主催:日本学術会議総合工学委員会ICO分科会(委員長:東大・名誉教授/特任教授・荒川泰彦氏)、共催:国際光年協議会)。
ICOは1947年に創設された、53の各国委員会とOSAやSPIEなどの国際学会から成る国際科学連合体の一つで、我が国では日本学術会議がその対応組織になっている。今回のシンポジウムを主催したICO分科会は、このICOへの実際的な対応等を審議するとともに、我が国の光・量子科学技術の発展に資する活動を行うことを目的に設立された組織だ。
国連は、光に関する新しい知識と光関連の活動を促進することの重要性を一般社会の中に浸透させていくため2015年を「国際光年」と定め、ユネスコがその推進を行うこととなった。そして、ユネスコは2018年から5月16日を「国際光デー」と制定、5月16日に決めた理由は、セオドア・H・メイマン氏が、1960年のこの日にレーザ発振に成功したという主張に基づいている(本当にレーザ発振であったかについては異論もある)。
ICO分科会では、この国際光デーを記念するシンポジウムを昨年の7 月7日(メイマン氏が所属していたヒューズ社がレーザ発振成功の記者会見を行った日)にも開催したが、この趣旨を引き継いで光科学技術の歴史と現状を俯瞰するとともに、最先端の話題を紹介するため今回のシンポジウムの開催を決定。6月28日の開催になったのは、今年の7月7日が日曜日であるということと会場確保の観点からとのことだ。
同分科会では、シンポジウム開催によって、この分野が生み出したインパクトや今後のイノベーションを国内にアピールするとともに、幅広い世代や立場の研究者を発表者とすることで、学会間の交流、世代間の交流、次代の若手育成、新しい産業やコミュニティー創出を推進したいとしている。
ちなみに、日本学術振興会の光エレクトロニクス第130 委員会では3月8日を「光の日」としており、毎年3 月8 日近辺に「光の日」公開シンポジウムを開催している。この日が「光の日」に選ばれた理由は、光の速さが真空中でほぼ 3×108m/s であって、フォトンは吸収されない限り休むことなく走り続けるとの理由からだ。したがって、我が国においては「国際光デー」と「光の日」という二つの関連行事が行われている。
今回のシンポジウムの参加登録は220名に及び、世界をリードする我が国における最先端の光科学技術の現状と動向が紹介された。以下に当日のプログラムと、各講演において印象に残った言葉を紹介する。
◆第一部
司会:中野義昭氏(日本学術会議第三部会員、東大・教授)
開会挨拶「我が国における国際光デーの意義」荒川泰彦氏(日本学術会議連携会員、東大・名誉教授/特任教授)
基調講演「Society 5.0への社会変革と大学の役割」五神真氏(日本学術会議第三部会員、東大・総長)
講演1「面発光レーザーの発明から爆発的広がりまで」伊賀健一氏(東工大・名誉教授/元学長)
講演2「量子‐古典クロスオーバーの物理と光ニューラルネットワーク」山本喜久氏(スタンフォード大・名誉教授、NTT Φ Laboratories・所長)
◆第二部
司会: 馬場俊彦氏(日本学術会議連携会員、横浜国大・教授)
講演3「Spring-8とSACLAが拓く高エネルギー光科学」石川哲也氏(理研放射光科学研究センター・センター長)
講演4「細胞検索エンジンが拓く生物学・医学の新世界」:合田圭介氏(東大・教授)
閉会挨拶「今後への期待」松尾由賀利氏(日本学術会議第三部会員、法大・教授)
開会挨拶を行った東大の荒川氏は、国際光デーの目標となっている「科学技術のための光」、「持続可能な開発のための光」、「人材育成と文化に貢献するための光」の三つの柱を紹介するとともに、今回のシンポジウムによって分野を超えた様々な交流が生まれることを期待すると述べた。
次に登壇して基調講演を行った同じく東大の五神氏は、AIやビッグデータを活用する社会における日本の優位性として、デジタル革命を支える高度な人・技・知、AI・ロボットへの社会受容性の高さ、全国に張り巡らされた高速・広帯域の光ファイバネットワークなどを挙げ、それゆえ「日本にはチャンスがある。日本が国際ルール作りを主導すべきだ」と提唱した。その一方で、高齢化・少子化によって日本に時間がないのも現実であり、だからこそスピーディーな改革が求められると指摘。そして、「国立大学は産業・社会基盤を支えると柱となる」として、それには「社会が期待している今がチャンスだ」と述べた。
東工大の伊賀氏は、自身の発明したVCSELは2020年にチップベースで2,200億円を突破する市場規模となっており、搭載されたレーザプリンタだけを見ても約1兆円の売上があるというデータを紹介。さらに、マイナーな評判から始まったVCSELは大きなイノベーションと産業を生み出し、高速・パラレル相互接続や3次元測距とモノの認識、さらには10kWの電力アプリケーションに到達、高速・低遅延・同時アクセスを実現する5G時代には、考えたことのない賢いVCSELのアイデアが出てくるのではないかと期待を寄せた。
NTT Φ Laboratoriesの山本氏は、量子ユニタリ計算を用いた孤立系量子コンピュータと量子散逸計算を用いた開放系量子ニューラルネットワークを比較紹介。前者の原理は、外界から遮断された孤立系での状態ベクトルのユニタリ回転で、量子リソースとしては量子エンタングルメントを使用、物理が明確でユニバーサル計算が得意である一方、雑音やエラーに対して脆弱であり、隠れた周期性や構造のある問題(現代暗号の解読)などに用いられるという。後者の原理となっているのは、外界からの励起や外界への散逸のある開放系での自己秩序形成で、量子ディスコードを用い、雑音やエラーに対しては強靭だが、物理が見えにくくヒューリスティック計算であることが短所だという。周期性や構造のない問題(組み合わせ最適化など)に用いられるとのことだ。
休憩を挟んで、理研の石川氏は共用運転開始以来22年を経過したSpring-8は依然として世界での第一線の地位にあり、この間25万人を超える利用者があったことを紹介。一方のSACLAは世界で2番目のX線自由電子レーザで、X線領域でのコヒーレント科学を切り開いていると述べ、高エネルギー光科学の行方は、「何が起こっているかは分かっていても、何故起こるか分からない現象」の何故を明らかにすることだと指摘した。
講演のしんがり、東大の合田氏は、かつては一人であった論文の著作者は共著という形を取るようになり、年を追うごとに共著者数の人数は増え続け、このまま行けば2030年には7.5人、22世紀には20人以上になるという予測を紹介した。特に最近の研究では、自身の研究を例に、様々な分野の研究者との共同研究が増えており、だからこそ特定分野に特化しない光科学は異分野を橋渡しする共通言語になると、光科学の重要性を訴えた。
最後に閉会挨拶を行った法大の松尾氏は、レーザに代表される光の研究は、それ自身を掘り下げる縦糸であるとともに、様々な学問分野に対して適用可能な横糸でもあると指摘、光の科学技術はさらに進化して、我々の生活と知的好奇心を豊かにしてくれるとシンポジウムの講演を締め括った。
講演終了後は隣接する会場において、国内研究グループから推薦された次代を担う気鋭の研究者67名によるポスター講演が行われた。それらが終了後、別会場で行われた懇談会にも多くの人々が出席、講演者を交えた活発な議論が交わされていた。大学・研究機関と産業界の交流、さらには世代間の交流といった、同分科会が目指すコミュニティーから生まれる研究開発の進展と、そこから育つ新しい産業に期待したい。
(川尻 多加志)