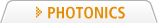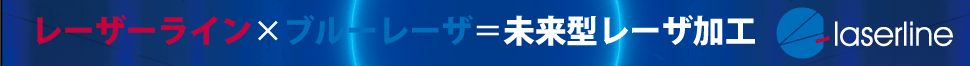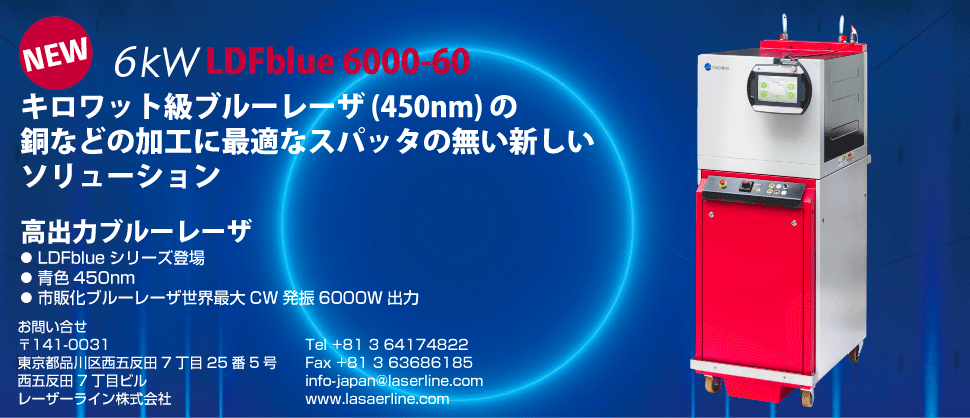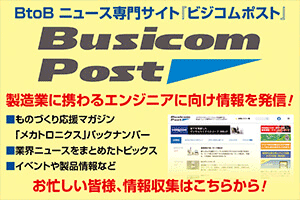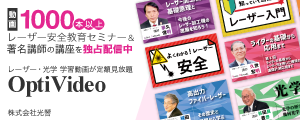Science/Research 詳細
金属3Dプリンティング特有の「セル組織」が高強度の理由
July, 8, 2025, 大阪--大阪大学大学院工学研究科の菊川泰地(博士前期課程)、石本卓也特任教授、中野貴由教授らの研究グループは、金属3Dプリンティング技術によって自発的、階層的、かつ特異的に形成される、マイクロメートルスケールの結晶学的ラメラ構造と、ナノメートルサイズのセル組織の強度への寄与を、定量的に個別解析し、セル組織(セル特異界面)が極めて大きな強化をもたらす因子であることを明らかにした。
寄与を個別に解明するため、① セル組織は熱処理によって、② ラメラ構造は特異なスキャンストラテジーの設計によって、独立に消去する方法を樹立した。その結果、ラメラ構造の存在は数%の強度上昇である一方で、セル組織は40%(1.4倍)もの強度上昇をもたらし、セル組織のきわめて高い強化効果を明らかにした。
研究で見出されたセル組織による強化は、これまでに3Dプリンティング造形材において明らかになった強化機構や強度の異方性、さらには、3Dプリンティングが得意とする形状に基づく機能性との重畳によって、従来の力学機能の限界を突破し、人為的カスタム力学機能制御の範囲を大幅に拡大する可能性があると期待されている。
研究成果は、Taylor & Francis発刊の材料科学に関するトップジャーナルの速報誌である「Materials Research Letters」誌に6月24日(火)午後2時(日本時間)に公開された。
研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)
3Dプリンティングの高い形状自由度や部品点数の削減を利点として、種々の製品にて3Dプリンティング製への「置き換え」が検討されています。一方で、本研究で得たセル組織による強化に関する知見は、LPBF製への置き換えが、単なる製造方法の変更にとどまらず、製品の力学機能の飛躍的な向上(それに付随する超軽量化)をもたらす可能性を秘めていると言えます。セル組織は、凝固の際の濃度分配に基づき、LPBFプロセス中にて多くの合金系で出現する。すなわち、社会基盤製品を構成する種々の合金材料にて適用可能であることから、今回の成果の波及効果は極めて広範な産業分野に及ぶものと期待している。さらに、3Dプリンティング製金属材料の機能の解明や人為的制御には、特異組織の形成機構や強化機構解明、特異組織の制御法解明といった新たな学理構築が不可欠であることから、この成果は学術的にも大きな意義を持つ。
(詳細は、https://resou.osaka-u.ac.jp)