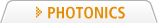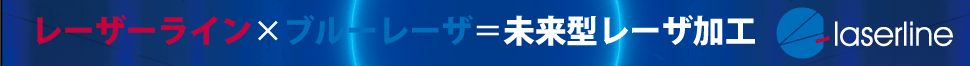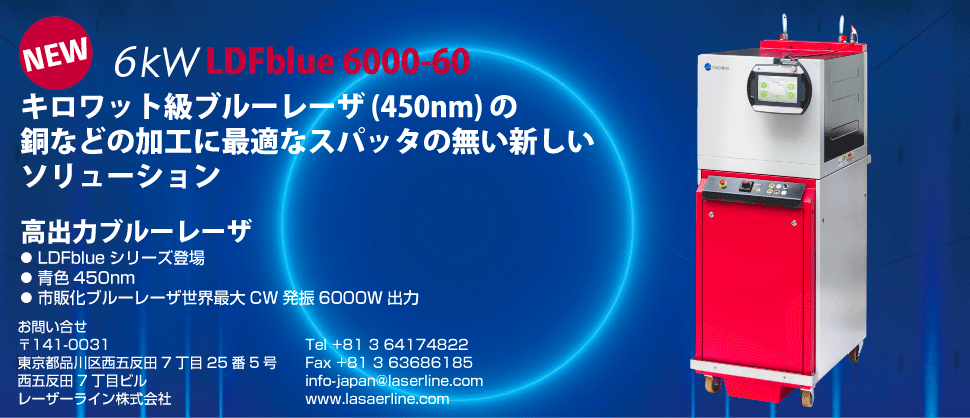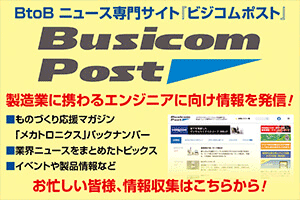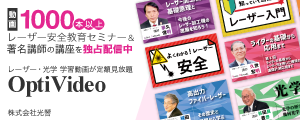Science/Research 詳細
AI技術の活用で導波路の接続状態の良否を自動判定

June, 23, 2025, つくば--産業技術総合研究所(産総研)物理計測標準研究部門 坂巻 亮 主任研究員、昆 盛太郎 研究グループ長は、ミリ波からテラヘルツ波にわたる電磁波の測定における導波路の接続状態を、機械学習を用いて自動判定する技術を開発した。
導波路とは、電磁波を特定の方向に効率よく伝送するための通り道。近年、ミリ波からテラヘルツ波にわたる高周波帯の電磁波を扱う通信機器などのデバイスの開発が進められている。これらのデバイスに多数搭載されている電子部品の透過特性や反射特性などの性能を評価する際、評価対象である電子部品と導波路を接続する作業が生じる。従来、導波路の接続状態は作業者が目視や手作業で確認していたが、人によって接続の良否の判断が異なり、測定精度にバラつきが生じていた。
今回、導波路の接続状態によって変化する測定データを収集し、AI技術の一つである機械学習によって導波路の接続の良否を自動的に判定するシステムを開発した。この成果により、熟練者でなくとも安定して高精度な測定を実施でき、研究開発や産業分野でのテラヘルツ技術の利用が向上すると期待される。
今後の予定
今後は、この技術を活用した測定システムのセットアップの自動・自律化技術の開発に取り組んでいく。今回の技術は接続状態の判定技術になるが、これに導波路の電動アライメントシステムを組み合わせることによって、自律的かつ自動的な装置セットアップを実現することができる。これを実現することで、ミリ波・テラヘルツ波評価システムの信頼性向上や、オートメーション化(オートファクトリー化)への寄与が期待される。特にプローブを用いた測定システムにおいては、装置のセットアップ作業におけるプローブの破損が発生することがある。これらのセットアップ作業を自動・自律化することにより、高価な高周波機器の管理コストの低減を見込むことができる。従来では熟練者による装置セットアップが必要であったところを、誰でも(あるいは無人で)実現可能にすることによって、6G通信やテラヘルツスキャナーといった次世代高周波技術の技術開発の加速化を推進する。
この技術の詳細は、2025年6月15日から20日にサンフランシスコ(アメリカ)で開催される「IEEE MTT‑S International Microwave Symposium(IMS)2025 workshop/general session」で6月15日に発表される。