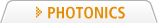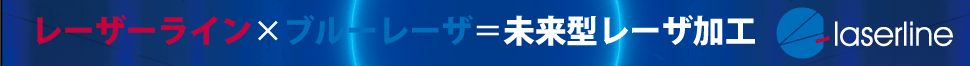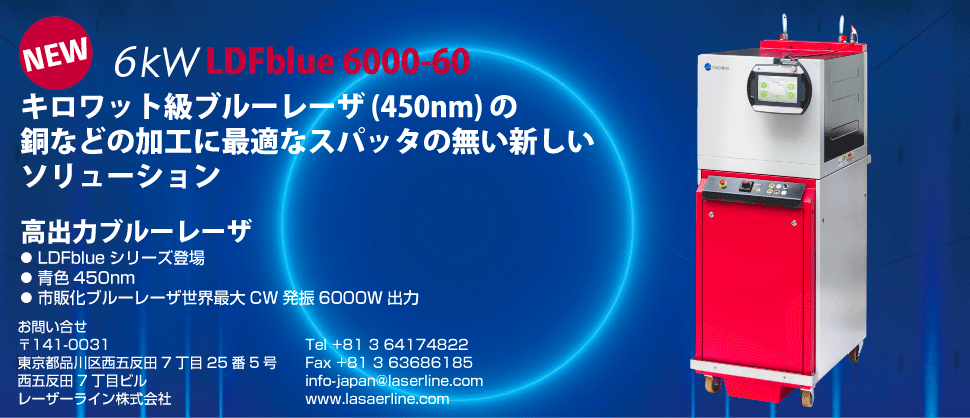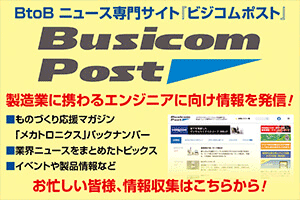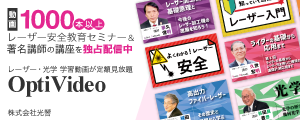Science/Research 詳細
補償光学が太陽のコロナの視界を強化

June, 18, 2025, Washington--太陽に関する長年の謎は、何十年にもわたって科学者を困惑させてきた:なぜ太陽の大気はその表面よりもはるかに熱いのか?表面の温度は約6000Kだが、太陽の外側の大気(コロナ)は数百万ケルビンまで加熱される可能性がある。太陽大気とコロナ加熱につながる物理的プロセスを理解するためには、高空間分解能の観測が重要である。
現在、米国の研究者たちは、コロナ構造の画像と動画をこれまでで最も詳細に生成する新しい補償光学技術を開拓している(Nat. Astron., doi: 10.1038/s41550-025-02564-0)。Conaと呼ばれるこのシステムは、カリフォルニア州のビッグベア太陽天文台(BBSO)にあるグッド太陽望遠鏡の回折限界に達し、これまで知られていなかった現象とコロナの細粒度の特徴を明らかにした。
Conaのご紹介
これまで、大口径望遠鏡の回折限界での高空間分解能の観測は、光球と呼ばれる太陽の表面でのみ可能で、コロナでは不可能だった。コロナには、太陽のプロミネンス、太陽の磁場によって形成された大きなループ状の構造、高温のプラズマが強い磁場で冷却されて凝縮し、光球に落下するコロナ雨などのプラズマ現象がある。
補償光学は、地球の大気中の乱流を補正するために、すべての主要な太陽望遠鏡に長い間適用されてきた。しかし、アダプティブミラーの形状調整に使われる波面センサは、光球構造専用に設計されていた。現在の研究では、補償光学を特にコロナ天体の観測に活用できる新しい波面センサを開発した。
「この補償光学の新たな応用により、コロナ加熱の謎や噴火の引き金となる可能性のある小規模プラズマと磁場のダイナミクスの新しい診断方法を可能にしたいと考えている。われわれちがConaと呼ぶコロナ補償光学システムにより、太陽のコロナの表面上方にある冷たいプラズマの特徴の地球の乱流大気を通じて、回折限定の観測が可能になる」と、国立太陽天文台(NSO)の補償光学科学者、研究著者のDirk Schmidtはコメントしている。
コロナの新たな視点
ほとんどの補償光学システムと同様に、Conaは波面センサを使用して光学収差を測定し、357個のアクチュエータを備えた変形可能なミラーを使用して光学収差を補正する。Conaの相関するShack-Hartmann波面センサは、水素アルファ光を放出する太陽の表面上の薄暗い特徴用に特別に設計された。
「非常に明るく、非常にコントラストの低い表面の波面センサとは対照的に、フルウェル容量の大きい高速カメラが必要だったが、ここでは、低照度アプリケーション向けに最適化された高速で低ダークノイズのカメラが必要になる。さらに、波面センサ設計のパラメータも特に最適化されている」(Schmidt)。
Schmidtと同氏の同僚は、世界で2番目に大きい太陽望遠鏡、1.6mのグッド太陽望遠鏡(Goode Solar Telescope)でこの技術を開発し、70km以上の解像度で回折限界に達した。観測の最初の数日間で、奇妙な微細構造で急速に進行するプラズマの特徴が明らかになり、チームはそれをねじれたコロナルプラズモイドと名付けた。その後、Conaは、コロナ加熱のマーカーであるコロナ雨の最小スケールに関する新たな知見を明らかにした。
「次のステップは、この技術を、国立太陽天文台がマウイ島で運営している全米科学財団の4mダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope)に適用することである。」とSchmidtは話している。「Inouye Solar Telescopeの口径は、グッド太陽望遠鏡のほぼ3倍の大きさである。そのはるかに大きな絞りは、補償光学にとって非常に困難な課題を提起し、ハードウェアにより厳しい要件を課している。」