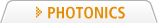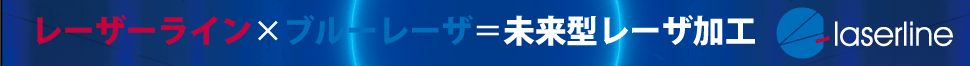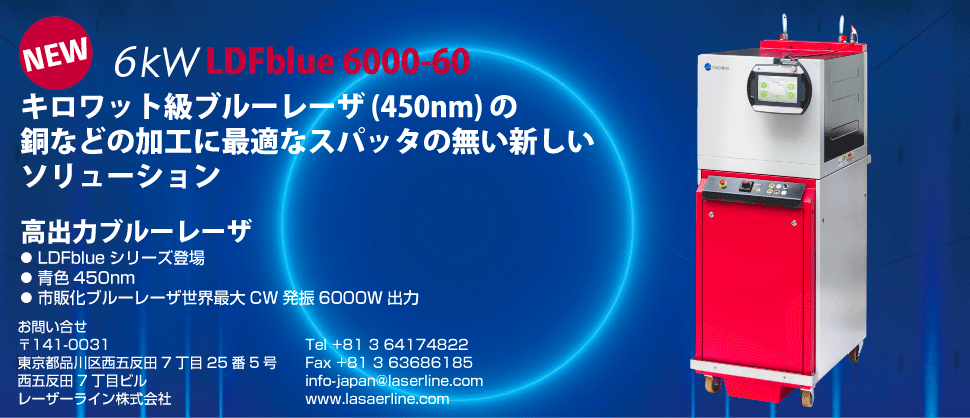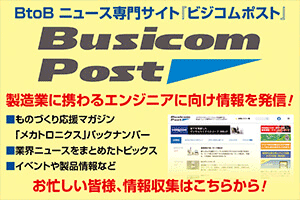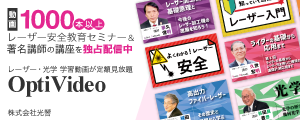Science/Research 詳細
地震計を使わないで地震を超高密に観測する―光ファイバセンシング技術

May, 21, 2025, 京都--京都大学船曵祐輝 理学研究科博士課程学生、宮澤理稔 防災研究所教授らの研究グループは、光ファイバセンシング技術を用いて京都府南部で発生した地震を捉え、次世代型の地震観測の有効性を実証した。
光ファイバセンシングの一つ、分散型音響センシング(DAS)では、一本の光ファイバケーブルのどこで、どのくらいの伸縮があったかを、高精度に測定できる。研究グループは地震観測を目的に、この技術を京都の国道沿いに敷設されている約50kmの光ファイバケーブルに対して用いた。従来の地震観測では、観測装置を一つ一つ地表に設置するという大変な労力が必要だった。しかしこの技術では、既設の光ファイバケーブルの端に装置を取り付けるだけで、ケーブル沿いの約1万か所もの場所で、地震の揺れを捉える事ができた。さらに地震波の振幅に関する大量のデータを活用し、小地震の発生過程を求めることに、世界で初めて成功した。これにより地震計を使わなくても、地震に関する観測研究が進められることを実証した。
現在、光ファイバケーブルは日本中や海底に張り巡らされているため、このDAS技術を使えば、従来の地震観測網を観測点数で凌駕し、より詳細に地震現象を調べられるようになる可能性を秘めている。
研究成果は、2025年5月3日に、国際学術誌「Geophysical Research Letters」にオンライン掲載された。
研究者のコメント
「私がDASを用いた研究を開始したのは修士課程からです。DASは新たな観測技術であり、地震学分野におけるブレイクスルーを担うことが期待される一方、DAS記録を用いた地震波解析は発展途上にあります。そのため、まず着手したのは、観測記録の扱い方の模索でした。その後、様々な試行錯誤の末、DAS記録の特性を活かした発震機構推定手法の開発に至りました。現象を『見る』手段が変われば、問いの立て方も変わります。今後もDASがもたらす新たな視点で、地震の理解を深めていきたいと考えています。」(船曵祐輝)
(詳細は、https://www.kyoto-u.ac.jp)