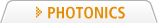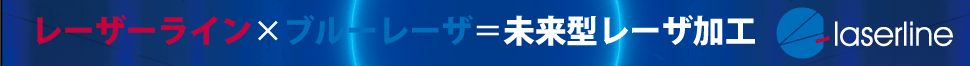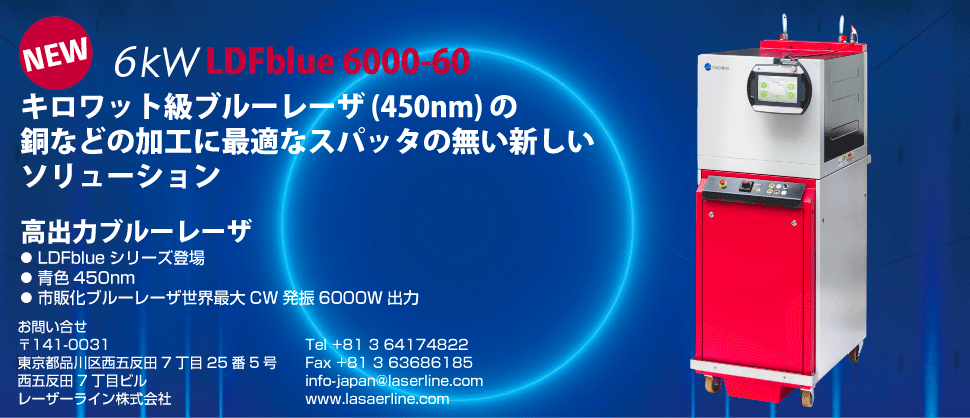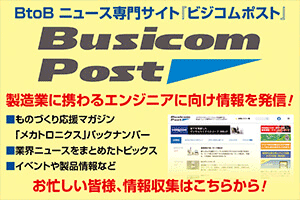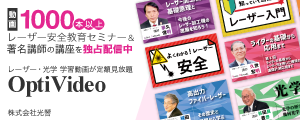Science/Research 詳細
飛行ロボット、建設の新たな地平を開く

May, 8, 2025, Lausanne--EmpaとEPFLの研究者が率いる国際チームは、将来、空中ロボットが建設資材を空中で正確に処理する方法を模索した。このアプローチは、アクセスが困難な場所や高所での作業に大きな可能性を秘めている。飛行ロボットは、地上の既存のシステムを置き換えることを意図したものではなく、修理や災害地域などで的を絞った方法でそれらを補完することを目的としている。
ロボットアームと3Dプリンティングガントリーは、すでに建設現場で見つけることができるが、ほとんどが重く、地面に恒久的に設置されたシステムである。起伏の多い地形や高所では、すぐに限界に達する。そこで、Empaのサステナビリティロボティクス研究所とEPFLの研究者が率いるチームは、将来、空中ロボットを自律型建設プラットフォームとしてどのように使用できるかを調査した。
Science Roboticsの最新号のカバーストーリーでは、研究者がこの今後のテクノロジーの最先端と可能性を示している。建設用ドローンは、山、屋上、災害地域、さらには遠く離れた惑星など、従来の機械ではアクセスできない場所に到達できるという利点は明らかである。また、固定された建設現場を必要とせず、群れで展開できるため、高度な柔軟性とスケーラビリティの容易さが得られる。同時に、輸送ルートを短縮し、材料消費を削減し、建設現場をより安全にすることができる。
極端な状況での修理と操作
空中ロボットは、従来の車両が通行できなくなった浸水や破壊された地域など、災害救援活動に特に適している。空中ロボットは、建築資材を輸送し、自律的に緊急避難所を建設することができる。また、アクセスが困難な場所での修理にも活用が期待されている。それらは、足場を組むことなく、高層ビルのファサードや橋の亀裂を自律的に検出して修理することができた。「地上の既存のロボットシステムは、多くの場合、数トンの重量があり、セットアップに時間がかかり、作業半径が限られている」と、EmpaとEPFLのSustainability Robotics Laboratoryの主執筆者であるYusuf Furkan Kayaは説明している。「一方、建設用ドローンは軽量で、機動性があり、柔軟性に優れている。しかし、これまでのところ、技術レベルが低い状態でしか存在していない。それらはまだ産業目的で使用されていない。」
実際、個々の建築要素の配置やケーブル構造の張力調整から、建築材料の層ごとのプリンティングまで、空中建設のさ様々な方法を実証する学術的なプロトタイプがすでに数多くある。例えば、Empaでは、飛行ロボットがチームとして協力して、構造物の建設や修理のための材料を層ごとにプリントするようにプログラムされている。
技術、素材、デザインの相互作用
ドローンの可能性はディスラプティブである – エネルギー供給と物資輸送が保証されれば、理論的にはどこにでも飛んで構築することができる。また、災害時には、数百台の空中ロボットが遠隔地に一時的なインフラをすぐに設置することができる。
同時に、ドローンによる将来の建設は新たな課題に直面している。研究者によると、主なハードルは技術の学際的な性質である:空中積層造形(Aerial AM)は、ロボット工学、材料科学、建築の3つの分野で同時に進歩する必要がある。EmpaとEPFLのサステナビリティロボティクス研究所の責任者であるMirko Kovacは、この相互作用を次のように説明している。「ドローンは、正確に飛ぶことができるかも知れないが、軽量で、安定した加工可能な材料なしでは、それは最大の可能性を発揮できない。たとえ両方が利用できたとしても、耐荷重構造を可能にするには、建物設計を空中ロボットの限られた精度に適合させる必要がある。」
既存のロボットを補完する
この学際的な調整に加えて、ロボティクスには、飛行時間の制限、ペイロード、自律性など、他の技術的なハードルがある。したがって、この研究では、ルートに沿った単純な飛行から、空中ロボットが建設環境を分析し、エラーを検出し、さらには設計をリアルタイムで適応させることができる完全な独立まで、5段階で自律性のフレームワークを提示している。Yusuf Furkan Kayaによると、これは理論モデルであるだけでなく、明確な開発計画でもある。「われわれの目標は、どのような材料でどのような環境で建設しているのかを理解し、建設中に結果として得られる構造をインテリジェントに最適化する空中ロボットを持つことである」
当座、Aerial AMは既存の地上ロボットシステムを補完するソリューションであり続ける。現在、ドローンのエネルギー消費量は8倍から10倍も高く、その建設量も限られている。したがって、研究チームは、従来システムが構造物の下部領域を構築するのに対し、ドローンは特定の高さから引き継ぎ、柔軟性と範囲という強みをそこで発揮するという組み合わせたアプローチを推奨している。