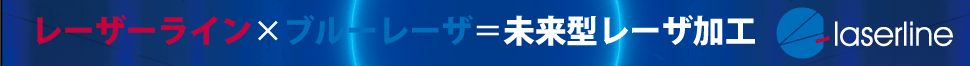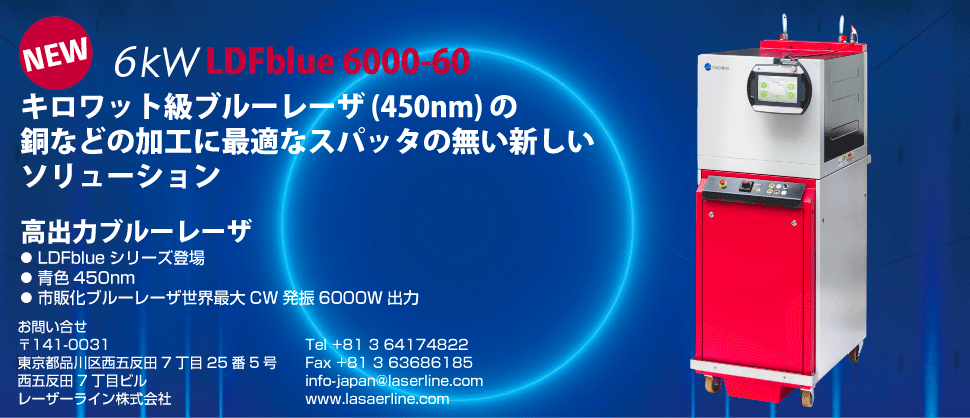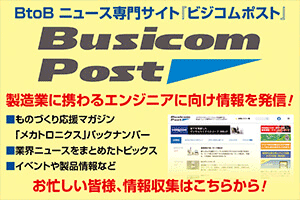Science/Research 詳細
光の「負」の屈折が格子状に並ぶ原子によって可能に

February, 27, 2025, 東京--日本電信電話株式会社(NTT)と英国ランカスター大学(Lancaster University)は、大規模シミュレータを構築することで、格子状に配列した原子の協調応答が、光学迷彩や回折限界を超えるレンズなどの技術に繋がる「光の負の屈折現象」を引き起こすことを見出した。
これまで、光の負の屈折現象を引き起こすためには、人工物質である「メタマテリアル」が必要だと考えられてきた。しかし、メタマテリアルは、光に対する散逸の大きさや製造上の欠陥に悩まされている。それに対し、正確に構造化でき容易に調整可能な格子状の原子は、光の吸収損失を持たず、光と物質の相互作用の高度な制御も可能なため、負屈折のもたらす革新的応用の早期実現へと繋がることに期待できる。
研究成果は、2025年2月12日(英国時間)に英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。
研究の詳細
この新しいアプローチでは、最先端の実験でみられるように、レーザを用いて、完全に秩序化した「結晶」のように整列させられる原子を利用する。ここでは、各原子が放射と吸収の両方を可能とする振動電気双極子として機能する。近接して配置された原子は、それらが放射する光を介して互いに強く相互作用するため、集団的な光学応答を引き起こす。格子と入射するレーザを調整することで、これら原子の累積放射によって、光の負の屈折を実現することができる。
今回、原子が入射光によってどのように励起され、どのように光を放射するかを含め、レーザ光に対する原子の応答を正確に予測する大規模シミュレータを構築した。これは、光によって誘起される全ての原子間相互作用を正確に取り込んで、そこで起きる現象を微視的に記述するものである。このようなシミュレータを用いて、原子媒質中の光ビームの伝搬を解析し、広範なビームや格子構成に対し、その媒質が負の屈折現象を示すことを発見した。これは、様々な条件下で光の負屈折現象が実現し、制御されたアナログプラットフォーム上で光の負屈折の研究が可能であることを示している。











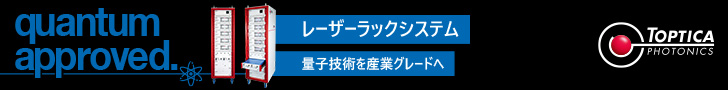
 レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。
レーザ・光関連製品Webガイド レーザ、オプトエレクトロニクスの最新製品をご紹介します。