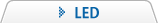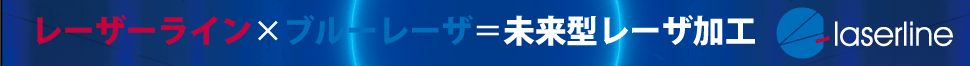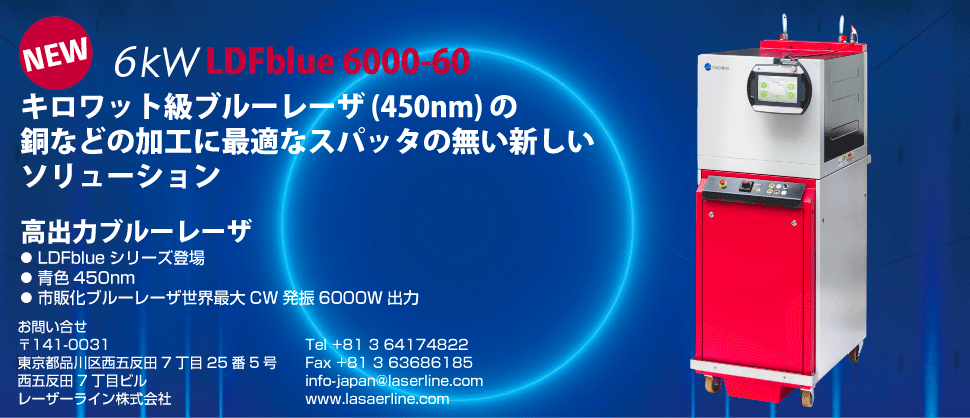Science/Research 詳細
固体タンパク質が蛍光タンパク質ベースのレーザ強度を最大化

December, 16, 2014, Boston--生きた細胞をベースにしたレーザを初めて開発した同じ研究チームが、溶液ではなく固体形状の蛍光タンパク質を用いると光強度が強くなること、タンパク質分子の発光部分を取り囲む自然のタンパク質構造を利用する成果をNature Communicationsで報告している。
研究チームは、マサチューセッツ総合病院光療法ウエルマンセンタ(Wellman Center for Photomedicine)のSeok Hyun Yun, PhDと、UKセントアンドルーズ大学(University of St. Andrews)、Malte Gather, PhD。
両研究者は、2011年に遺伝子工学で造った単細胞を使って緑色蛍光タンパク質(GFP)を発現させ、フォトンを増幅してレーザ短パルスとする論文をNature Photonicsに発表した。生きた細胞内では、蛍光タンパク質分子は水分子と他のタンパク質で囲まれているので、その濃度には限界がある。現在の研究は、固体の蛍光タンパク質をベースにしたレーザの開発を研究するように計画されていた。固体なら、他のデバイスへの組み込みが容易になる。
実際に発光する蛍光タンパク質分子の部分、つまり蛍光体は、円筒状のタンパク質構造に封入されており、隣接分子の蛍光体が相互に近づきすぎないようにしている。近づきすぎると、光の量が、いわゆるクエンチング現象で減少する。この構造的特徴が自然生成的な蛍光タンパク質のクエンチングを、たとえ最高濃度でも、阻止するという仮定を調べるために、研究チームは様々な濃度のGFP溶液、および乾いたGFP薄膜によって放出される光の強度を計測した。さらにこれらの結果を人工の蛍光染料によって生成された光と比較した。
濃度が低いところで、GFPと染料の両方のレベルを上げると蛍光は増えるが、あるポイントで人工染料から放出される光の量が落ち込み、最終的に染料の固体形態から光が検出できなくなった。対照的に、GFPの蛍光はより高い濃度では継続的に強くなり、固体形態で最大輝度が達成された。これは、GFP蛍光体と他の自然タンパク質がクエンチングを免れるという理論をサポートするものである、と研究チームは説明している。
GFPの固体形状が最高輝度の光を発するというこの証拠により、研究チームは、乾いたGFPの薄膜を2つの高反射ミラーで挟んだレーザデバイスを初めて作製した。溶液中のGFPのより低い濃度を利用するデバイスと比較すると、固体GFPレーザは発振するための励起エネルギーは10倍少なくて済んだ。
もう1つ別のでバスは、「コーヒーリング効果」を利用した。この効果では、溶液に溶けた物質が乾いたときに滴の端にリング状に堆積する。研究チームの実験は、蛍光タンパクの乾いた滴によって形成された微小リング内のタンパク質分子によって放出される光が増幅され、リングを周回することが明らかになった。つまり、レーザ光が生成された。異なるタイプの蛍光タンパクのリングを近接させるとマルチカラーレーザ発振が得られた。タンパク質リングの環境湿度の変化が発光強度を変えるので、この効果をベースにしたデバイスはセンサとして使える、と研究チームは説明している。
「このGFPリングレーザは、すべてタンパク質でできた初めてのレーザである。将来、生体適合レーザを身体や組織に埋め込んで、分子や物理的環境の光センシング、細胞の刺激、あるいは感光性薬剤の活性化が可能になるかも知れない」とYun氏はコメントしている。