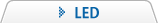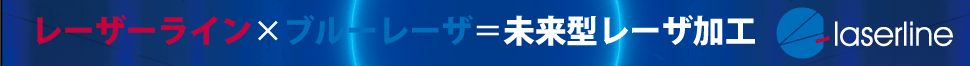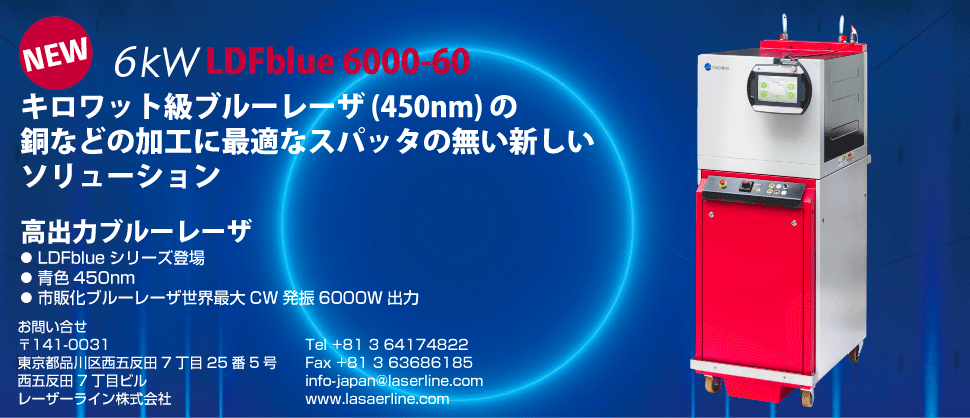Science/Research 詳細
量子科学技術研究開発機構、世界最短波長「超蛍光」の観測

January, 9, 2019, 東京--量子科学技術研究開発機構(量研)量子ビーム科学研究部門関西光科学研究所のハリーズ・ジェームズ上席研究員、大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所(分子研)の岩山洋士助教・繁政英治技術課長、理化学研究所(理研)の久間晋研究員、上智大学の東善郎教授を中心とする研究グループは、X線自由電子レーザー1)(XFEL)施設「SACLA」を用いて、世界最短波長の「超蛍光」の観測に成功した。
原子が光を吸収してエネルギーの高い状態になることを原子が励起されると言う。一方、この状態からエネルギーの低い状態に移る変化が脱励起。超蛍光とは、励起された多数の原子が協調して脱励起するときに出てくる光のことで、その実現にはいくつかの条件が存在するが、特に重要なのは、励起された原子集団の原子間距離が、超蛍光の波長と同程度でなければいけないことである。そのため、波長が短いほど、高い密度の試料と、多くの原子を励起できる強力な光が必要になるので実現が難しく、可視光領域では古くから知られていたものの、これまで可視光より短い波長での報告はなかった。
研究グループは、今回の実験のために、試料であるヘリウムガスを従来に比べて一桁以上高い密度で供給できる、高密度ガスセルを独自に開発した。この高密度ガスセルを用いて、SACLAの軟X線ビームラインの波長24.3nmの極めて明るいFEL光を高密度のヘリウムガスに照射した。その結果、可視光領域(今回は469 nm)に加え、より波長の短い、VUV(真空紫外)領域(164 nm)およびEUV(極端紫外)領域(30.4 nm)においても、高強度・かつ高指向性の発光が観測された。これらの発光の出射角度や強度の時間変化は、この発光が超蛍光である可能性が高いことを示唆するものである。さらに、日本原子力研究開発機構の大型計算機を利用した高度な数値計算によって、観測された発光が2段階的な超蛍光(469 nm、164nm)と、励起光のコヒーレンス性に関連性が高い、いわゆる「ヨーク」超蛍光(30.4 nm)に由来することが裏付けられた。
今回の成果は、60年以上の歴史を持つ現象、超蛍光を従来の可視光領域より一桁短い波長領域で実現したもので、量子光学の分野において学術的意義の高い成果であるとともに、将来的には強力なコヒーレント光源として、化学反応制御への応用につながるものと期待でき。
この研究成果は、「Physical Review Letters」誌に発表された。
(詳細は、http://www.qst.go.jp)