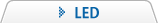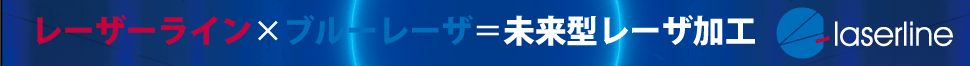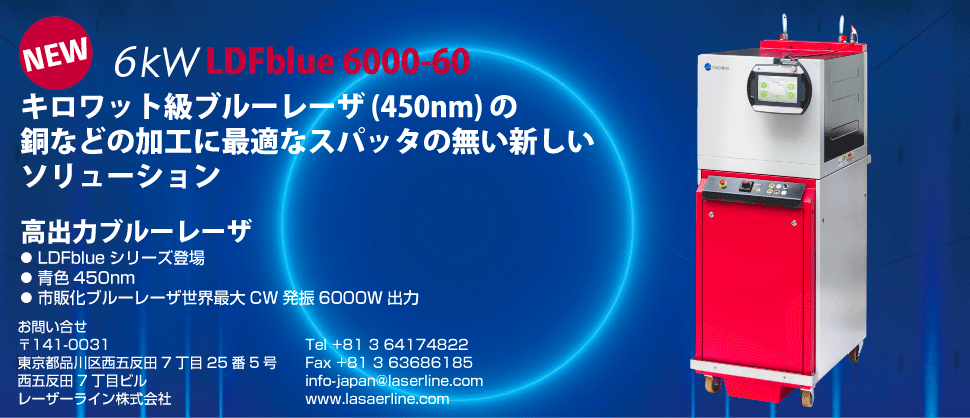Science/Research 詳細
グラフェンp-n接合を用いた電子のビームスプリッタ動作の原理実証に世界で初めて成功
September, 8, 2015, 東京--日本電信電話(NTT)は、CEA Saclayと共同で、グラフェンp-n接合※2を用いた電子のビームスプリッタ動作の原理実証に世界で初めて成功した。量子光学の実験に必要な基本素子であるビームスプリッタが実現できたことで、グラフェンを用いた電子の量子光学研究が可能となる。
グラフェンは電子のコヒーレンス長が長く電子の量子光学実験に有用な材料と考えられているが、量子光学の実験に必要な基本素子であるビームスプリッタを作製するのが困難であるとされてきた。共同研究グループはグラフェンp-n接合が電子のビームスプリッタとして動作することを提案し、層数均一性が高く伝導特性が良いグラフェンを大面積で生成する技術を利用して原理実証を行った。このビームスプリッタとグラフェンにおける長いコヒーレンス長を利用することにより、これまで不可能だった複雑な干渉計の作製等が可能となるなど、電子の量子光学研究が大きく加速する。これにより、光子にはない電子間相互作用が電子のコヒーレンス損失に与える影響の評価や量子もつれ生成が実現され、固体中の量子情報伝達・処理が発展することが期待される。
NTT物性研とCEA Saclayは、グラフェンにおいてp-n接合を用いた電子のビームスプリッタを提案し、その原理実証に世界で初めて成功した。グラフェンのp-n接合では、n領域とp領域の電流チャネルが混成し、例えばn領域から入射された電子はp-n接合中でn領域とp領域のエッジチャンネルに等確率で分配され、その出口で分岐する。この分配と分岐プロセスをビームスプリッタとして提案した。
また、ビームスプリッタとしての動作を確認するため、電流のノイズ(ショットノイズ※10)を計測した。ビームスプリッタとして動作する場合、p-n接合に入射された電子はランダムにn領域とp領域のエッジチャンネルに分配され、ショットノイズが発生する。実験では、p-n接合が短い時、ビームスプリッタとして振る舞う場合に予想される大きさのショットノイズが観測され、p-n接合を長くしていくとその大きさが小さくなっていった。この結果から、p-n接合における量子性損失の目安となるエネルギー緩和長は15 µmであることが求められ、15 µmより十分短いp-n接合はビームスプリッタとして動作することが実証された。