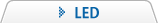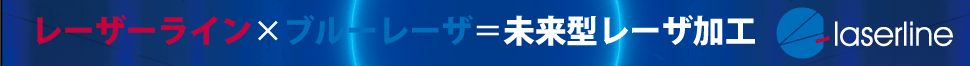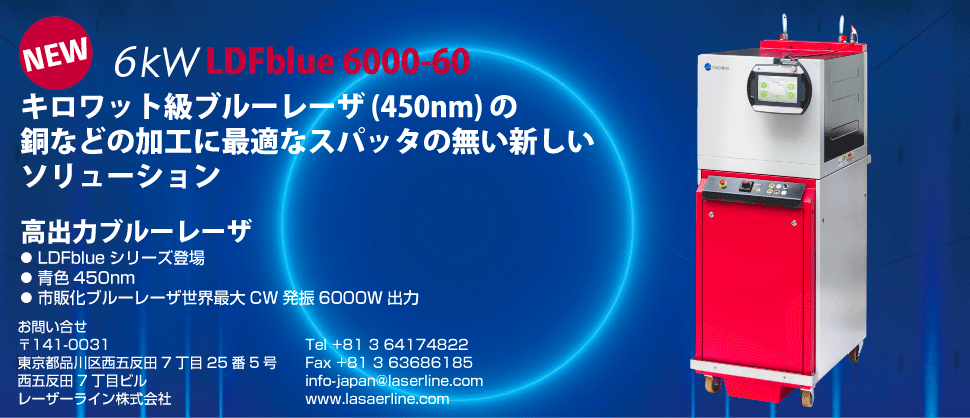Science/Research 詳細
従来の解像度限界を超える顕微鏡、分子の高速コ・トラッキング

February, 29, 2024, Munich--LMU (Ludwig Maximilian University of Munich)の研究チームは、複数の分子の急速な動的プロセスを分子スケールで同時に追跡する革新的な方法を開発した。
われわれの体内のプロセスは、タンパク質やDNAなどの様々な生体分子の相互作用によって特徴付けられている。これらのプロセスは、多くの場合、わずか数ナノメートルの範囲で発生する。その結果、回折により分解能が200nm程度の限界がある蛍光顕微鏡では観察できない。生体分子の2つの色素マーキング位置がこの光学的限界よりも近い場合、それらの蛍光は顕微鏡下で区別できない。この蛍光は局在化に利用されるため、正確な位置決定が不可能になる。
この分解能の限界は、従来、超解像顕微鏡法では、色素を点滅させ、蛍光のオンとオフを切り替えることで克服されてきた。これにより、蛍光が時間的に分離され、識別可能になり、従来の分解能限界を下回る局在化が可能になる。とは言え、迅速な動的プロセスの研究を伴うアプリケーションの場合、このトリックには重大な欠点がある:つまり、点滅は複数の色素の同時局在化を妨げる。これにより、複数の生体分子が関与する動的プロセスを調査する際の時間分解能が大幅に低下するのである。
LMUの化学者Philip Tinnefeld教授主導により、Fernando Stefani教授(ブエノスアイレス)と協力して、LMUの研究者は、この問題に対処するための洗練されたアプローチpMINFLUXマルチプレックスを開発した。研究チームは先頃、この手法に関する論文を学術誌「Nature Photonics」に発表した。
MINFLUXは超解像顕微鏡法で、わずか1nmの精度で局在化が可能である。従来のMINFLUXとは対照的に、pMINFLUXは、レーザパルスによる色素の励起とその後の蛍光の間の時間差をサブナノ秒の分解能で記録する。これにより、色素の局在化に加えて、蛍光の別の基本的な特性である蛍光寿命に関する洞察が得られる。これは、色素分子が励起されてから蛍光を発するのに平均してかかる時間を表す。
「蛍光寿命は、使用する色素によって異なる」と、論文の共同筆頭著者Fiona Coleは説明している。
「われわれは、異なる色素を使用した場合の蛍光寿命の違いを利用して、まばたきを必要とせずに発光する色素に蛍光光子を割り当て、その結果、時間的分離を実現した」
この目的のために、研究チームは局在化アルゴリズムを適応させ、必要な分離を達成するための多指数近似モデルを含めた。
「これにより、複数の色素の位置を同時に決定し、複数の分子間の高速動的プロセスをナノメートルの精度で調べることができた」と、共同筆頭著者Jonas Zähringerは付け加えている。
研究チームは、DNAオリガミナノ構造上の異なる位置間をジャンプする2本のDNA鎖を正確に追跡し、DNAオリガミナノ構造の並進運動と回転運動を分離し、抗体の抗原結合部位間の距離を測定することで、この方法を実証した。
「しかし、これはほんの始まりに過ぎない。高い時間分解能と空間分解能を持つpMINFLUXマルチプレックスは、将来、タンパク質の相互作用やその他の生命現象に新たな知見をもたらすと確信している」とPhilip Tinnefeldは、コメントしている。