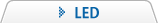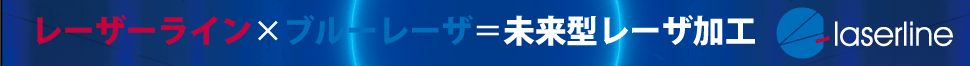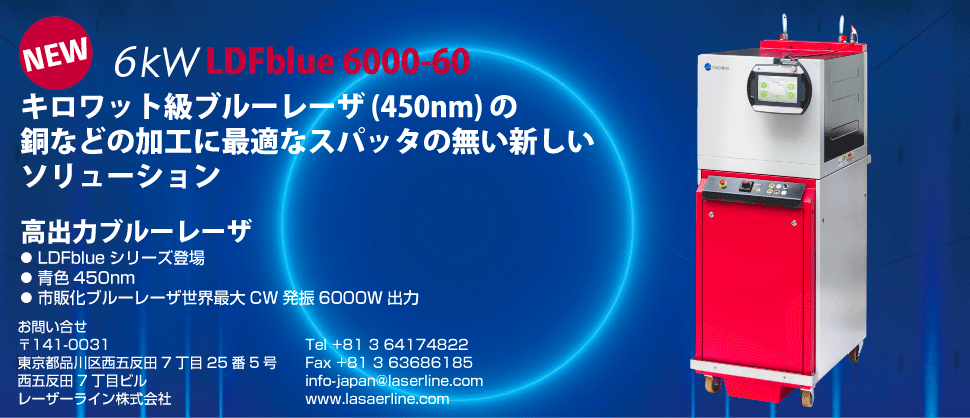国内リポート 詳細
羽ばたく大学・国研発ベンチャー
第81回応用物理学会秋季学術講演会でフォトニクス分科会がオンライン・シンポジウムを企画

September, 17, 2020, 東京--9月8日(火)から11日(金)までの4日間、オンライン開催された第81回応用物理学会(応物)秋季学術講演会の初日、フォトニクス分科会(幹事長:栗村直氏〈物質・材料研〉、写真:1月撮影)企画によるシンポジウム「フォトニクスが生み出すイノベーションと新産業創出Ⅲ:羽ばたく大学・国研発ベンチャー」がオンラインにて開催された。
プログラム
フォトニクス技術は、ベンチャー企業設立数の多い分野の一つであり、これまでにも計測、映像、検査などにおいて様々な産業を創出してきた。今回のシンポジウムでは、大学・国研発でフォトニクス技術を事業化に結びつけたパイフォトニクス、パリティ・イノベーションズ、フォトニックラティス、ライトタッチテクノロジー、光響、フォトンラボの6社によって、研究から事業化までの貴重な経験が語られた。
シンポジウム冒頭の「OPENING REMARKS」で幹事長の栗村氏は、本シンポジウムはもともと産業界と学術界のブリッジになりたいとの趣旨で企画されたもので、これまで開催された2回が何れも好評を博したことを受け、今回の第3回を企画したと説明した。以下、各講演概要を紹介していく。
◆光パターン形成LED照明「ホロライト」とその応用:池田貴裕氏(パイフォトニクス:代表取締役)
同社は、2006年に設立された光産業創成大発ベンチャー企業、社員数は現在33名。池田氏は徳島大在学中にホログラフィと出会い、その後、浜松ホトニクスに入社、ホログラムゴーグルの研究開発に携わった。在職中MITに留学して、ホログラフィック顕微鏡の研究にも従事。帰国後、光産業創成大に入学して、在学中同社を設立した。
同社の「ホロライト」は、もともとホログラムを高品質に再生することを目的に開発されたLED照明装置で、太陽光線と同程度の疑似並行光を発生できる。開発のきっかけは、光産業創成大で開催されたホログラフィックディスプレイ研究会において「LEDを使った照明装置があれば」という要望に応えるため開発を引き受けたことだったという。
2007年に開発された「ホロライト」は、遠方に鮮明な光のラインを形成する光パターン形成LED照明装置へと進化を遂げ、今では検査、演出、建築、道路、安全、芸術、実験など、様々な業界で使用されている。レンズの種類によって光の形状を自在に変えることができ、直線型、円環型、矢印型、円弧型などの照明が可能な製品がラインアップされている。
池田氏は、起業家精神を得るには経験が必要で、それは新しいことへのチャレンジで得られると述べた。そこで成功と失敗を繰り返し、得られた経験を次のチャレンジに繋げていく。その過程で自分自身のオリジナル要素が生まれ、経験を何回も経ることで新しいことにチャレンジする怖さが無くなってくると指摘した。さらに、起業実践を通して様々な業界のプロフェッショナルとの出会いが、応用を拡げる上でとても重要であったとも述べた。
質疑応答で「一番苦労した時期は?」と訊かれた池田氏は、「(常に)今が一番苦労している。でも伸びて行くには、どんどん苦労して行くしかない。苦労しないと次のステージには行けない」と語るとともに「勝ったと思わないこと。常に負けていると思って頑張らないといけない」と述べていた。
◆2面コーナーリフレクタアレイによる空中映像表示と非接触ユーザーインターフェースへの応用:前田有希氏(パリティ・イノベーションズ:取締役研究開発部長)
同社はNICT(情報通信研究機構)からスピンアウトしたベンチャー企業で、従業員数は9名。「SF・ファンタジー世界の表現が当たり前に存在する生活空間をつくる」をミッションに掲げる。講演では、2面コーナーリフレクタアレイ(DCRA:Dihedral Corner Reflector Array)と非接触ユーザーインターフェースへの応用に関する取り組みが紹介された。
2000年代、NICTで研究開発が進められた超臨場感コミュニケーション技術の要素技術の一つが立体映像であった。当時の立体映像に関する研究は視差方式が主流。しかし研究員の前川聡氏(同社・代表取締役)は、従来とは異なる平面鏡をベースにした結像素子(固有焦点距離がなく、等倍で面対称位置に結像する光学素子)を用いた立体映像方式を発案、研究開発を進め事業化のため2010年、同社を創業した。
2013年には量産向けの100mm角の試作に成功、2015年には空中スイッチと空中タッチディスプレイキットを試作開発、その後150mm角、300mm角の製造にも成功した。NICTとは独占的通常実施権を締結して、量産化・事業化を進めているという。2017年と2020年には、経産省の戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)にも採択されている。
前田氏は、DCRAは面内再帰反射に基づく結像光学素子であり、面対称位置への空中映像表示が可能なので、指の位置を検出するセンサと組み合わせて非接触ユーザーインターフェースに適用することができ、新型コロナウィルスのような感染症対策にも活用できるのではと述べていた。
◆フォトニック結晶と偏光計測技術:佐藤尚氏(フォトニックラティス:代表取締役社長)
同社は、東北大の川上彰二郎氏によって発案された自己クローニング型フォトニック結晶とその応用製品を開発・製造・販売する東北大発ベンチャー企業、社員数は22名(役員含む)だ。2000年に科学技術振興事業団(現・科学技術振興機構:JST)の起業支援プログラム・新規事業志向型研究開発成果展開事業(後のプレベンチャー事業)を獲得、2年後の2002年、川上氏等によって創業された。
フォトニック結晶は、構造の規則性を人工的に作る技術。場所を選んで規則性を自由に制御することができ、偏光の面分布を自由に制御できる。ところが、その実現方法が実用化のボトルネックになっていた。1997年、川上氏はより実用的なフォトニック結晶の製造方法として、自己クローニング法を提案した。それは、周期的な凹凸を形成したガラスの基板の上に屈折率の異なる材料を交互に積み重ねていくという極めてシンプルな方法だった。一般的な成膜技術では凹凸の上に膜を付けても、凹凸がすぐ埋まってしまう。しかし自己クローニング法では、一定の角度の斜面を持つ周期構造が安定して形成される。自らの形を複製していくようにプロセスが進むので、この方法は「自己クローニング法」と名付けられた。
シンプルで安定した製法のため量産にも適しており、基板を変えるだけで同一プロセスにより様々な光学素子の作製が可能だ。今では、特徴的な偏光子や波長板として光通信を始め、様々な市場において実用化されている。撮像センサとアレイ状フォトニック結晶を組み合わせた偏光イメージングセンサは、2次元偏光分布のリアルタイム観察が可能で、特に透明材料の複屈折計測機に展開され、開発用途から製造現場において活用されている。
講演では応用機器の市場展開についても紹介され、佐藤氏はフォトニック結晶素子の産業部材としての活用と計測システム・モジュールの製造現場での活用を一層進めるとともに、海外市場への展開を図り、事業拡大を目指して行きたいと述べた。また、「起業に際してリスクを意識しなかったか」という質問に対しては「リスクよりもフォトニック結晶の将来性の方が優っていた」と答えていた。
◆中赤外レーザーを用いた非侵襲血糖値センサーの事業化:山川考一氏(ライトタッチテクノロジー:代表取締役)
同社はQST(量子科学技術研究開発機構)認定第1号のベンチャー企業。従業員数は8名(役員含む)で、中赤外線レーザを用いた世界初の非侵襲血糖値センサの開発・事業化を進めている。
山川氏は日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)に入所して最先端レーザ技術の研究開発に従事、2016年からはQSTの量子ビーム科学研究部門レーザー医療応用研究グループに在籍、2017年に同社を創業した。
これまでにJSTの研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)や大学発新産業創出拠点プロジェクト(START)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のシード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援を受け、今年度は日本医療研究開発機構(AMED)の医工連携イノベーション推進事業(開発・事業化事業)にも採択された。
糖尿病患者は国内だけでも1,000万人、世界では4億2,500万人に達し、2045年には6億人を超えると予想されている。これら糖尿病患者は血糖値測定のため1日4~5回、痛みを伴いながら採血用の針を体に打ち続けなければならない。自身の体でインスリンを作ることができない1型糖尿病患者に至っては、インスリン注射を含め年間3,000本もの針を打つ必要があるという。使用した針は感染性廃棄物として処理しなければならず、国内の糖尿病関連医療費は年間1兆2,000億円を超える。
同社は、採血による日々の苦痛や精神的ストレスから患者を解放するため、中赤外線レーザを用いて病院から一般家庭まで広く普及できる非侵襲血糖値センサの事業化を進めており、2022年の上市を目指している。その仕組みは、中赤外レーザ光を指先に照射すると光の粒子の一部はグルコース分子に吸収され、吸収されなかった光の粒子は皮膚などで反射され、これを検出器で検出して入射光と反射光の差分を血糖値として算出するというもの。指先を光にかざすだけ、約5秒で測定できる。
開発を応援しようと、糖尿病患者とその家族を支援するNPO法人がクラウドファンディングを立ち上げ、1,100人を超える人々によって目標金額2,500万円を超える資金が調達できたという。山川氏は、プロト機から量産機に落とし込むまでのハードルは高かったが、今その山を越えようとしているところだと述べていた。
◆レーザー業界のプラットフォーム形成:住村和彦氏(光響:代表取締役)
住村氏は同志社大、阪大を経て、2009年に個人発ベンチャー企業として同社を起業した。起業後には京大でMBAも取得している。現在の従業員は25名だ。
住村氏はレーザ業界にとって不可欠な基盤となる、潰れにくいインフラ・プラットフォームをヒト、モノ、情報という括りで形成しようと事業展開している。講演では、プラットフォーム形成でオープンイノベーションを実行するとともに、レーザ技術革命の促進を支援していくための諸活動が紹介された。
組織における経営資源にはヒト、モノ、情報、金などがあるが、住村氏が起業を考えた時点ではGoogle、Amazon、FacebookなどがITプラットフォーマーとして支配的地位にあり、経営資源を何れか一つに絞ろうとした場合、すでに手遅れ感があったという。ただし、二つ以上を組み合わせてやればチャンスはありそうで、かつ領域(業界)を特化すればその全てができそうだと考え、光・レーザ業界のプラットフォーマーになろうと決意、レーザ技術革命によって情報・医療・食料・環境・エネルギー革命を促進させ、安心・安全・豊かな社会を構築・貢献するというビジョンを掲げ起業した。
当初は何もない状況だったが、学会論文などの技術情報だけは豊富にあった。そこで光技術情報サイト「Optipedia」を立ち上げ、その後もニュース情報サイト「Optinews」や製品情報サイト「Optishop」を立ち上げた。これらのサイトを通じ、モノについての問い合わせが頻繁に来るようになる。当初は商社経由で製品を購入していたが、その後海外メーカからの直接購入に切り替えることで、素早い対応やレーザが分かる博士等による専門的技術相談の他、業界最安値も実現したとのことだ。
今では問合せが年間3,000~4,000件、世の中にあるモノは既存製品を紹介、ないモノは新規製品を開発するという。新規製品の開発例としては、100万円以下の1μmフェムト秒レーザやレーザマーカ、レーザメスのビームプロファイラ、レーザクリーナなどが挙げられる。
同社のビジネスモデルは「雪だるま式モデル」だ。先ずWeb上で情報が増える。→次にそれを見る人が増える。→モノの問い合わせが増える。→顧客の悩み情報(製品ネタ)が増える。→産・学の協力者が増える。→販売可能な製品数(モノ)が増える。→さらにWeb上で情報が増える。このサイクルで連続増収を続けているという。
研究者は、世界最高レベルの製品を作れば売れるという錯覚に陥りやすい。住村氏は、顧客が欲しいのは製品ではなく、便益なのだと述べる。ビジョン実現のため、レーザの「布教活動」にも力を入れている。攻殻機動隊の作家、アニメ専門学校、声優、デザイナーに加え、エネルギー界のメディアやレーザー学会など、多岐に渡るコラボを実施しているそうだ。住村氏は質問に答える形で「MBAの勉強は有益であり、中でもフレームワークの知識を得たことはビジネスに役立った」と述べていた。
◆最新レーザー技術を利用したインフラ計測のビジネス化:木暮繁氏(フォトンラボ:代表取締役社長)
2017年にSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」の技術成果を社会実装する組織としてスタートした同社は、理研・QST認定のベンチャー企業。従業員数は14名(専属社員4名)で、主な事業はトンネル覆工面計測の画像撮影システムとレーザ打音システムの連携運用システムの普及だ。
国家プロジェクト(国プロ)の研究開発の必須条件が社会実装になりつつある中、講演では研究者が最も不得意とするビジネス化の観点から、技術概要とビジネスモデルおよび研究開発審査会の乗り切り方法、実際の事業化推進の仕組みづくり、さらには製品化・社会実装を紹介、国プロの社会実装という課題解決手法が提示された。
日本のインフラ構造物の約半分は建築後すでに50年以上が経過しており、これらを維持・更新していくには、今後30年で194兆円が必要とも言われている。その維持管理は、現状では人による目視や打音検査で行われているが、コストの削減や予想される専門検査員の不足・高齢化に対応するため、その機械化が強く求められている。
2014年、理研チームが提案した画像およびレーザによるトンネル覆工面の遠隔検査に関する研究開発がSIPに採択された。赤外線パルスレーザをコンクリート表面に照射して振動させ、別のグリーンCWレーザのドップラー効果で振動を計測、そこに存在する欠陥を見つけようというものだ。
当初、SIPは基礎技術の研究を求めていたが、プロジェクト開始の2年目から具体的な製品化と継続的な供給を条件とする社会実装を厳しく要求するようになった。そこで、チームでは企業の事業部戦略立案と、社外との協業マネジメント経験のあるプロの実業家を社会実装担当で採用することを決定、こうして小暮氏がプロジェクトに参画、結果として研究者は審査会での社会実装に関する質疑応答から解放され、研究開発に注力できるようになったという。
チームは社会実装の実行組織としてベンチャー企業の設立を約束し、2017年にフォトンラボが設立された。設立にあたっては、小暮氏を始め研究者と先端計測サービス会社の「計測検査」、さらに特別ルールに基づき金融機関が出資するという形が採られた。
小暮氏は、先進技術ベンチャーの抱える課題に対応し得る人材としては、国研の研究リーダー(開発担当)、実際に活動中の中堅企業代表者(実業務<サービス>担当)、大企業での経営企画経験を持つ技術経営コンサルタント出身者(経営担当)、資金需要と管理を行う金融系人材(資金調達担当)が必要だと述べる。講演では、SIPの研究成果を社会実装するという当初の目的は着実に実行フェーズに移行しているとした上で、国研と連携するベンチャー企業ならではの資本施策の難しさも指摘した。一方、大切なことは「人との信頼感であり、人を見る眼だ」として、事業化・社会実装に関する相談があればアドバイスをしたいとも述べていた。
講演の途中と最後に設けられた質疑応答「総合討論」の中で印象に残ったのは、ベンチャーをやって良かったのは「人間力が高まった」ことや「ファンドからの出資という場で鍛えられた」ことであり、大切なのは「心が折れることが多いので、起業時の理念の芯を強く持っていること」、「人を信じること」、「代表者は楽しさも辛さも知っておくべきである」という講演者の方々の言葉であった。
日本ではベンチャー企業が育ち難いというのが常套句になっているが、だからこそ実際に起業した人達の生の声が聞ける、このような機会は大変貴重であり、意義深いものがある。今後も継続的に開催されることを期待したい。
フォトニックワークショップ
同分科会では12月20日(日)と21日(月)の両日、沖縄・那覇で「光の多様性を探求する!!」と題した第5回フォトニックワークショップを開催する(オンライン開催の可能性あり)。
量子計測、AI、バイオ顕微鏡などの分野の最先端で活躍中の方々による基礎から将来展望までの講演と、光学分野全般を対象としたポスター発表(ショートプレゼン付き)も行われる。学会・研究会デビューを果たしたい、交流の輪を広げたいなどを希望する学生、留学生、若手研究者にフォーカスした企画とのことなので、興味ある方は下記URLを参照していただきたい。https://annex.jsap.or.jp/photonics/event-schedule/201220-1221
(川尻 多加志)