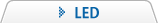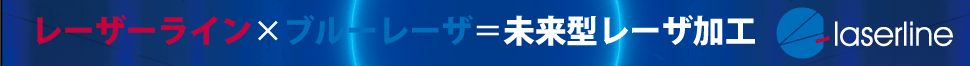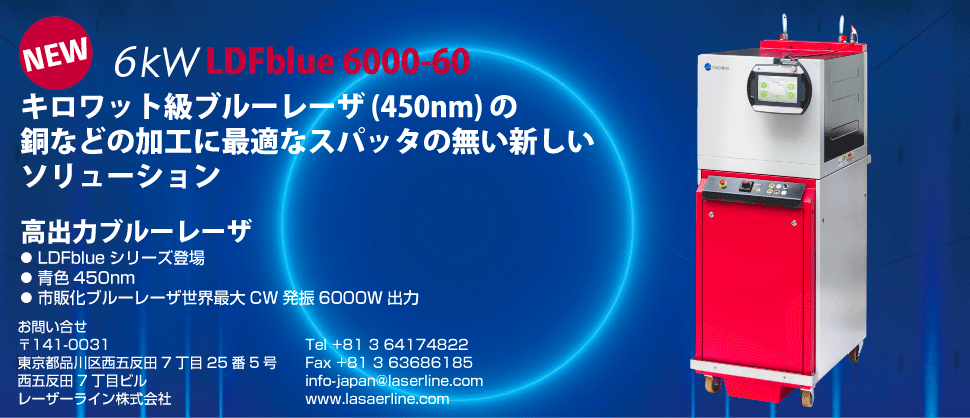国内リポート 詳細
注目が集まる自動運転技術! 早期普及の解は?
自動車・モビリティフォトニクス研究会の平成30年度第1回討論会、開催される

May, 25, 2018, 東京-- 自動運転への注目が集まる中、光産業技術振興協会 自動車・モビリティフォトニクス研究会の平成30年度第1回討論会が5月16日(水)、東京工業大学 キャンパス・イノベーションセンター東京で開催された。
同研究会は、自動車・モビリティフォトニクスに関わる光センシングおよびその処理技術、Human Machine Interface技術、通信技術、ヘッドライト・ブレーキライト等に関連する技術動向および産業動向に関する情報収集及び意見交換を行うとともに、それらの将来展望について産業界の関係者を中心に学官を交え討論することで自動車・モビリティフォトニクスに関わる今後の研究開発の方向付け、産業・社会への具体的な貢献への端緒を創出して行くため、平成29年に設立された。
討論会は代表幹事の西山伸彦氏(東京工業大学:写真)による挨拶からスタート、続いて小木津武樹氏(群馬大学 次世代モビリティ社会実装研究センター)が「自動車の自動運転への取り組み」を講演、橋本尚久氏(産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター)が「ラスト/ファーストマイルのためのモビリティに対する取り組み」、杉原裕明氏(シナノケンシ 開発技術本部新商品開発部)が「遠隔地からのリアルタイム計測・管理を実現する3Dレーザースキャナーシステムの開発」、戸塚弘毅氏(santec 光画像センシングビジネスユニット)が「バイオ・メディカル向け光干渉断層画像測定技術(OCT)とその技術を適用した長距離測距への可能性」について講演を行った。本稿では、国内の大学で最大級の自動運転研究開発施設を持つ群馬大学の小木津氏の講演にスポットライトをあてる。
地域限定・路線限定の自動運転
小木津氏は、従来の自動車は「あらゆる所」に行くことができるのが売りであったために、自動運転にも「あらゆる所」で動作することが求められているが、「あらゆる所」ですべての危険を認識する汎用的なアルゴリズムは難しく、運用環境不定下では100%の安全性を保障することは極めて困難だと指摘した。そこで、同大学では場所を限定して技術的な敷居を低くするとともに、自動運転を「地域の足」として捉え、地域限定・路線限定での早期の社会実装を目標に、レベル4の完全自動運転を技術的に可能にすることを目指している。
具体的には、地方でのドライバー不足が指摘されているバスやタクシーなど、公共交通機関の自動運転化を目標に掲げている。小木津氏は、旅客運送や物流、観光、医療福祉、卸売・小売など、自動運転のユーザーサイドに加え、材料や動力機、センサ、電池、充電システム、道路設備といった自動運転を技術的に支えるサプライヤーサイドを含めた多業種が完全自立型自動運転に対応できるよう、研究センターをいわば自動運転の「よろず相談所」として機能させると述べた。センターの社会実装用自動運転車両保有数は、乗用車の他にバスやトラックなど18台、国内の大学では最多だという。
荒巻キャンパス内には、国内初の完全自動運転総合研究開発施設も新設された。データセンター(サーバー室)や管制室・遠隔操縦室、シミュレーション室、車両整備開発室などを備え、施設は企業に貸し出される予定だ。敷地内には国内大学最大規模の自動運転専用の試験路(6,200m2)も設置され、可動式の信号機や標識も多数用意されている。
公道実証実験は2016年度から行ってきた。人を乗せた自動運転から無人の自動運転へ、白ナンバーから料金の取れる緑ナンバーへ、さらには運用者を大学内から大学外へと、段階的にレベルを上げている。2016年から2021年までは桐生市の公道で、2017年11月から2か月間は神戸市北区筑紫が丘内で実証実験を行い、今年11月には群馬県前橋市において路線バスで実証実験を行う計画だ。
早期普及の現実的な解
若者の車離れに象徴されるように、日本では運転することに価値を見出す人が以前より減少している。高齢化により平均的な運転能力も低下している。過疎地では公共交通機関の弱体化に伴って、生活に必要だから高齢者が無理をして運転する結果、事故も増加しているという。
2本目の講演者である産総研の橋本氏も、公共交通機関の最寄駅から病院といった最終目的地までの「ラスト・ファーストマイル」への自動運転適用を取り上げていたように、今回の討論会では、あらゆる地域で展開する自動運転ではなく、あくまで地域限定・路線限定の自動運転に焦点が当てられた。米国での自動運転車の事故は、公道における運用の難しさを改めて認識させたが、限定された地域であれば周囲の道路状況等、きめ細かい情報が把握できる。それゆえ実現のハードルは相対的に低く、地域限定・路線限定は現実的な対応だと言えよう。
一方、討論会後半の2本では自動車分野以外の応用が取り上げられた。いきなり自動車業界へ参入するには様々な障壁がある。その厳しい現実を考えれば、自動運転へ応用できる技術を持つサプライヤーは、足元のビジネスも忘れてはならないということだろう。
(川尻 多加志)