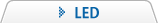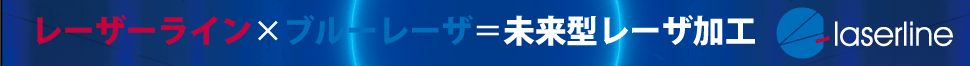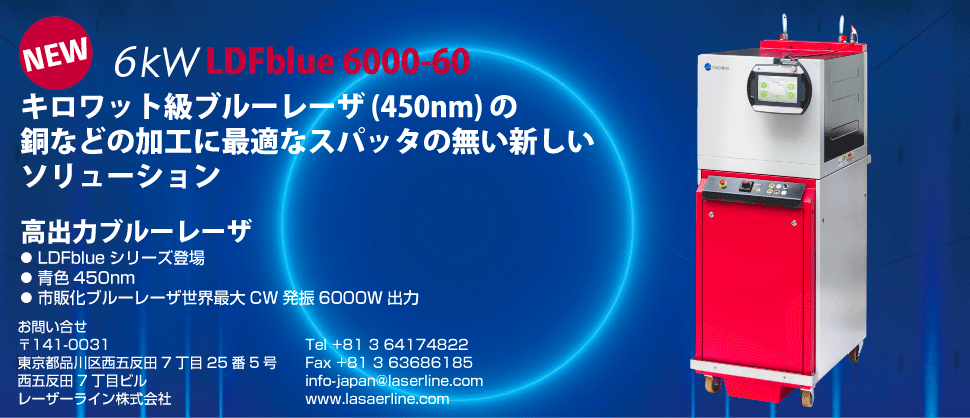国内リポート 詳細
液晶ディスプレイは有機ELディスプレイに勝てるのか
―日本液晶学会設立20周年記念シンポジウム開催―

May, 7, 2018, 東京--日本液晶学会設立20周年記念シンポジウムが4月10日(金)、東京・江戸川区のタワーホール船堀において開催された。同学会の前身にあたる液晶討論会の第一回が開かれたのは1975年10月、約20年の時を経て1997年に日本液晶学会が設立され、2011年には一般社団法人となり、今に至っている。
今回のテーマは「液晶技術が拓くディスプレイの未来 ~液晶ディスプレイの特質と発展性~」。国内の液晶ディスプレイ産業はパネル製造技術の成熟化、製品のコモディティ化、海外メーカーの躍進などによって不透明な状況が続いている。一方で、長く蓄積されてきた部材・駆動技術など高度な専門分野を元に、液晶ディスプレイの機能性・付加価値を高める開発は相次いでいる。シンポジウムは、今後の表示分野を先導する最先端の液晶関連技術と研究開発の発展性を展望する興味深いものであった。
◆液晶技術発展への貢献
第1部「液晶ディスプレイと情報化社会」では3本の講演が行われたが、このうち「液晶ディスプレイの研究開発史と発展への期待」と題して、液晶ディスプレイの発展に貢献してきた東北大学・名誉教授の内田龍男氏(インテリジェント・コスモス研究機構・代表取締役社長)が、その研究を振り返りつつ今後の展望を語った。
内田氏は1970年に東北大学工学部電子工学科を卒業、75年大学院工学研究科博士課程電子工学専攻修了の後、工学博士号を取得して電子工学科助手、82年助教授、89年教授、04年工学研究科副研究科長、06年工学研究科研究科長・工学部長を歴任、仙台高等専門学校校長や国立高等専門学校機構理事なども務めた。この間、科学技術庁長官賞、大河内記念技術賞、市村賞、SID Jan Rejchman Prize、SID Slottow-Owaki Prize、高柳健次郎賞などを受賞している。
内田氏は、当時の半導体の権威、東北大学の和田正信教授の研究室に入り、大学院でも半導体研究を続けようと考えていた。ところが、研究室のテーマの4つのうち3つは半導体、残り1つが液晶で、内田氏はあみだくじで負けて液晶の担当になったそうだ。
液晶ディスプレイの黎明期に研究をスタートさせた内田氏は、電子工学材料としては未開拓の液晶研究に挑戦、高性能カラー液晶ディスプレイなどの実現に貢献した。また、液晶分子の配向機構の解明とその制御手法を確立、実用化の基盤を作り上げた。高性能化に関してもカラー化方式、反射型方式、広視野角・高速液晶ディスプレイ等の研究を行い、その発展に大きく貢献した。特にカラー液晶ディスプレイの研究では、多くの方式を考案・開発、液晶セル内側に赤、緑、青の微細なカラーフィルターを設けた加法混色型フルカラー方式やバックライト無しの超低電力反射型フルカラー方式など、これらは液晶TVやPC、携帯電話など、広く実用化されている。
◆液晶ディスプレイ VS. 有機ELディスプレイ
内田氏は講演の中で、液晶ディスプレイと有機ELディスプレイを比較、トータルの特性では現状、液晶の方が圧倒的に優れているとしつつも、かつてのプラズマディスプレイと液晶ディスプレイの競争の歴史を振り返って、技術とは別に、ある種の時代の流れが動き始めると、情勢は一気に変わってしまうと指摘した。さらに、現状の有機ELは実用ぎりぎりのレベルだが、この後どれだけ有機ELにエネルギーがつぎ込まれるかで将来が決まってくるとした。特に高解像に関しては、液晶が透過方式であるためにTFTや配線が邪魔をして光の透過率が下がってしまうのに対し、有機ELをトップエミッション構造にすれば、光の利用効率を上げることができると指摘。その課題はトップの透明導電膜をどれだけ低温で作れるかだとした。
液晶ディスプレイが絶対的に優位な点は、反射型液晶が持つ超低電力性だ。温度や光、振動などをエネルギー源とした電源不要のディスプレイの実現が期待でき、内田氏は液晶ディスプレイもまだまだ発展の可能性は大きく、流れを変えるようなトピカルな話題づくりによって世界は変えられると述べた。
第1部のあとは、第2部「液晶材料の革新」、第3部「部材技術の先導」、第4部「デバイス技術の進化」、第5部「応用システムの展開」が続き、最新の研究開発事例が紹介されたが、ここから垣間見えたのは日本の産業としての強みがディスプレイそのものから今や材料や部材などにシフトしたということだろう。(川尻 多加志)