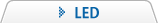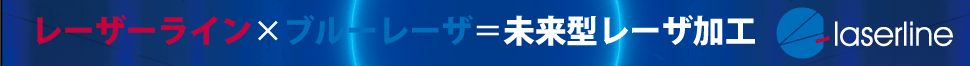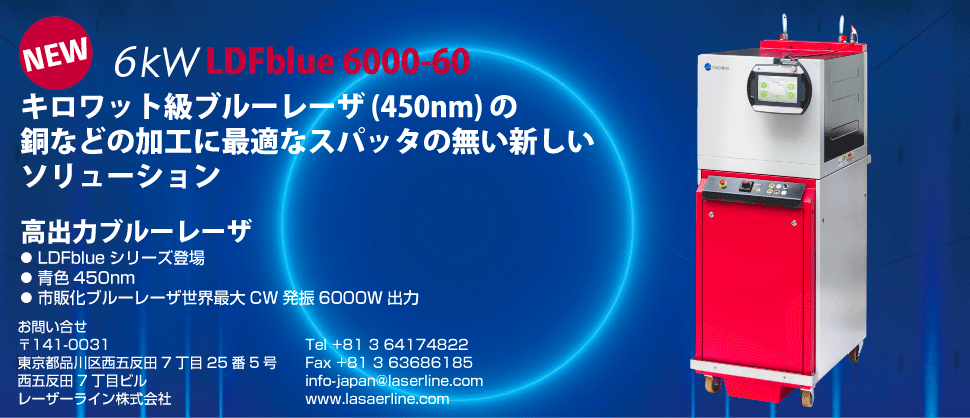国内リポート 詳細
量子ドットとともに
-荒川泰彦教授、最終講義でその研究を振り返る―

April, 20, 2018, 東京--3月19日(月)、東京大学・駒場リサーチキャンパス・コンベンションホールにおいて、東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構長/生産技術研究所光電子融合研究センター長の荒川泰彦教授の最終講義が行われた。荒川教授は講演で38年にわたる自身の研究を振り返りながら、フォトニクス分野にイノベーションをもたらす量子ドット科学技術に対する熱い思いを語った。
荒川教授は1971年愛知県立旭丘高等学校を卒業、75年東京大学工学部電子工学科を卒業して、80年同大学院電気博士課程修了後、生産技術研究所専任講師、81年同研究所助教授、84年カリフォルニア工科大学客員研究員、87年東京工業大学精密工学研究所(兼任)、88年東京大学先端科学技術研究センター助教授、92年生産技術研究所助教授、93年同研究所教授、98年先端科学技術研究センター教授、2002年生産技術研究所ナノエレクトロニクス連携研究センター長、07年ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構長、09年生産技術研究所教授、光電子融合研究センター長などを歴任してきた。11年から3年間は、ミュンヘン工科大学の客員教授も務めている。
最終講義は満席状態で、講義終了後に行われた懇談会にも多数の人々が出席、荒川教授の長年の労をねぎらうとともに、その業績を称え今後の活躍を期待する声が数多く寄せられていた。
◆研究の歴史
1982年、荒川教授(当時助教授)は恩師の榊裕之教授とともに、電子を三次元的に閉じ込めるナノメートル寸法の半導体立体ヘテロ構造の概念を提案した。これこそが量子ドットレーザの原点で、荒川教授は閾値電流特性や微分利得(変調特性)などの理論計算を行う一方、閾値電流特性の温度無依存化や変調周波数帯域の増大に関する磁場実験など、量子ドットレーザ黎明期における研究を先駆的に行った。
この頃、荒川教授はこの三次元量子閉じ込め構造を「多次元量子井戸」と呼んでいた。その後、1983年の後半頃からは「量子箱」と呼び始めたそうだが、実際できる構造は立方体ではなく、ピラミッドの形や半球状の形であるため、今では「量子ドット」という名称が定着している。量子ドットは、しばしば人工原子とも呼ばれている。
荒川教授はその後も研究を進め、量子ドットレーザデバイスの研究においては、1990年にGaAs系やGaN系材料を用いた量子ドットの結晶成長技術を開拓、2000年には高性能量子ドットレーザ、2008年にはシリコン上の量子ドットレーザを実現した。量子ドット光素子の研究においても、2002年に単一光子発生素子、2008年に単一量子ドットレーザ、2011年に太陽電池や遠赤外線センサ、2014年にはナノワイヤ量子ドットレーザを実現。量子光物性においては、1990年に量子ドット・量子細線の励起子物性、1992年に共振器量子電気力学、1995年に単一量子ドット分光、2002年には量子ドット・フォトニック結晶結合系に関する研究を行ってきた。
◆量子ドットレーザの特長
半導体レーザには、連続状態での自由キャリアの熱的拡がりによって、本質的に閾値電流の温度依存性が存在する。一方、固体・分子レーザは原子密度が低いため体積が大きく、電流注入が不可能なので小型化、集積化、低消費電力という点で課題を抱えている。
荒川教授は、量子ドットレーザは自由キャリアを閉じ込めることで熱的広がりを抑制でき、小型で電流注入も可能、温度安定性を有し、大量生産が可能なので、半導体レーザと固体・分子レーザが持つ課題を解決でき、双方の長所を有する理想の半導体レーザだと述べる。そして、「バルク中の電子は、運動場で自由に飛び回る子供のようなもの。しかし、これだと子供の取るエネルギーはバラバラだ。一方、量子ドット中の電子は、強制的に椅子に座らされた子供に例えることができる。椅子の大きさが同じなら、子供のエネルギーはすべて揃う」と語った。
シリコンフォトニクスにおけるレーザ光源としては、SiラマンレーザやGeレーザといったⅣ族光源の研究も行なわれている。しかしながら、現実的な解としてはハイブリッドシリコンⅢ-Ⅴ族レーザが有力と言われており、量子ドットレーザは低消費電力、高温耐性、反射雑音耐性の点から最適な光源とされている。集積化の手法としては、フリップチップボンディング、ウエハ貼り合わせ、直接成長などがあるが、荒川教授はこれらについても先駆的な研究を推し進めた。
◆産学連携プロジェクト
1990年代初頭まで、日本企業は大学が担当する基礎研究分野の一部まで担える余裕を持っていた。当時、企業側からは「大学は人材だけを育てて頂ければ十分」といった発言まで聞こえてきた。ところがバブル崩壊後、経済が低迷する中で日本企業は急速に体力を落としていった。基礎研究はもちろん、開発研究すら十分に行う余裕もなくなり、結果として基礎研究から生産までの役割分担の中に、企業も大学も担うことができない空白地帯が生まれてしまった。危機感を持った国は、積極的な施策を実施した。その結果、今では大学の役目は大幅に拡がり、開発研究から応用研究の一部までを担うようになった。大学に求められる役割は確実に変わった。
量子ドットレーザの実用化に関しては、2000年時点ではあまり期待されておらず、全体としては懐疑的であったという。この状況を大きく変えたのが国家プロジェクトだ。荒川教授は2002年からスタートした量子ドット関連の各種産学連携プロジェクトをリーダーとして継続的に推進してきた。
2002年度から2006年度までの文部科学省・世界最先端IT国家実現重点研究開発プロジェクト「光・電子デバイス技術の開発」は、経済産業省の高度情報基盤プログラム「フォトニックネットワークデバイス技術開発プロジェクト」と連携しながら進められた。東京大学生産技術研究所にはナノエレクトロニクス連携研究センターが設立され、荒川教授は研究センター長に就任した。プロジェクトでは量子ドット形成技術基盤開発、光子制御ナノ構造形成技術基盤開発、光電子制御技術基盤開発、ナノ光電子デバイス基盤技術開発などが実施され、量子ドット光デバイスの実用化は大きく前進した。2006年には量子ドットレーザを製品化する大学発・カーブアウト型ベンチャー企業、(株)QDレーザも設立された。
2006年度から2015年度まで実施された文部科学省・科学技術振興調整費先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム「ナノ量子情報エレクトロニクス連携研究拠点」プロジェクトでは、東京大学にナノ量子情報エレクトロニクス研究機構が設立され、荒川教授はこの機構長にも就任している。量子ドットレーザやフレキシブル電子デバイスの高性能化を図る一方、これらの要素技術をもとにして量子暗号や量子中継を含めた量子暗号ネットワーク技術や量子コンピュータの基盤技術を実証、太陽電池・量子ドット光検出器等の研究開発も行われた。
2009年度から2013年度までは、内閣府の最先端研究開発支援プログラム(FIRST)「フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発」プロジェクトが実施された。ここでは、電子と光子の融合によって半導体集積回路の限界を超えることをターゲットに据え、光源搭載型シリコンフォトニクス回路において、現状の100倍の10Tbps/cm2の高密度伝送方式を実現して2025年頃のオンチップサーバを目指した。革新的技術の探求とシステム実証を両立させ、最先端技術の先駆的研究と同時に、実社会に貢献する成果を創出することも目標に掲げた。成果としては、2012年度に30Tbps/cm2の伝送速度を達成、2013年度には25~125℃の環境下で20Tbps/cm2を達成して、温度無依存性を実証した。
2012年度から2021年度まで実施される経済産業省・未来開拓研究プロジェクト「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」では、光電子集積インターポーザの実現を目指している。計画では、第1期で光I/Oコアを開発、第2期では光I/Oコアを集積化して大容量LSIを光接続、2018年以降に事業化を行い、親会社の製品他に適用する計画だ。第3期では情報通信機器を中心に広くシステム化して、サーバの消費電力を30%減らすことを目標に掲げている。2017年には光I/Oコアの生産・販売を行なうアイオーコア(株)も設立された。
◆38年を振り返って
プロジェクトからは多くの人材も輩出された。量子ドット科学技術はフォトニクス分野にイノベーションを起こすと熱く語る荒川教授は、最後にこう述べて最終講義を締め括った。「1980年、生産技術研究所に講師として着任、小さな研究室を設立して以来38年間、東京大学で研究・教育活動に携わることができ、この間大学の社会的使命の多様化や産業構造の大きな変遷があったが、大学人として量子ドット研究の創始からその実用化まで、一貫して関わることができたのは幸運であり、工学者冥利に尽きる。長年にわたりお世話になった恩師の諸先生や同僚の先生方、研究室メンバー、産業界の方々に御礼を申し上げたい。そして、生研が世界をリードする研究を生み出すInstituteとして今後も発展することを祈念している。特に若い研究者の皆さんには、不連続な進展を求めて、果敢に挑戦することを期待したい。最後に、量子ドットの論文を出版した年に結婚した妻に感謝する」。
荒川教授は4月以降も、ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構の特任教授として、引き続き研究を継続するそうだ。(川尻 多加志)