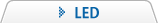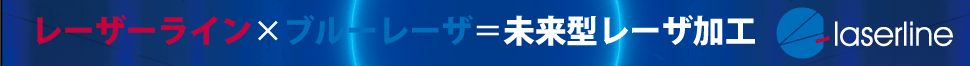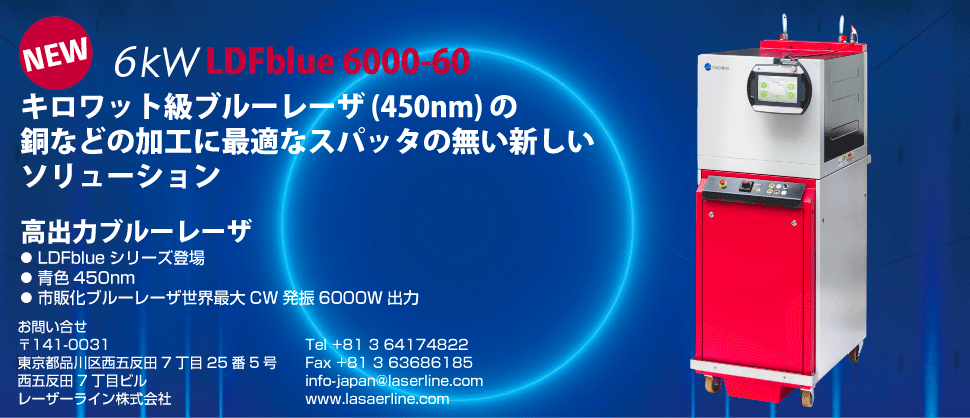Science/Research 詳細
近赤外光を吸収する有機化合物の合成に成功
June, 13, 2017, 豊田市--愛知工業大学応用化学科の森田靖教授と村田剛志准教授(物性有機合成化学)が、近赤外領域に強い光吸収帯を示す純粋な有機化合物の合成に成功した。
併せて、共同研究者の中井浩巳・早稲田大学理工学術院教授(理論化学)が、独自に開発した計算手法を適用することで、この有機化合物の集積体が示す近赤外光吸収帯の実験値の正確な再現化に成功した。変換効率の高い太陽電池への活用など、特異な電子的特性を生かした材料設計へとつながる画期的な成果となり、『Nature』の姉妹誌『npj Quantum Materials』のオンライン速報版に論文が掲載された。
森田教授・村田准教授の研究グループは、独自に分子設計・合成した電荷を持たない開殻有機π電子系分子(有機中性ラジカル分子)をトリオキソトリアンギュレン(TOT)と命名し、それを基盤とした基礎・応用研究を進めている。ベンゼン環が多数集まった構造を持つTOTは、結晶中で一次元的に無限に積層した大規模集積構造(一次元π積層ポリマ)を形成することが明らかになり、さらにこの有機化合物の集積体の光吸収特性を調べたところ、一次元π積層ポリマの積層方向に1100nmから1500nmの近赤外領域に吸収極大を持つ、強い光吸収を発現することを見出した。
中井教授の研究グループは、この近赤外光吸収の機構を明らかにするため、結晶構造から抽出した集積構造に対して量子化学計算を行った。その結果、分子間に新たな分子軌道が生成し、電子がそれらの軌道間で遷移することにより、近赤外光吸収が発現することが分かった。さらに、独自の計算手法である分割統治法を適用することで、従来の量子化学計算では困難だった励起状態にある大規模集積系の計算に成功し、光吸収の実測値を再現した。
森田教授は「従来の材料で見られる近赤外光の吸収は、ほぼ例外なく一分子の中の電子的相互作用により引き起こされるものでした。今回の研究成果は、一分子でなく、分子間の電子的な相互作用によって近赤外光の吸収が顕著に実現できた中性有機分子としては初めての例です」と説明している。
可視光線と赤外線の中間領域に波長を持つ近赤外光は、センサや光通信などの電子デバイスに広く利用され、近年は生体イメージングなど医療分野での活用も活発に研究されている。その中で、近赤外光に対して吸収特性を持つ有機電子材料の開発が注目を集めているが、通常の有機物は紫外~可視領域の光しか吸収できず、近赤外領域まで吸収波長を伸ばすことは困難だった。また、有機分子が示す光吸収などの特性を解析したり予測したりする有効な手段として量子化学計算が広く活用されているが、従来の方法では計算量が原子数の増加とともに急激に大きくなるため、最新のコンピュータを使用しても計算が完了しないという問題があった。
森田教授らが創成した近赤外光吸収材料は、有機中性ラジカルでありながら普通の閉殻有機物と同程度の高い安定性を持ち、さらに単占分子軌道(SOMO)という有機中性ラジカルに特有の分子軌道が分子間で強く相互作用して自己集合化したことにより、近赤外光吸収の実現に至った。また中井教授らの分割統治法の応用により、多数の分子の集合により発現する性質が扱えることも示され、今後の有機電子材料の設計・開発の進展に向けて大いに期待される成果となった。
(詳細は、www.ait.ac.jp)