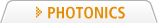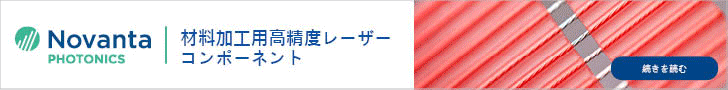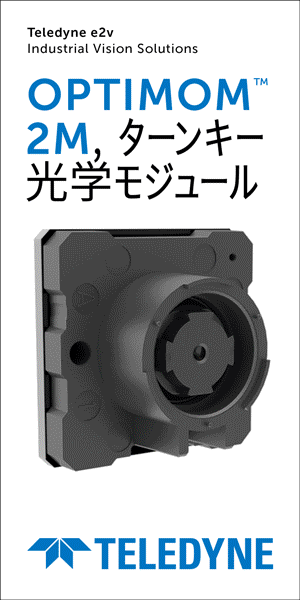Science/Research 詳細
目と脳を模倣した、色を識別する次世代光電子シナプス素子の開発

July, 14, 2025, 東京--東京理科大学 先進工学部 電子システム工学科の生野孝 准教授、同大学院 先進工学研究科 電子システム工学専攻 小松裕明氏(博士課程3年)、細田 乃梨花氏(2024年度修士課程修了)の研究グループは、色素増感型太陽電池を応用した新しい光電子デバイスの開発に成功した。
この素子は、人間の脳内に存在するシナプスを模倣した特性を示すもので、外部からの光刺激に応じて出力特性が過去の情報を保持しながら穏やかに変化するという特徴を持つ。さらにこのデバイスを、物理現象を計算資源として用いる物理リザバーコンピューティングのリザバー層として活用することで、入力される光の色の違いや、人間の動きの違いを分類できることを実証した。この成果は、自動運転、監視システム、スマート農業などに不可欠な、次世代マシンビジョン技術の飛躍的な発展につながると期待される。
従来のマシンビジョンシステムは、大量の視覚データをリアルタイムで処理する必要があるため、消費電力や処理速度に大きな制約があった。一方、この研究で開発されたデバイスは、自己発電で動作する「自己給電型」であり、外部電源を必要とせずに光の情報を処理できる。さらに、1つの素子で複数の色を識別できる波長応答特性をもつ点も特徴である。
この成果は、例えば次世代EV自動運転機能を支える超低消費電力のAI視覚デバイスの実現や、センサと演算機能が一体化したエッジAIシステムの構築に向けた大きな一歩となる。
今後の展望
この研究により、従来のマシンビジョンシステムが抱えていた「消費電力」「外部処理回路の必要性」「リアルタイム性に欠けるデータ処理性能」といった課題に対して、一つの解決策を提示することができた。色素増感型太陽電池を用いた光電子シナプスは、自己発電機能を備えた自律駆動型のデバイスであり、外部電源や複雑な補助回路を必要としない。さらに、デバイス内部で波長応答に基づいた時系列処理が可能であり、物理リザバーコンピューティングの枠組みによって、学習を伴う高次の分類処理を実現する。
このような機能を持つ小型デバイスの登場は、次世代マシンビジョンシステムの高度化を加速すると期待される。特に、人間の視覚に近い高分解能な色識別機能を活かした応用が見込まれる。たとえば、自動運転車両における周辺環境の即時認識、省電力で動作するウェアラブル生体センシングデバイス、小型の認識モジュールを組み込んだロボティクスシステムなどが想定される。
さらに、この研究で開発されたデバイスは、マシンビジョンにとどまらず、次世代コンピューティング技術として注目されている物理リザバーコンピューティングのリザバー層そのものとしても機能することから、高い汎用性を持つ。色素による波長選択性と、時間的応答特性を融合させることで、高分解能な色識別と論理演算を同時に実行可能であることもこのデバイスの大きな特徴であり、将来的に比較認識を含む低消費電力型AIシステムの中核技術としての応用が期待される。
研究成果は、2025年5月12日に国際学術誌「Scientific Reports」にオンライン掲載された。
(詳細は、https://www.tus.ac.jp)