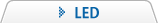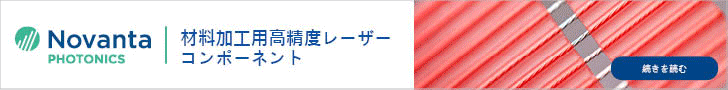Science/Research 詳細
名古屋大学、超解像蛍光イメージングに最適な超耐光性蛍光色素を開発
October, 29, 2015, 名古屋--名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)の山口茂弘教授、深津愛子准教授、多喜正泰准教授、WANGChenguang研究員、佐藤良勝講師、東山哲出教授らの研究チームは、生命現象などを可視化する超解像蛍光イメージングに最適な新しい蛍光色素分子fC-NaphoxJを開発し、この色素が従来の蛍光色素をはるかに上回る耐光性をもつことを明らかにした。
今回の研究により、従来の色素で、は困難で、あった超解像顕微鏡(STED顕微鏡)による繰り返し観測にも成功し、STED顕微鏡を実用レベノレに押し上げるための基盤技術を確立した。
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所の研究チームは、生命現象などを可視化する超解像蛍光イメージングに最適な新しい蛍光色素を開発した。
生体内の分子の動きを視るバイオイメージングは、現在の生物学研究に欠かせない研究手法の一つ。バイオイメージング技術の発展に大きく影響を及ぼしたのは、2014年のノーベノレ化学賞に選ばれた超解像顕微鏡の一つであるSTED顕微鏡。STED顕微鏡は、従来の蛍光顕微鏡の限界を大きく上回る高い空間分解能によって、これまで識別が難しかった細胞内にある小器官の構造やタンパク質の動きなどの観察を可能にした。しかし、強いレーザ光の照射を必要とすることから、タンパク質などに結合した蛍光色素の槌色が激しく、生きた細胞を視るライブイメージングなどの実践的なバイオイメージングへの応用が阻まれてきた。
ITbMの研究チームは、新たな蛍光色素分子「C-Naphox」を開発し、この色素が従来の蛍光色素をはるかに上回る耐光性をもつことを明らかにした。今回の発明により、従来の色素では困難であったSTED顕微鏡による繰り返し観測にも成功し、STED顕微鏡を実用レベルに押し上げるための基盤技術を確立した。
生体組織や生命現象を可視化するバイオイメージングは、現在の生命科学研究を支える基盤技術として急速に発展してきた。中でも、蛍光イメージングは、目的の物質が存在する場所や動きを蛍光として感度よく検出できるため、観察対象を生きたまま観察することができる。そのためライブイメージングの最も有力な手法として広く用いられている。
ところが、この蛍光イメージングには致命的な欠点が存在する。光を検出手段として用いる蛍光顕微鏡では、光の回折によって像がぼやけ、隣接した二つの物質が一つに視えてしまうため、顕微鏡で正確に観測できる対象物の大きさの下限(空間分解能)に制約が生じる。物理学者エルンスト・アッベが19世紀に提唱した「アッベの式」によると、観測可能な像の大きさは光の波長の2分の1までであり、400~700nmの波長をもっ可視光を 用いた場合には、200nmが理論上の限界ということになる。これに対して、細胞内小器官やウイノレス、DNA、タンパク質など、生命科学者が興味を持つ生体組織や分子の多くは200nm以下の大きさであり、蛍光イメージングでは鮮明に観察することは困難。微細な生体組織や生物活性分子の動きをありのままで観察する方法の開発は、生物学研究の手法に革新をもたらす重要課題であり、多くの研究者が渇望していた。
約10年前、この「200nmの壁」を超えることのできる新たな蛍光顕微鏡、超解像蛍光顕微鏡が発明された。1994年にStephanE. Hell博士(ドイツ・マックスプランク研究所)らによって開発された誘導放出抑制(stimulated emission depletion; STED)顕微鏡はその一つ。STED顕微鏡では、蛍光色素を結合(ラベル化)した対象物に、光(励起光)とそれをドーナツ状に取り囲んだSTED光の2種類のレーザを照射する。蛍光色素に励起光を照らすと、エネルギー状態の高い励起状態になり、蛍光を発しながら、徐々にエネルギーの低い基底状態に戻る。さらに蛍光色素の蛍光極大波長よりも長波長のSTED光を周りに当てることにより、その部分の蛍光色素のみに誘導放出現象を引き起こし、強制的にSTED光と同じ波長でのみ発光させる。この波長の光のみをフィノレタで取り除くことで、STED光の当たらない中心部のみの蛍光を高感度に検出することができるようになるため、数十nm程度にまで空間分解能を高めることができる。
しかし、これらの超解像顕微鏡を汎用的な手法として実用的に用いるためには、依然として大きな壁が存在した。その最も大きな壁が、蛍光色素の耐光性。超解像蛍光顕微鏡では、通常の蛍光顕微鏡と比べて格段に強いレーザ光の照射を必要とすることから、蛍光色素の複色が深刻な問題となっている。例えば、STEDイメージングにおいて、空間分解能はSTED光の強度が大きくなるほど高くなることが明らかにされているが、STED光を強くすることで、同時に蛍光色素の槌色も促進される。現在の耐光性蛍光色素の代表格であるAlexaFluor488や ATTO 488といった色素ですら、STEDイメージングに用いた際の光槌色は深刻で、あり、繰り返し 測定を行うことが困難であるのが現状。これでは、STED顕微鏡の強みである高い空間分解能を生かしたままライブイメージングを行うことができない。すなわち、超解像顕微鏡技術の本来の有用性を十分に発揮するためには、強力なレーザ光の照射にも耐えうる新たな蛍光色素の開発が必要不可欠である。
これに対して今回、研究グループは、従来の炭素(C)、窒素(N)、酸素(0)原子を中心とする分子骨格に、ホグ素(B)、グン(旬、ケイ素(Si)、硫黄(S)などの通常ではあまり用いられない元素を組み込むという分子デザインをもとに、新たな蛍光色素の開発に取り組んできた。その中で、15族元素であるリン(P)を含む有機蛍光分子の構造と蛍光特性の相関について調べる過程において、リンと炭素原子で橋かけした構造をもっC-Naphoxが極めて高い耐光性をもつことを発見した。
C-Naphoxは、現在最も耐光性に優れた蛍光色素として知られるAlexa Fluor488やATTO 488と比較しても圧倒的に高い耐光性を示す。例えば、強力なキセノンランプ(300 W)を用い て460±11nmの光を照射する実験を行い、2時間の光照射によってAlexaFluor488 とATT0488がそれぞれ初期濃度の26.2%および96.7%まで分解したのに対し、C-Naphoxは99.9%が分解することなく残っていた。同条件で12時間照射を行い、ATTO 488が 58.7%まで分解したのに対し、C-Naphoxは初期濃度の99.5%と、ほぼ定量的に生き残っているこ とが分かった。
研究チームは、C-Naphoxを用いて生きた細胞を染色し、STED顕微鏡を用いた蛍光イメージングへの応用を試みた。その結果、極めて強いSTED光の照射下で50回繰り返し観察を行っても、83%の初期蛍光強度を保持できることがわかった。同条件でAlexa 488を用いた場合には、数回の繰り返し測定でほぼ完全に褪色してしまうことと対照的な結果である。すなわち、C-Naphoxの例外的に高い耐光性により、従来不可能であると考えられてきた繰り返しSTEDイメ ージングが初めて実現した。
リンを鍵とする分子設計により超耐光性蛍光色素C-Naphoxの開発に成功し、この色素が生細胞の繰り返しSTEDイメージングにおいてもほとんど槌色しないことを明らかにした。この超耐光性蛍光色素の登場により、長時間の繰り返し測定を伴うタイムラプスSTEDイメージングや、ライブSTEDイメージングといった、従来の蛍光色素で、は不可能で、あった超解像蛍光イメージングが実現できると考えられる。今回開発した蛍光色素を近年発展のめざましい超解像顕微鏡技術
と組み合わせることで、数々の生命現象を高精細にイメージングできる手法の開発につながるものと期待される。
(詳細は、www.nagoya-u.ac.jp)