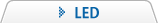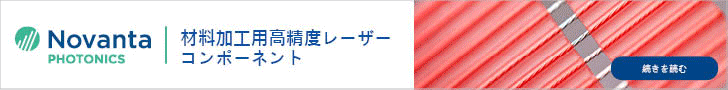Science/Research 詳細
光で細胞内の酵素のはたらきを自在に操作する
October, 7, 2015, 東京--東京大学の研究グループは、共同研究により、新規に作製した人工の光感受性分子とシミュレーション解析を用いて、細胞内における酵素活性の時間的な変動パターンを定量的かつ可逆的に光操作する手法の開発に成功した。また、開発した手法を用いて、酵素活性の時間的な変動パターンによって、細胞内で誘導される遺伝子発現の誘導強度が異なることを明らかにした。
研究グループは、東京大学大学院理学系研究科化学専攻の桂嘉宏大学院生と小澤岳昌教授、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の黒田真也教授の研究グループで構成。
研究で光操作の対象としたタンパク質リン酸化酵素Aktは、糖尿病やガンといったヒトにおけるさまざまな疾患において、その活性が異常な時間的変動パターンで上昇・下降することが知られている。そのため、Akt活性の時間的な変動パターンと細胞応答との関係性を詳細に解析しうる本手法は、今後、インスリンなどの薬剤の最適な投与量および時間の提案やAktが関与する疾患発症のメカニズム解明などに寄与することが期待される。
また、この研究で確立した一連の方法論は、Akt以外の分子にも応用可能である汎用性があり、近年注目が集まっている「生命機能を光によって意のままに操る」研究全般の発展に貢献することが期待できる。
人工の光感受性Aktの作製
共同研究グループは、植物由来の光受容タンパク質CRY2について、遺伝子工学技術を用いAktと融合することにより、光感受性のある人工Aktを作製。Aktは細胞質から細胞膜への移動により活性化する性質があるため、光照射によって細胞膜へ移行する設計をした。作製した光感受性Aktをマウス筋芽細胞内に発現させ、細胞外から光を照射し、光感受性Aktが分単位の時間スケールで可逆的に活性化することを確認した。活性化した光感受性Aktは、細胞内に内在する本来のAktと同様に、Aktの基質タンパク質をリン酸化し、Aktに支配される遺伝子発現や細胞極性の決定(細胞の移動方向の決定)などの生命現象を誘導することを確認した。さらに、レーザ光源を用いることにより、細胞内の特定の場所でのみAktを活性化させる「空間的な操作」も可能であることが示された。
人工光感受性Aktの活性の時間パターンを再現する数理モデルの構築
次に、作製した人工光感受性Aktの活性の時間パターンを定量的に光操作するシステムの開発に向けて、Aktの時間的な活性を記述する数理モデルを構築。この研究を含めこれまでにさまざまな分子種を対象とした光操作技術が開発されているものの、生体内における分子活性を精密に制御する方法論が不足していた。共同研究グループは、実験データに基づき、人工光感受性Aktの活性の時間的な変動を表す数理モデルの構築に成功。構築した数理モデルでは、さまざまな光照射パターンに伴うAkt活性の変動を正しく予測することが確認でき、定量的にAkt活性を操作する技術開発に成功した。さらに数理モデル構築の過程で、実験結果とシミュレーション結果との比較検討から、Aktの活性化メカニズムに、ポジティブ・フィードバックと呼ばれる活性化機構が関与することを新たに特定した。
Akt活性の時間的変動パターンの意義
構築した数理モデルと人工光感受性Aktを融合した一連のシステムを用いて、Akt活性の時間的変動パターンが持つ生物的意義について検討。活性化の強度と頻度が異なる3つの時間的変動パターンのAkt活性をそれぞれマウス筋芽細胞内で人工的につくりだし、それぞれのパターンにおいてAktによって調節されている遺伝子発現の誘導効率を比較した。その結果、Akt活性の総量が同じであっても、その時間的変動パターンによってAktによる細胞機能の誘導効率が異なることを発見した。従来の生物研究では、分子の「固有名詞」である分子名とその機能を一対一につなぐ研究が中心である一方、この結果は、分子活性の時間的変動パターンにも細胞機能の制御メカニズムが内包していることを直接的に示す結果である。
(詳細は、www.jst.go.jp)